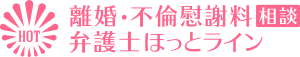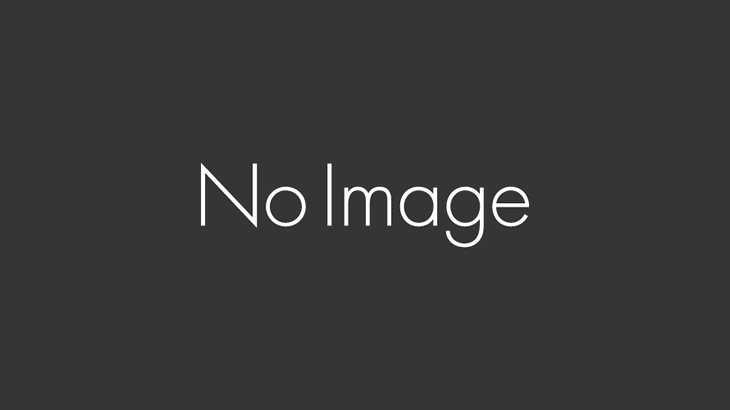- 「子どもの面会交流を拒否されたときの対処法が知りたい」
- 「元配偶者に面会交流を拒否されたとき、慰謝料請求はできる?」
子どもがいる夫婦の場合、離婚時に面会交流についての取り決めをするという方も多くいます。しかし取り決めをしたにもかかわらず、途中から面会交流を拒否されるケースがあります。一方で離婚当初から、面会交流を拒否されるという場合も。
そこでこちらの記事では、面会交流を拒否されたときの対処法について、詳しく紹介していきます。面会交流を拒否された人の中には、相手に慰謝料請求したいと考えている人もいるでしょう。慰謝料請求の可否やその方法についても紹介するので、参考にしましょう。
面会交流を拒否できる?
まずは「面会交流を拒否できるのか?」という疑問から見ていきましょう。
面会交流とは
前提として、面会交流とは親権を持っていない別居親が、自分の子どもと定期的に会うことができる権利です。民法第766条でも面会交流について、次のように定められています。
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
引用:民法|e-GOV法令検索
最近では、子どもが健やかな成長をするためにできるだけ悪影響を与えないという考え、いわゆる「子の福祉」が重視され、面会交流はこの福祉の観点からすべきというのが主流です。
原則として拒否できない
前出の通り、面会交流は子の福祉の観点からも必要な制度です。同居親の一方的な感情や判断で面会交流を拒否することは、基本的に許されません。
面会交流は親の別居後や離婚後に行われるため、親同氏の関係が悪いことも多いでしょう。しかしいくら親同士の関係が悪くても、子どもと親との間には関係のないこと。面会交流は、離れて暮らす子どもと別居親、双方にとっての権利です。同居親の勝手な判断で拒否できるものではありません。
面会交流を拒否したい、会わせないのは違法かを知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「面会交流を拒否したい!子供に会わせないことの違法性と対処法を解説!」
例外的に面会交流を拒否できる・認められないケース
しかし一方で、次のようなケースでは、例外的に面会交流を拒否したり、面会交流そのものが認められない可能性があります。面会交流は子どもの利益や福祉の観点から大変重要ですが、どのような場合でも常に認められるわけではありません。
子どもを連れ去られる危険がある
面会交流が子の連れ去りにつながると判断できる場合には、面会交流を拒否できます。本来、面会交流は子どもの健やかな成長にプラスになるからこそ実施されるべきもの。一方で同居親でない側の親が、面会交流を利用して子どもを連れ去った場合、子ども利益に著しい悪影響を与えることが考えられます。
そのため過去に子どもを連れ去ったことがある、または無断で連れ去ろうとしたなど、連れ去りの危険が高いと判断された場合には、面会交流の拒否や制限が認められます。
子どもを虐待する恐れがある
子どもが虐待される恐れがある場合もまた、面会交流を拒否できる可能性が高いです。とくに同居中に子どもへの虐待や家庭内暴力があり、その虐待が原因で離婚に至った場合などは、面会交流でも同様の虐待が行われる恐れがあると考えられるため。
その他何らかの方法によって子どもの心身を傷つける懸念があるときには、子どもの利益にならないため、面会交流は認められません。
子どもの虐待で慰謝料請求ができるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「子どもが虐待されたから慰謝料請求したい!配偶者ヘの請求方法を詳しく解説」
元配偶者にDV・モラハラがあった
元配偶者にDVやモラハラをしていた場合でも、面会交流の拒否が認められる可能性があります。とくに子どもが、加害者である別居親を恐れている場合などは、面会交流が子の福祉の助けにならないとして、面会交流を拒否される可能性が高いです。
このような場合には、手紙のやり取りやプレゼント、写真等を送ってもらうなど間接的な面会交流から始めるべきでしょう。
10歳以上の子ども自身が拒否している
子ども自身が面会交流を拒否している場合、基本的に面会交流は認められません。とくに10歳以上の子どもが拒否している場合には、面会交流が認められない可能性が高いでしょう。一方で10歳未満の子どもについては、同居親の影響を強く受けているケースもあるため、その点を考慮に入れて破断されます。
面会交流は子どもの幸せのために実施されるもの。そのため、最も尊重されるのは「子どもの意思」でなければなりません。子ども自身が嫌がっているのに無理やり面会交流させても、それは子の福祉に資さないと考えられます。
その他子どもの福祉に反すると判断できる場合
上記以外でも次のようなことがある場合は、面会交流の「拒否制限事由」に該当するため、面会交流を拒否される可能性があります。
- 子どもにとっての危険行為や犯罪行為をさせる可能性がある
- 子どもの学力低下や非行の原因となっている
- 子どもを通じて金銭の要求をする
- 子どもが乳幼児などで別居親が世話できなにもかかわらず、「1日預けろ」など無理な要求をする
面会交流を拒否されたときの対処法
同居親に子どもとの面会交流を拒否された場合、それを実現するために一体どのような方法が取れるのでしょうか。こちらでは拒否されたときの方法を8つ紹介していきます。
拒否された証拠を確保
面会交流を拒否された場合、まずは拒否されたことが分かる証拠を確保しておきましょう。その後の履行勧告や間接強制の申立、慰謝料請求のために必要だからです。相手とのやり取りを録音した、ボイスメッセージやメモなどはしっかりと保管してください。
その他、日々のやり取りやあったことを記録した日記なども、証拠となり得ます。また面会交流の内容について決めた書類がある場合には、必ずそろえて保管しておきましょう。
話し合いの場を持つ
次に元配偶者と話し合って、拒否している理由を理解して解決策を見つける必要があるでしょう。お互いに歩み寄りが可能な場合には、解決につながる可能性があります。具体的に話し合うポイントは次の通りです。
- 面会交流の重要性を訴える
- 拒否する理由や懸念点を聞き出す
- 子どもにとってより良い解決策を考える
- 必要であれば第三者を入れて話し合う
まず面会交流は、子どもの権利であり離婚しても両方の親に愛されていることが実感できる大切な機会であることを説明しましょう。そのうえでなぜ面会交流を拒否するのか聞き出してください。監護親にしてみれば、子どものスケジュールや体調との兼ね合いなど、やむを得ず拒否している場合もあるでしょう。
しかし再三にわたり面会交流を拒否されたり、手紙を子どもに渡すことすら拒絶されるといった場合には、弁護士や調停委員などの第三者を入れて話し合うことも検討してください。
面会交流調停・審判の申立て
面会交流を拒否された場合には、面会交流調停や審判の申立てという方法があります。離婚時に夫婦間で面会交流に関する取り決めをしていたが実際に面会交流を拒否された場合でも、家庭裁判所に面会交流調停の申立てが可能です。
調停は基本的に月1回開かれ、面会交流についての双方の希望や考えを出し合いながら話し合いを進めていきます。調停での話し合いがまとまらないときには、審判へと移行します。
審判では家庭裁判所の裁判官が、面会交流の有無について判断します。場合によっては、家庭裁判所調査官が親双方と子どもの面談調査を実施し、面会交流についての考えを述べることもあります。近年では、特段の事情がある場合を除き、基本的には実施の方向で意見を述べるのがほとんどです。
履行勧告の申出
調停や審判で面会交流についての取り決めがされたにもかかわらず、相手が面会交流を拒否し続けている場合には、家庭裁判所に「履行勧告の申出」をする方法があります。履行勧告とは、家庭裁判所の調停や審判で決めた金銭の支払いや面会交流の実施を守らない人に対して、家庭裁判所がその義務を履行するように指導する手続き。
調停や和解条項、審判または判決の主文に記載のある内容に限り、家庭裁判所が同居親に対して、面会交流を履行するように書面などで勧告してくれます。しかし履行勧告には強制力がないため、相手が応じるかどうかは未知数です。
再調停の申立て
同居親に面会交流を拒否する明確な理由があるときには、再度面会交流に関する調停を申し立て、面会交流の条件や内容を変更する方法がおすすめです。面会交流の時間帯や場所、第三者の立ち合いなど、拒否する理由となっている条件について見なおし、新たな取り決めをしなおすことで、面会交流が実現できる可能性も。
なお面会交流をすること自体に支障があるといった指摘がなされた場合などには、家庭裁判所の調査官立ち合いのもと、試験的に面会交流をするという「試行的面会交流」制度があります。試行的面会交流で問題が無ければ、当事者間だけでの面会交流に移行するという流れです。
間接強制の申立て
相手が履行勧告に応じないなど、面会交流を拒否された場合の手段の一つに、「間接強制」の申立てがあります。間接強制とは、「民事執行法」に基づく強制執行のひとつで、裁判所が「義務を履行しない場合には金銭(間接強制金)の支払いを命じる」などの決定を出すことで、心理的に圧力をかけ、自発的な履行を促すための強制執行の手段。間接強制の不履行1回につき、数万円程度の強制金を発生させることで、面会交流に応じてもらうようにする方法です。
間接強制が可能なのは、面会交流の条件等がきちんと決まっている場合に限られます。そのため面会交流の条件がきちんと決まっていないケースでは、そもそも間接強制が認めらえないでしょう。申立てを行うのは、家庭裁判所です。
とはいえ「子どもが拒否しているのだから間接強制できないのでは?」と考える同居親がいるかもしれません。しかし間接強制決定に関する過去の判例によると、「子どもが面会を拒否する理由や事情は、面会交流の審判で考慮されていたはず。そうである以上、子どもの意思は間接強制できない理由には該当しない」という結論が出ています。
参考:最高裁判所判例集|裁判所
親権者変更の申立て
同居親が悪意を持って面会交流を拒否している場合には、子どもの利益のためにも親権者変更の申し立ての検討が必要です。家庭裁判所に申立てて親権者変更が必要と判断されれば、面会交流を拒否している同居親から親権を取り上げて、あなたが親権を得られます。
また父母双方が親権者変更に合意している場合でも、親権者を変更するためには、必ず家庭再場所での手続きが必になります。調停で話し合いがまとまらないときには、引き続き審判で必要な審理が行われたうえで、裁判官によって結論が示されます。
父親が親権を取れる確率については、こちらの記事を参考にしてください。
「父親が親権を取れる確率は?重視されるポイント・親権獲得のためにすべきことを解説」
慰謝料を請求する
同居親が面会交流を拒否する場合、その理由によっては不法行為に該当し、損害賠償(慰謝料)請求が認められる可能性があります。慰謝料とは、相手の不法行為(ここでは正当な理由が合い面会交流の拒否)によって生じた精神的苦痛に対して支払われる金銭のこと。
面会交流の拒否により、別居親や子どもに対して精神的苦痛を与えたといえるだけの証拠が必要になります。慰謝料を請求するためには、家庭裁判所に「慰謝料請求調停」を申し立てることから始めます。
面会交流の拒否で慰謝料を請求する方法
上で少し触れたように、面会交流の拒否で慰謝料請求できる場合があります。こちらでは、面会交流の拒否で慰謝料を請求する方法について詳しく紹介していきます。
慰謝料相場
面会交流の拒否で慰謝料を請求した場合、受け取れる慰謝料の相場はどのくらいになるのでしょうか。過去の判例から見ると、慰謝料の相場は10万~100万円程度です。令和4年に口頭弁論が終結した損害賠償請求事件では、11万円の支払いが命じられました。
金額だけを見るとそれほど高額は期待できないのが分かります。一方で、次のような背景がある場合には、慰謝料の相場は高額になる可能性があります。
- 相手が協議に全く応じようとしない
- 面会交流を拒否された期間が長い
- 約束してから1度も面会に応じない
- 拒否の理由が一方的で身勝手である
慰謝料請求できる条件
面会交流の拒否で慰謝料を請求するためには、次の2つの条件を満たす必要があります。
- 面会交流について具体的な取り決めがある
- 面会交流の拒否が悪質で違法性がある
それぞれの条件について、詳しく見ていきましょう。
面会交流についての取り決めがある
面会交流の拒否により慰謝料請求が認められるためには、面会交流の取り決めがあるのが条件です。というのも「面会交流権が侵害された」と主張するには、それ以前に面会交流権があると認められる必要があるため。面会交流は、具体的な取り決めがあって初めて認められる権利だからです。
そもそも不法行為に基づく損害賠償が認められるためには「故意または過失により被害者に違法に損害を与えた」と認められる必要が。面会交流の拒否で慰謝料を請求する場合には、面会交流に関して取り決めた内容に違反したことが「違法」と評価される可能性が高いです。
これに対して取り決めの内容が「随時面会交流に応じる」などという抽象的なものだった場合には、面会交流の拒否により慰謝料請求が認められる可能性は低くなります。このようなことから、面会交流の拒否で慰謝料請求が認められるためには、面会交流についての取り決めがあることが条件の一つです。
拒否の理由が悪質で違法性がある
拒否の理由が悪質で違法性があることもまた、慰謝料請求が認められる条件です。不法行為には悪質なものからそうでないものまで段階があります。悪質な場合には精神的苦痛が認められやすく、受ける苦痛も大きくなるとみなされます。しかし悪質といえない場合には、受けた精神的苦痛が小さい、または慰謝料請求が認められるほどの苦痛が認められない可能性が。
具体的に面会交流の拒否が悪質で違法性が高いと認められるのは、次のようなケースです。
正当な理由なく拒否する
同居親が正当な理由なく拒否した場合、悪質で違法性が高いと認められやすいです。たとえ面会交流が拒否された場合でも「娘が昨日から熱を出し、今日は外出できない」という理由だった場合は、「拒否するのも仕方ない」と納得しやすく、正当な理由があるため慰謝料請求が認められません。
面会交流は親と子という人間同士の間で交わさせるものであるため、場合によってはルール通りに実施できないこともあるでしょう。拒否の理由に正当がある場合も多く、このような場合には慰謝料請求が認められません。
一方で「娘をあなたに会わせたくない」といった理由で面会交流を拒否された場合は、こちらの方が納得できずに怒りや悲しみといった感情が出てくるでしょう。このような理由に正当性はなく、単に会わせたくないからといった理由で拒否された場合には、慰謝料請求が認められる可能性がたかくなります。
長期間にわたり何度も拒否する
長期間にわたって何度も面会交流を拒否された場合もまた、慰謝料請求が認められる可能性が高いです。一度だけでなく何度も拒否されたケースでは、違法で悪質性が高いと判断されるため。またそれだけ長期に渡って拒否され続けていると、受ける精神的苦痛も大きなものになります。
慰謝料請求には証拠が必要
面会交流を拒否されたときに限らず、慰謝料請求を認められるためには証拠が必須です。相手の違法行為の内容を明らかにするために必要になります。面会交流の拒否に関しては、主に次の2つの証拠を準備してください。
面会交流の取り決めに関する証拠
面会交流についての取り決めた内容を証明するために、次のような証拠を準備しましょう。
- 離婚協議書
- 面会交流の内容を記した合意書
- 調停調書
- 審判調書
- 離婚裁判における和解調書(面会交流の取り決めを含んでいるもの)
- 公正証書
離婚時に協議によって面会交流の方法を決めたものの、書面化していないという場合には、面会交流の取り決めがあったことや内容を立証するのが非常に難しくなります。
面会交流を拒否された証拠
次に相手に面会交流を拒否されたという証拠も必要です。その点で次のような証拠があるといいでしょう。
- 拒否の理由に関するやり取り(メール・LINE・メッセージ・音声など)
- 日程調整に関するやり取り
- 実際の面会交流の内容についてのメモ・日記
- 子どもの意向に関する証拠(メッセージ・電話の音声など)
子ども自身の面会交流に対する意向を証拠として確保しておくことで「同居親の意思によって拒否されている」ということが主張できます。
弁護士に依頼する
面会交流の拒否で慰謝料請求するときには、法律の専門家である弁護士に依頼するのがおすすめ。面会交流の拒否で慰謝料請求が可能かどうかの判断が得られます。また相手との交渉を任せられるほか、必要な証拠についてや調停を起こすときのアドバイスが得られます。
とくに法律にかかわる争いには、多くの時間や労力が必要です。すべての手続きややり取りをすべて自分で行おうとすると、仕事やプライベートにも大きな影響が出てしまうでしょう。しかしこれらの手続きをすべて弁護士に任せることにより、精神的負担を軽減できるというメリットが期待できます。
面会交流を拒否されても…やってはいけないNG行為
面会交流を拒否されていくら悔しくても、次のような行為は絶対にしてはいけません。その後の手続きに不利になるだけでなく、あなた自身が犯罪者になる可能性があるからです。
子どもを連れ去る
いくら面会交流を拒否されたからといって、子どもを無理やり連れ去るのはNGです。たとえ自分の子どもとはいえ、監護親の許可なく子どもを連れ去ってしまうと、刑法224条の「未成年者略取・誘拐罪」に当たる恐れがあるからです。
刑事罰に処せられない場合でも、離婚調停など離婚後の面会交流の内容を決める場面で不利な状況になる可能性が高いでしょう。すでに離婚している場合には、連れ去りが再度起こり得ると判断されてしまうと、面会交流そのものができなくなります。一時の感情で衝動的な行動に出るのは、慎んでください。
面会交流中に子どもに「もっとお父さんに会いたい」「お父さんの住んでいるところに行きたい」といわれた場合も同様です。子ども希望を叶えてあげたいという想いをおさえ、「お母さんに相談してから決めようね」と答えてください。
連れ去り別居は違法か?について知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「連れ去り別居は違法?合法?親権獲得への影響と子どもを連れ去られたときの対処法とは」
養育費の支払いをストップする
面会交流を拒否されたのが苛立たしくても、養育費の支払いをストップするのはやめましょう。別居親の中には、面会交流を拒否されたまま子どもを近くで見守れない時間が増えると、親としての自覚や責任感が薄れて、養育費の支払いをストップしてしまう人が少なくありません。
また「面会交流できないなら養育費を支払わない」などと、面会交流を実現させる交渉材料として養育費の不払いをちらつかせる人もいます。しかし養育費の支払いは、面会交流の対価ではありません。面会交流を拒否されたからといって、養育費の支払いをストップしてもいい理由にはなりません。
そもそも養育費の支払いは親としての義務であり、親としての実感が得られない、面会交流を拒否されたといった理由で支払をストップすることは認められていません。調停や審判で養育費について取決めがあった場合、勝手に支払いをストップすると、預貯金や給与が差し押さえられる恐れがあるので気を付けてください。
養育費の支払いを減額したいという方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「再婚で養育費を減額できる?減額請求の方法と勝手に減額されたときの7つの対処法」
監護親の悪口をいう
いくら面会交流を拒否する相手のことが憎くても、子どもに向かって悪口をいうのはダメです。ただでさえ両親の離婚で子どもの心は傷ついています。片方の親からもう片方の親の悪口を聞かされるのは、子どもにとっては大変な苦痛です。
どんなに相手が悪いと思っていても、子どもにその怒りをぶつけるのは適切ではありません。「お母さん(お父さん)の悪口をいうならもう会いたくない」といわれてしまう可能性もあるので、子どもに悪口をいうのは慎みましょう。
まとめ
面会交流は子どもと別居親の権利です。基本的に拒否することはできません。しかし子どもを虐待した過去がある場合や配偶者にDV、モラハラがあった場合、10歳以上の子どもが拒否している場合などは、面会交流の拒否が認められる可能性があります。
もしすでに面会交流を拒否されている場合には、相手との話し合いで拒否の理由を明らかにし、解消できるものは解消すべきでしょう。それでもダメなら面会交流調停・審判の申立てや履行勧告の申出、間接強制の申立てを検討すべきです。場合によっては親権者の変更や慰謝料請求も有効な方法です。
面会交流の拒否で慰謝料請求するには、いくつかの条件があり必要な証拠を確保しなければなりません。困ったときには法律の専門家である弁護士に相談してください。請求が認められそうかや具体的な手続きを任せられます。まずは無料相談を利用して、親権問題や離婚問題に詳しい弁護士に話を聞いてもらいましょう。