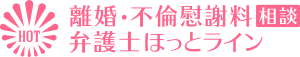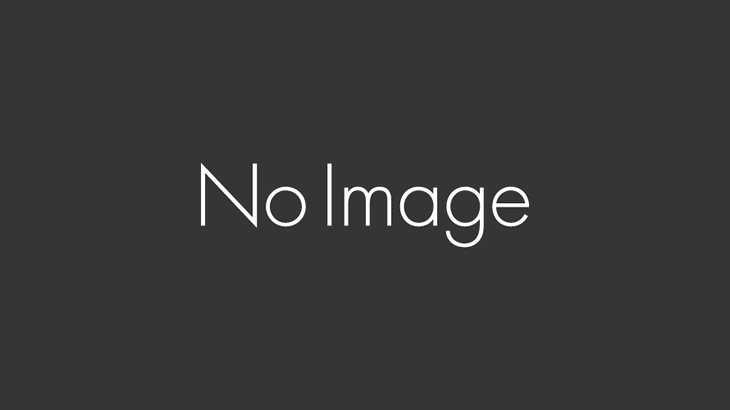- 「離婚前に財産分与のための口座整理とは?」
- 「財産分与で損しないための口座整理の注意点が知りたい」
離婚前に必要な準備として、財産分与のための銀行口座の整理があります。よりスムーズに財産分与で損をしないためには、口座整理は必須です。こちらの記事では離婚前に口座整理するときの注意点を詳しく解説していきます。これから財産分与の準備をするという方は参考にしましょう。
相手が隠し口座を持っていそうなときには、どの金融機関の口座にいくら預貯金が入っているが調査しなければなりません。また財産分与前に口座を解約したり、その口座からお金を引き出す場合には、注意が必要です。財産分与をより有利にするためにも、口座整理は慎重かつ確実に進めていきましょう。
離婚前の口座整理はなぜ必要?
財産分与を進める上で、口座整理は必須だと冒頭で紹介しましたが、では離婚前の口座整理はなぜ必要なのでしょうか。
離婚時の財産分与をする上で必要
離婚前の口座管理が必要なのは、離婚時の財産分与を進める上で欠かせない手続きだからです。離婚時には、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を公平に分け合う財産分与という手続きがあります。基本的には1/2ずつの割合で、専業主婦(主夫)であろうと共働きであろうと、財産分与の割合は原則として変わりません。
共有財産|財産分与の対象となる夫婦で築いた財産
婚姻期間に形成した財産を「共有財産」といい、財産分与は共有財産を公平に分ける手続きです。財産の名義がどちらかの単独名義であっても、共有財産に変わりありません。また夫婦の片方が専業主婦であっても、一方が仕事に専念できるのは他方の家事や育児労働に支えられているからと考えられるため、基本的に1/2ずつの割合で分けられます。
共有財産には、具体的に次のようなものがあります。
- 預貯金
- 現金
- 不動産
- 株式や有価証券
- 自動車
- 退職金
- 年金
- 保険解約返戻金
- 借金や借入金
- 子ども名義の預貯金
夫婦の収入からお金を出したのであれば、子ども名義の預貯金も財産分与の対象です。一方で子どもがもらったお年玉やアルバイトをして貯めたお金などは共有財産に該当しない可能性が高いでしょう。子ども名義の財産が共有財産に該当するかどうかは、ケースバイケースで判断されます。
預貯金や現金などプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどの借入金も財産分与の対象です。とはいえすべての借金・借入金が対象になるという訳ではなく、婚姻期間中に借り入れた家族が生活するために必要な借金に限られます。家族が住む家のローンや使用する車のローン、生活費のための借金は財産分与の対象ですが、自分の趣味のためのキャッシングやギャンブル、浪費のための借金は財産分与の対象外となります。
退職金を財産分与として請求する方法は、こちらの記事を参考にしましょう。
「退職金も離婚時の財産分与になる!金額計算から請求方法まで解説します」
特有財産|財産分与対象外の個人の財産
特有財産とは夫婦の協力とは無関係に形成・維持してきた財産のことで、結婚前からの財産や自分の親族から贈与・相続された財産を指します。特有財産は財産分与の対象とならないので、共有財産か特有財産か区別できるかが重要になります。
財産分与の基準時
財産分与の基準時についてですが、これは「いつの時点の財産をもとにして財産分与を行うかを決める基準時点」をいいます。具体的には、共有財産に当たるか特有財産に該当するかを判断するために必要です。共有財産を夫婦が協力して築いた財産とすると、財産分与の基準時は「夫婦の協力関係が終了した時点」となります。
夫婦の協力関係が終了した時点については、次の2つのタイミングが考えられます。
- 別居時
- 離婚成立時
夫婦の協力関係は家計の運営や家事の負担など、同居を前提とするものです。そのため離婚前に別居期間がある場合には、別居開始時点をもって夫婦の協力関係が終了したと判断されます。実務では原則として別居時を財産分与の基準時としています。
共有財産と特有財産を区別するために必要
離婚前の口座整理は、共有財産と特有財産を区別するために必要です。財産分与の対象は共有財産となりますが、独身時代から使っていた銀行口座を結婚後も引き続き使っていた場合、口座にある預金が特有財産か共有財産かを判断するのが難しくなります。
この場合、独身時代に貯めたお金は特有財産に、婚姻期間中にためたお金を共有財産に分けないと、全体が共有財産とみなされる可能性が高いです。
具体的な口座整理の方法
こちらでは具体的に、口座整理の方法について解説していきます。
結婚前からある口座
結婚前から使用している口座がある場合には、普通預金であれば結婚の前後で切り分ける必要が出てきます。具体的には同居を開始した時点からです。一方で独身時代に預け入れた定期預金であれば、特有財産となるため財産分与の対象とはなりません。特有財産であると証明するためには、通帳のコピーや取引履歴などを準備しておくといいでしょう。
婚姻期間中の預金がある口座
婚姻期間中に貯めたお金については、財産分与の対象となります。こちらも通帳のコピーを準備し、入手金記録の他に金融機関・支店・口座番号・口座名義が分かるように、コピーを取っておきましょう。
【ケース別】結婚前からある口座の整理方法
独身時代の銀行口座が結婚後も使用されている場合、婚姻期間中に残高の増減や口座間の資金の移動があるため単純に別居時点の残高から同居前の残高を差し引いていいとはなりません。こちらではケース別に、口座の整理方法を解説していきます。
同居前よりも残高が減った
別居時点での残高が同居前よりも減っていた場合はどうなるのでしょうか。例えば同居開始時点で口座に300万円あった残高が、別居時点では200万円に減っていたというケースです。ということは100万円のマイナスになるわけですが、この預金は財産分与の対象とはなりません。
つまり同居前よりも口座残高が減ったままになっているという場合は、財産分与の対象とならない点を覚えておきましょう。
同居前より残高が減ったのち元に戻った・増えた
同居前よりも一時的に残高が減ったものの、元に戻ったり増えたりした場合にはどのように財産分与したらいいのでしょうか。例えば、同居前の残高が200万円だったものが、結婚期間中に生活費などで使われて100万円にまで減少し、別居時点で300万円にまで増えたケースです。
結婚前よりも口座残高が減っている場合の財産分与には、次のような方法があります。
- 最も少なかった残高を特有財産とする
- 別居時点での残高を共有財産とする
- 同居期間中の入出金をすべて洗い出し、特有財産と共有財産に分ける
結婚前の口座から住宅資金の頭金を出した
結婚前の自分の口座から、住宅ローンの頭金を出したという人もいるでしょう。住宅ローンの頭金として結婚前の自分の預貯金から支払ったと証明したい場合には、次のような証拠が必要となります。
- 頭金を特有財産から出したと分かる、預貯金の取引履歴や贈与契約書
- 自宅の購入費用が分かる、不動産売買契約書
- 住宅ローンの借入額が分かる、金銭消費貸借契約書
このような証拠から「頭金を特有財産から出した」と証明できたとしても、購入時よりも不動産の評価額が下がっていた場合には、出した頭金分を特有財産とすることはできません。もう一方に対して不公平になるという考えから、頭金分をそのまま財産分与として受け取れる訳でないことを覚えておきましょう。
住宅ローンが残った家に離婚後も住む方法については、こちらの記事を参考にしてください。
「住宅ローンが残った家に離婚後も妻が住む方法|ケース別対処法と知っておくべき注意点」
結婚前の財産を勝手に使われた
では、結婚前の預貯金を配偶者に勝手に使われていた場合はどうなるのでしょうか。このケースでは財産の使い道がポイントになります。結婚前の預貯金を生活費のために勝手に使われた場合、共同生活を維持するために使用されたと考えられるため、配偶者に返還を要求しても、その請求が認められる可能性は低いです。
一方で配偶者の遊興のためや個人的な借金の返済に充てていた場合には、勝手に使われた分についての返還請求が認められる可能性があります。相手が請求を拒否することが考えられる上に、複雑な手続きが必要なので、弁護士に相談したうえで請求するかどうかを考えていった方がいいでしょう。
貯金の使い込みで離婚請求できるかについては、こちらの記事を参考にして下さい。
「夫や妻の貯金使い込みで離婚できる?別居時に気を付けたいこと&財産分与で損しない方法」
相手の隠し口座を調査する方法
財産分与では、財産の整理が必須です。そのため双方の預貯金口座を開示しあうことになります。中には通帳の開示を拒否する配偶者もいて、このようなときはどうしたらいいのでしょうか。
通帳開示を拒否できる?
通帳を開示したくないときは、拒否できるのでしょうか。たとえ夫婦であっても、通帳の開示を強要できません。また配偶者以外の人から開示を求められた場合にも拒否できます。相手が通帳の開示を拒否するかもしれないと思ったときには、次のような方法で隠し口座を調査していきましょう。
自力で調べる
別居前であれば、自力で調べる方法があります。具体的には次のような方法です。
家にある通帳を探す
まずは家に通帳やキャッシュカードがないか探してみましょう。相手から開示されている口座以外のものが見つかったときには、相手の隠し口座の可能性があるので、通帳のコピーや写真を取るなどして証拠を残しておいてください。なお不正な入出金があると主張したいときには、同居期間中のすべての通帳のコピーが必要です。
届いた郵便物を確認する
自宅に届いた金融機関からのDMや、お知らせのハガキなどから隠し口座の有無を調べる方法があります。把握している金融機関以外のところから郵便が届いた場合や、別の支店からお知らせが届いたときには、隠し口座を持っている可能性が。今までに自宅に届いた郵便物を見返すなどして、隠し口座につながる情報がないか探ってみましょう。
取引履歴を確認する
通帳の取引履歴を確認することで、隠し口座の存在が明らかになる場合があります。例えば把握している相手の銀行口座から、別の口座に振り込んでいる履歴が見つかるときがあります。振込先である別の口座が把握している口座の一覧の中に見つからないときには、他の口座を開設している可能性があります。
相手方から過去分の通帳や取引履歴を出してもらい、取引内容を調査することをおすすめします。
相手のスマホから探す
最近では通帳のないインターネットバンキングやネット証券が主流です。そのような口座を使用している場合には、家の中を調べるだけでは隠し口座を見つけることは困難です。相手のスマホを無断で操作することは推奨されることではありませんが、自分の隣で操作しているときや置かれたスマホの画面が表示されているときには、さりげなく金融機関のアプリが入っていないか確認しましょう。
任意の開示請求をする
自分で調査するのが難しいときや調査しても分からなかったときには、任意の開示請求をするという方法があります。離婚調停など裁判所で財産分与の手続きをしている場合には、相手方に対して通帳の開示請求をしていくことになります。
ただしこの開示請求は法的手続きでないため、相手が開示を拒否する場合があり、開示してくれたとして一部の場合も。また拒否されたとしても、何か罰則があるわけではありません。相手方が開示請求に応じないときには、以下のような手続きを取る必要があります。
弁護士会照会制度を利用する
相手が任意の開示請求に応じないときや他にも口座を持っていそうなときには、「弁護士会照会制度」を利用して、隠し口座の存在を明らかにできる可能性があります。弁護士会照会制度とは、弁護士法第23条の2に基づいて、弁護士会を通じて裁判所での手続きをする上で必要な調査をするために利用できる照会方法。
公的機関や公私の団体に対して、必要な報告を求められます。この制度を利用して対象の金融機関に照会をかければ、隠し口座の存在を明らかにできます。ただし金融機関によっては照会に応じるかを判断するガイドラインを設けているところがあり、応じるかどうかは金融機関次第です。
また弁護士会照会制度を利用するには、少なくとも相手方が口座を持っている金融機関名が分かっていないといけません。照会1件につき費用がかかってくるので、手あたり次第照会をかけてしまうと、膨大な費用がかかるのも注意が必要です。
裁判所の調査嘱託を利用する
弁護士会照会制度でも明らかにできなかったときには、裁判所の調査嘱託を利用する方法があります。調査嘱託とは裁判所を通して、官公庁や民間の団体に対して必要な事項の報告を求める手続き。裁判所を通して行われるので、弁護士会照会制度と比べても回答に応じてもらえる確率が高い方法です。
しかしこの制度を利用するには、裁判所に調停や審判、裁判が継続していることが条件です。また金融機関名だけでなく、支店名も特定していないと利用できないので、「どこかの銀行に隠し口座があるはずだ」というだけでは調査嘱託を利用できません。
離婚前に口座整理するときの注意点
離婚前に財産分与のための口座整理をするときには、次のような点に注意が必要です。
同居期間の長さで控除額が変わる可能性
結婚前からあった口座を結婚後も引き続き使っていた場合、同居期間の長さで特有財産として控除できる金額が変わってきます。同居期間が長期になるにつれて、独身時の貯金と別居時点での貯金とを完全に分離するのが難しくなるためです。
ある程度独身時代の残高が減っても、一定程度の同居期間中の収入によって補填されていたと考えられるので独身時代の残高を財産分与時に控除するのは相当でないという判断が下ったことも。とくに財産分与について調停や裁判で決める場合、担当の裁判官によって判断が変わる可能性が高いでしょう。
財産分与前の口座解約は慎重に
財産分与前に口座を解約するときには、慎重な判断が求められます。こちらでは自分名義の口座と相手名義の口座を解約するときの注意点を紹介していきます。
自分名義の口座
自分名義の口座を解約することは、自分の所有物を処分しているのに過ぎず、直接的に法的な問題にはなりません。とはいえ解約時期によっては、財産隠しを疑われるリスクがあるので、安易に口座を解約するのはおすすめできません。こちらでは別居前と別居後に解約した場合の注意点を紹介していきます。
別居前の解約
たとえ自分名義の口座であっても、別居前に解約するのはトラブルの原因となります。別居前、つまり財産分与の基準時以前に口座を解約してしまうと、口座に入っていた預金の行方を追えなくなる可能性があるため。解約時に払い戻された預貯金を、養育隠したり使い込んだりできてしまいます。
たとえ急な出費などやむを得ない事情があり口座を解約した場合でも、財産分与時には解約時の預金の行方をきちんと説明できるようにしましょう。説明できないと、相手に財産隠しを疑われてしまう可能性が高いです。
離婚時に貯金を隠すことは可能かについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚時に貯金を隠すことは可能?財産分与の基礎知識と不利にならない方法」
別居後の解約
別居後の口座の解約については、別居前の解約よりも警戒する必要はないでしょう。別居が開始しているということで基準時がはっきりしているため、別居後に口座を解約しても財産分与の対象から外れることにならないため。解約した口座については、通帳のコピーや取引履歴の開示で、別居時点での残高を確認できます。
相手名義の口座
相手名義の口座に関しては、相手方に所有権があるものなのでたとえ配偶者でも勝手に解約することはできません。実際の裁判例でも、口座に入っているのが婚姻期間中に形成された共有財産であっても、それは財産分与の対象となる財産を構成する一部を意味するに過ぎず、あくまでも名義人である相手方の財産であるとしています。
仮に相手に了承を得ずに勝手に口座を解約した場合、銀行をだましたとして詐欺罪などの刑法犯罪に当たる可能性も。配偶者が死亡したなどの特別な事情がない限りは、相手の承諾なしに勝手に口座を解約することはできません。
財産分与で名義変更が必要な財産については、こちらの記事を参考にして下さい。
「離婚時の財産分与で名義変更が必要?必要な財産ごとの手続き方法・必要書類・期限を詳しく解説」
勝手に口座からお金を引き出すリスク
では口座を解約しないまでも、お金を引き出すことは可能なのでしょうか。
自分名義の口座
財産分与前に自分名義の口座から預金を下ろすことは、問題なくできます。ただし普段全く動きのない口座から、多額の現金を引き出すなどすると、離婚に向けた準備をしているのではと怪しまれたり、財産隠しをしようとしているのではと勘繰られたりする場合も。
離婚後に宝くじを換金すれば財産分与の対象にならないか知りたい方は、こちらの記事を参考にして下さい。
「離婚後に宝くじを換金すれば財産分与の対象にならない?気になるポイントと財産分与の注意点とは」
相手名義の口座
相手名義の口座に関しては、原則として相手方に権限があるので、勝手に預金を引き出すべきではありません。しかし相手方から口座の管理を任されていたり、給与口座から生活費を引き出すことを許可されていたというケースは夫婦間でよくあることです。
このように相手方から管理を任されている口座であれば、生活の範囲内で預金を引き出すことが許されます。また別居後であっても、相手方から婚姻費用の支払いがないといった特別な事情があるときには、相手名義の口座から預金を引き出すことが認められる可能性があります。
口座整理するときのリスク
実際財産分与のために口座整理をする場合には、次のようなリスクに注意しましょう。
財産分与を請求する側
財産分与を請求する側(権利者)としては、別居前に口座を解約されてしまうと別居時点での残高を追えなくなってしまいます。通常財産分与を行う場合には、通帳残高や取引履歴を見て別居時点での残高を把握します。しかし口座を解約されてしまうと、解約した後のお金の動きは通帳に記録が残らないためです。
相手方が口座を解約してしまったときには、解約時に払い戻された預金が現在どのように管理され、別居時点での残高がいくらなのかについて、他の口座の取引履歴を含めて確認する必要があります。
財産分与を請求される側
財産分与を請求される側(義務者)としては、口座を解約した場合に財産隠しや浪費のために使われたと疑われないように気を付けて下さい。財産隠しを疑われると、相手方がし尚に財産開示に応じなくなる可能性が出てきます。またこちらがきちんと財産開示しているにもかかわらず、他に隠し財産があるのではと疑心暗鬼になり、その先の離婚協議が進まなくなることも。
財産を隠すつもりがない場合でも、口座を解約しただけで疑惑を与えることにつながるため、別居前の口座解約は極力しないようにしましょう。
解約後の履歴開示ではマスキングをしない
やむを得ない理由で口座を解約した場合、通帳のコピーや取引履歴を相手方に開示する場合があります。このとき取引履歴等の中身をマスキングすることは極力避けるようにしましょう。そもそも取引履歴等を開示するのは、財産隠しといった不透明な資金移動がないことを相手に証明するために行います。
にもかかわらずマスキングをしてしまっては、相手方の不信感を十分に払拭できません。親からもらった贈与だったり過去の借金の返済だったりと、隠したい取引履歴画あった場合でも隠さずきちんと開示しましょう。
離婚前の口座整理や財産分与に関するQ&A
こちらでは離婚前の口座整理や財産分与に関する、よくある疑問・質問にお答えしていきます。
財産分与の請求はいつまでもできる?
財産分与の請求には時効があり、その時効を過ぎると請求できなくなります(民法第768条2項)。基本的には離婚してから2年を経過すると請求できなくなりますが、離婚の種類ごとの時効の起算点は以下の通りです。
| 協議離婚 | 離婚届が受理された日から数えて2年 |
| 調停離婚 | 離婚調停が成立した日から数えて2年 |
| 裁判離婚 | 判決が確定した日から数えて2年 |
離婚した相手の通帳・取引履歴は見せてもらえる?
離婚前の口座整理で把握していなかった相手方の口座を見つけた場合、離婚後に相手の通帳や取引履歴は見せてもらえるのでしょうか。離婚が成立すると、夫婦は赤の他人になります。元配偶者であっても離婚後の開示請求に応じる必要がなくなります。
元配偶者が亡くなって子どもに相続させるためなど、特別な事情がない限りは金融機関も口座情報を開示してくれないでしょう。そのため、相手口座の把握は離婚前に念入りに行ってください。
口座を解約すると取引履歴は取れない?
口座を解約した後で残高を把握したい場合、取引履歴は取れるのでしょうか。多くの金融機関では解約口座のデータを10年分程度保管しています。金融機関によっては10年以上前のデータも保存している場合があるので、解約口座の取引履歴が欲しいときには、銀行の窓口で確認しましょう。
貯金の使い込みを証明するにはどうしたらいい?
配偶者によって共有財産の使い込みが発覚した場合、財産分与で自分の取り分が増える可能性があります。その場合には配偶者が共有財産を使い込んだことを証明しなければなりません。使い込んだかどうかは、利用目的や金額の他、家計の収支のバランスを踏まえて総合的に判断されます。
使い込みに該当するかどうかはケースバイケースの判断になるので、詳しくは弁護士に相談して下さい。
財産分与を有利に進める方法は?
財産分与を有利に進めるには、離婚問題に詳しい弁護士に相談するのがおすすめ。とくに配偶者との交渉がうまくいかない場合や、配偶者に隠し財産があると考えられるときには、弁護士に依頼したうえで相手と交渉してもらったり、弁護士会照会制度を使って財産調査を依頼しましょう。
調停や裁判で離婚そのものや財産分与など離婚条件について争うときには、裁判所とのやり取りなども代行してもらえます。別居前の口座整理には注意すべきポイントがたくさんあります。弁護士にアドバイスを受けたうえで、適切に口座整理を進めるようにしてください。
財産分与を弁護士に依頼する場合の費用は、こちらの記事を参考にしましょう。
「財産分与に関する弁護士費用|内訳別相場や変動する要素、安くする秘訣を解説」
まとめ
離婚前には財産分与を行うにあたり、別居時点での口座残高の把握や共有財産と特有財産とを分ける口座整理が必要です。結婚前からの口座を結婚後も引き続き使っていた場合には、残高の推移によって共有財産に含まれるかどうかが異なります。
また結婚前の口座からマイホームの頭金を出した場合や、配偶者に共有財産の使い込みをされた場合でも財産分与の方法が変わります。相手の隠し口座を探すには、自宅にある通帳や郵便物を確認するほかに、弁護士に依頼して弁護士会照会制度を利用する方法や裁判所の調査嘱託を利用する方法があります。
財産分与前に口座を解約したり預金を引き出すときには、後のトラブルを招かないよう慎重に判断したうえで実行に移しましょう。財産分与を有利に進めるには、弁護士に相談するのがベストです。相手との交渉を任せられるほか、財産調査や裁判所の手続きを代行してもらえます。