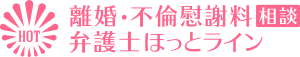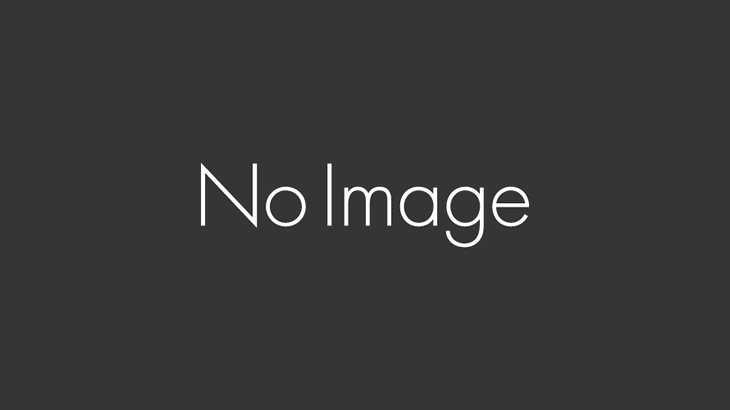- 「離婚を考えている別居中の妻に子どもを連れ去られた…」
- 「子どもの連れ去りが親権獲得に与える影響は?」
離婚時に子どもの親権を争っているケースで、しばしば問題になるのが子どもの連れ去り別居です。なんの断りもなく突然子どもを連れ去られた場合や、だまし討ちのような形で子どもを連れ去られた場合、離婚時の親権獲得に不利になってしまうのでしょうか?
こちらの記事では連れ去り別居が違法となるケース・ならないケースや、連れ去り別居が親権獲得に与える影響について詳しく解説。さらに子どもが連れ去られてしまったときに取れる対応や注意点、連れ去り別居に関する疑問・質問にもお答えしていきます。子どもを連れ去られてしまった、配偶者に連れ去られる可能性があるという方は参考にしましょう。
連れ去り別居とは?
連れ去り別居とは一般に使われる言葉で、法律用語などではありませんが、夫婦のどちらかが相手の同意を得ずに勝手に子どもを連れて別居をしてしまうことを指します。子どもの親権争いをしているときにしばしば問題になり、ケースによっては違法になる場合も
よくある連れ去りのケース
夫婦のどちらか一方が子どもを連れ去る事例として、次のようなケースがよくあります。
- 夫(妻)が仕事に行っている間に連れ去る
- 保育園や学校などに迎えに来た振りをして連れ去る
- 通学路で待ち伏せして下校途中に連れ去る
- 面会交流をしている最中に家に連れていき、監護親の元に返さない
状況的には、離婚の話し合いを始める前や始めた後、親権について協議を行っている間のケースが多いです。
連れ去り別居は違法になる?
では連れ去り別居は違法になるのでしょうか?いくら親といえ、もう一方の親の同意を得ずに子どもを連れ去って別居した場合は、違法と判断される可能性が。これは子の安定した監護養育環境を強引に変更し、不安定にさせる点に違法性があると考えられます。
連れ去ったときの状況や経緯などから、未成年者略取誘拐罪などの刑事罰対象となる可能性も。家庭裁判所において違法な連れ去り別居と判断されると、親権者決定に不利になったり面会交流を制限される恐れがあります。同様に連れ去られた側の親も、実力行使で子どもを連れ戻すと、違法と判断される可能性があるので注意が必要です。
離婚協議中の連れ去り別居
離婚協議中の連れ去り別居は、それぞれのケースで判断が分かれます。確かに離婚協議中であっても、夫婦は子どもの共同親権者。別居後の子の監護をどちらが行うかについては、夫婦で協議して決めるのが基本です。一方で話し合いなしで子連れ別居されたというだけでは、違法性が認められない可能性も。
別居から離婚が認められるまでの期間について詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。
「別居からの離婚が成立する期間はどれくらい?必要な期間や別居する際の注意点」
違法な連れ去りとみなされるケース
子どもの連れ去りが違法と認められる可能性があるのは、次のようなケースです。
- 子どもの親権に関して激しい争いになっている最中に子どもを連れだした
- 子どもが抵抗しているにもかかわらず、無理矢理連れて出ていった
- 面会交流後にそのまま監護親の元に返さなくなった
- 別居後の家にいきなり来て、同意も得ずに勝手に子どもを連れ去った
- 相手方が監護親になると取り決めがあったのに、合意に反して自分が子どもを連れて別居した
- 幼稚園や学校からすきを見て子どもを連れ去った
違法な連れ去りとはならないケース
一方で子どもを連れ去っても、違法とはならないケースがあります。
- 離婚前提の夫婦で合意の上での別居
- 子どもが虐待されていた
- 配偶者からDVやモラハラの被害を受けている側の連れ去り
- 他方の親に子どもを養育する能力がない
- 実家などへの一時帰省
相手からのDVやモラハラの被害が激しい場合、子どもにも同様の被害が及ぶ可能性があります。そのため被害を受けている側の配偶者が子どもを連れ去っても違法にはならない可能性が高いでしょう。
DV夫と早く離婚したいとお考えの方は、こちらの記事を参考にしてください。
「DV夫と離婚したい…早く安全に離婚するための手順・相談先・気になるポイントを徹底解説」
子どもの連れ去り・引き渡し調停は増加傾向
子どもの連れ去りで問題になるケースは、年々増加傾向にあります。最高裁判所事務総局がまとめた「子の監護に関する処分事件の事件動向について」という資料によると、「監護者指定」事件で家庭裁判所に申し立てられた件数は、調停・審判ともに右肩上がりで増加傾向です。
| 年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成26年 | 平成28年 | 平成30年 | 令和2年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調停 | 1,658 | 2,075 | 2,165 | 2,314 | 2,555 | 2,854 |
| 審判 | 1,312 | 1,590 | 1,920 | 2,167 | 2,327 | 2,244 |
平成23年で調停が1,658件、審判が1312件だったものが、令和2年では調停が2,854件、審判が2,244件と約10年で大幅に増加していることが分かります。
共同親権導入の一因に
子どもの連れ去り問題は、共同親権導入の一因となっています。共同親権とは、離婚後も父母共に子どもの親権を持ち、子どもの監護や教育、財産管理などに関する責任や権利を双方が負うこと。これまで離婚後は、夫婦の片方のみが親権を持つ「単独親権」だったものが、2026年までに「共同親権」に変更されることが閣議決定しています。
実はこの共同親権導入には、子どもの連れ去りが社会問題化した背景がありました。これまでは単独親権だったので、離婚時にどちらが親権を持つのか、夫婦で争いになってしまうケースがありました。しかし実際には離婚する前に子どもを連れて別居していて一定期間過ごした場合、子供を連れ去った側が親権獲得に有利になりやすいといわれていました。
これでは子どもを連れ去ったもの勝ちということに。このような状況を改善する目的でも、共同親権に変更される流れができたという訳です。
国際結婚では大きな問題に
国際結婚において、子どもの連れ去りは大きな問題に発展するケースがあります。というのも国際的なルールで「ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)」というものがあるからです。ハーグ条約の締約国は2024年5月現在で128の国と地域に及びます。日本は2014年4月にハーグ条約の締約国となっています。
ハーグ条約は子どもの福祉を考え、国境を越えた連れ去りの防止や元の居住国に迅速に返還させるための国際的な取り決め。外国人との間の国際結婚においてはもちろん、日本人同士の結婚であっても対象となります。国境を越えた16歳未満の子どもの連れ去りにハーグ条約が適用されると、条約に基づいて子どもの返還を求めることができます。
参考:外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締約国(地域)|外務省
子どもの連れ去りと離婚時の親権について
では子どもの連れ去りは、離婚時の親権獲得にどのように影響してくるのでしょうか?
親権者決定の原則
親権者決定の原則として、次のような項目を総合的に見て親権者をどちらの親にすべきか判断されるのが一般的です。
- 子どもへの愛情度合い
- これまでの監護実績
- 家庭環境
- 親の経済状況
- 親権者の健康状態・性格
- 育児の協力者の有無
- 子どもの意思
民法では15歳以上の子どもの親権について、子ども自身の意思を聴取して検討すべきとしています。
監護の継続性
家庭裁判所で親権者を決定する場合、「監護の継続性」が重視されます。監護の継続性とは、子どもの養育状況に問題がない場合、これまで養育していた人が離婚後も引き続き養育することが望ましいという考え方。ただでさえ両親の離婚で子どもは不安定になります。それに加えて生活環境まで変わってしまうと、精神状況がさらに不安定になる恐れがあるためです。
監護の継続性の原則により、たとえ違法な子どもの連れ去りにより監護が開始された場合でも、連れ去り後の生活が一定期間あれば、現在の監護環境を維持する方が望ましいと判断されるケースが多くありました。
父親が親権を取れる確率が知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「父親が親権を取れる確率は?重視されるポイント・親権獲得のためにすべきことを解説」
母子優先から母性優先へ
子どもの年齢が低いほど、とくに乳幼児については母子優先の原則が適用されていました。実際令和4年の司法統計では、母親が親権者となる割合は、離婚調停で「子の親権者の定め」をすべき全件数の約94%に上っています。
しかし現在では、母親であるというだけで妻側が有利になる傾向は少なくなりつつあるといわれています。「母親優先」から「母性優先」に変わりつつあるという訳です。つまり育児において母親的な役割を担っている親を優先とするという運用です。
親権争いで母親が負ける理由について知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「親権争いで母親が負ける理由とは?親権争いを勝ち取る6つの対策も解説」
親権獲得への影響
では子どもの連れ去りは、親権獲得にどのような影響があるのでしょうか。結論からいうと、連れ去りがあっても親権獲得に不利にならないのが通常です。とくにこれまで主に子どもの養育をしていた側の親が子供を連れて別居した場合は、不利になりにくいといえます。
また環境面でも、家を出た当初は子どもの生活環境が変わり、友だちとの交流が断絶するなどの悪影響があるものの、時間の経過に伴い新たな生活環境になじみ友人ができたりして、その悪影響を取り除く必要がなくなってきます。逆に子どもを連れ戻すと、再び生活環境を変えることによるデメリットを考えざるを得なくなります。
不利になるケース
次のようなケースでは、子どもの連れ去りが親権獲得に不利に働く場合があります。
- 子どもがはっきりと自分の意思を示せる年齢にもかかわらず、子どもの意思に反して連れ去る
- 子どもがこの家から離れたくないといっているのに強引に連れ出す
- 普段子どもの養育をしていない側が子どもを連れ出す
子どもの意思に反して強引に連れ去った場合は、親権獲得に不利になります。また普段子どものことを妻に任せきりという場合は、父親が子どもを連れだして別居すると不利になるでしょう。
不利にならないケース
一方で、連れ去り別居が不利にならないケースがあります。
連れ去った側に不貞行為がある
妻の不倫で離婚する場合でも、不倫しているからといって妻が親権獲得に不利になるということはありません。確かに相手の不倫で離婚する場合「不倫した人に子どもを任せられない」と考える人もいるでしょう。しかし不倫はあくまでも夫婦の問題で、子どもとの関りである親権とは法的に別問題として扱われるからです。
ただし子どもを連れ去った側の不倫が、子供の成長を妨げているとみなされる場合は、事情によっては不利になる可能性があります。
DVやモラハラする配偶者の元から子どもを連れ去った
一方の親にDVやモラハラがあったり、子どもへの虐待があった場合には、そのような親の元から早く離れた方が子どもの利益(幸せ)に即した行為ということになり、連れ去った側の親権獲得に不利になりません。逆にDVやモラハラをする側は、同居を続ける方が子どものためにならないと判断されて不利になります。
子どもが連れ去られたときの対処法
子どもを連れ去られてしまったとしても親権獲得に不利にならないということは、連れ去られてしまった側は「連れ去られ損」ということに。子どもの親権を取りたいと思っていた方はもちろん、連れ去られた子どものことが心配という方は、次のような対処をすべきでしょう。
配偶者と子どもの所在を確認する
まずは連れ去った夫や妻に連絡を取り、子どもの所在や安全、健康状態を確認してください。どこにいるか見当もつかないときは、警察に相談してもいいでしょう。また配偶者や元配偶者による連れ去りではなく、事件や事故に巻き込まれている可能性があるときには、迷わず警察に連絡しましょう。
相手と話し合いを試みる
子どもの無事が確認できたら、相手との話し合いを試みましょう。具体的には子供を連れ去った理由や子どもの返還について、そして離婚前であれば離婚が成立するまで同居できないかを聞いてみましょう。もし相手が話し合いに応じなかったり、両者の主張が平行線をたどる場合には、次の手段に出る必要があるでしょう。
子の引渡し調停(審判)を申し立てる
相手が話し合いに応じなかったり、話し合いに進展が見られないときには、家庭裁判所に「子の引渡し調停(審判)」を申し立てる方法があります。子の引渡し調停とは、連れ去られた子どもを自分の元に戻してもらうため、調停委員や弁護士を介して話し合いで解決を目指す手続き。
申し立てる家庭裁判所は、相手方の住所地を管轄する裁判所か、当事者の合意で定める裁判所です。調停の申立に必要な物は以下の通りです。
- 申立書とその写し
- 子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)
- 収入印紙1,200円分(子ども1人につき)
- 連絡用の郵便切手(各家庭裁判所に確認)
ただし調停ではあくまでも話し合いで解決を目指します。父母間での合意を得るのは相当ハードルが高いので、初めから「子の引渡し審判」から申し立てる場合が多いです。
子の監護者の指定調停(審判)を申し立てる
子の引渡し調停(審判)と同じタイミングで、「子の監護者の指定調停(審判)」を申し立てるのが一般的です。子の看護者の指定調停(審判)は、父母のどちらが子どもと一緒に暮らして監護するかについて合意を目指す手続き。こちらも調停で解決が見込めない場合には、審判から申し立てることができます。
子の監護者の指定審判では、次のような様々な事情を考慮したうえで、子どもが父母のどちらと一緒に暮らした方が健全に成長できるのかを考えて裁判所が判断を下す手続きです。
- これまでの監護の継続性
- 親の監護能力
- 環境とその環境への子の適応状況
- 看護補助者の有無
- 子の年齢
- 子の発達状況
- 子の意思
- 子と父母との結びつき
上記の中でとくに重要視されるのが、監護の継続性と子の意思です。意思の表明が難しい幼い子どもの場合、監護の継続性はとても重要です。また父母共に監護者として問題ない場合は、監護の継続性を重視して判断します。調停や審判を経て監護者に指定されれば、合法的に子どもを連れ別居できます。
審判前の保全処分(仮処分)
裁判所の決定を待っている間にも子どもの心身に危険が生じる、適切な看護が受けられそうもないというときには子の引き渡し審判とセットで、「子の引渡しを求める審判前の保全処分(仮処分)」を申し立てる必要があります。裁判所が認めれば、仮に子の引き渡しを命じることが可能です。
もっともこの保全処分(仮処分)を申し立てなくても、子の引渡し・子の監護者の指定調停や審判を申し立てられます。しかし保全処分(仮処分)も同時に申し立てることで、裁判所の期日が早まったり、調査官の介入時期が早まるなどのメリットも。とくに違法な連れ去りと考えられるときには、必ず保全処分(仮処分)を併せて申し立てるようにしましょう。
子の意思が尊重される
審判前の保全処分(仮処分)においては、子どもの意思が尊重されます。とくに15歳以上の子どもの場合、子の陳述を聞くのが原則とされています。15歳未満の子であっても、その意思は尊重されるとしています。子の意思の確認は、家庭裁判所の調査官による面接調査によって行われます。
このとき、仮に違法に連れ去られる形で相手方の監護を受けるようになったとしても、「お父さん(お母さん)のいる家には戻りたくない」と子どもが主張すれば、監護親を決める上でのポイントになります。
相手が応じないときには強制執行が可能
審判で子の引渡しが決定したにもかかわらず、引き渡しに応じないときには「強制執行」を行うことができます。強制執行には「間接強制」と「直接強制」の2種類があります。
| 間接強制 | 家庭裁判所が子どもを引き渡さない期間、一定の支払い義務を課すことにより、心理的に圧迫して子どもの引き渡しの実現を図る方 |
| 直接強制 | 家庭裁判所の執行官と一緒に子どもがいる場所に行き、子どもを連れ帰る方法
間接要請をしても相手が応じないときや、子どもに身に危険が迫っている場合などに行われる |
審判前の保全処分(仮処分)が認められて強制執行を行う場合、強制執行できる期間は相手に「子を仮に引き渡せ」と告知してから2週間以内と決まっています。
人身保護請求を行う
強制執行にまで至っても子どもを引き渡さないときには、「人身保護請求」を行うことが可能です。人身保護請求とは、人身保護法に基づき引き渡しに応じないことが子どもの利益(幸せ)に反していると明白であるとき、拘束されている子どもを取り戻す手続き。子の引渡しの手続きでは、最終手段といえます。
ただし人身保護請求が認められるのは、次のようなケースに限られます。
- 正当が理由がないのに拘束を受けている
- 相手の監護では子の健康が損なわれる恐れがある
- 子どもが満足のいく義務教育を受けられない
子どもが上記のような状況にあり、拘束の違法性が顕著だとみられ他の手段では子どもを取り戻すのは不可能と判断された場合です。人身保護請求は基本的に弁護士にしか行えない手続きです。人身保護請求を行う場合には、代理人として弁護士に依頼しましょう。
面会交流調停
相手が子どもを連れ去ったときの状況やその後の監護状況によっては、調停や審判をしても相手方に親権や監護権を取られてしまう可能性があります。そこでせめて定期的に子どもに会える機会を持てるよう、「面会交流調停」も併せて申して立てておくのもいいでしょう。
面会交流調停では、次のような内容について取り決めが行われます。
- 面会の頻度
- 面会の時間
- 面会の場所
- 当日の待ち合わせ方法
- 連絡方法
- 第三者の立ち合いの有無
- 学校行事への参加について
- プレゼントやお小遣いについて
調停を申し立てた側は、申立ての理由や経緯はもちろん、離婚や別居に至った経緯、子どもとの関係や面会交流に関して不安に思うことなどを聞かれます。
自力で連れ戻すのはNG
たとえ相手が違法に子どもを連れ去ったとしても、自力で取り戻そうとするのはおすすめできません。というのも、上記のような法的手続きがあるにもかかわらず相手方から自力で子どもを奪い返すと、違法行為である「自力救済」を行ったとみなされるため。
逆にあなたが違法な連れ去りをしたと判断され、親権獲得に不利になる可能性が。また面会交流を認められなくなったり未成年者略取の罪で刑事告訴される恐れがあるため、絶対にしないようにしましょう。
警察に連絡
悪質な連れ去りがあったり、その後の子どもの命にかかわる危険がある場合には、警察に連絡するのも一つの方法です。相手が未成年者略取及び誘拐罪で捕まる可能性があるのはもちろんのこと、警察官の説得で相手が子どもの引き渡しに応じる可能性も。
ただし警察では、配偶者や子どもを見つけることには協力してくれるものの、きちんと監護養育されていることが確認できれば、民事不介入(民事事件には関与できない)としてそれ以上の夫婦の争いには介入しません。もちろん親権争いにも関与しないので、その点は覚えておきましょう。
弁護士に相談
警察が動いてくれなかったときや、自分で法的手続きをするのが難しいときには、弁護士に相談して早期解決を図りましょう。とくに違法な連れ去りの場合には、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。というのも連れ去られてから時間が経てばたつほど、子どもを取り戻すのが困難になるため。さらに親権獲得にも不利になります。
自身のケースで違法かどうか判断ができない場合でも、まずは弁護士に相談し、どのような手段を取れるのかアドバイスをもらいましょう。
子連れ別居・離婚するときの注意点
子連れでの別居や離婚を考えている方は、次のようなことに注意が必要です。
面会交流の不当な拒否は親権獲得に不利になる
子どもを連れて別居した場合、相手から子どもと会わせてほしいと連絡が来ることがあります。また相手に面会交流調停を申し立てられるケースもあるでしょう。そのようなときできる限り面会交流をさせる必要があります。とくに理由もないのに(何となく会わせたくないなど)面会交流を拒否すると、後の親権獲得に不利になる可能性があるからです。
面会交流権は子の福祉のために認められた法的な権利です。子どもが過去に虐待された、今会わせると子の利益(幸せ)を害する恐れがある場合を除き、子の利益に配慮して相手方との面会交流に積極的な姿勢を示す筆王があります。
養育費や生活費について
別居後の養育費や生活費については、「婚姻費用」として収入の高い側に請求できます。別居したとはいえ家族・夫婦である以上は、互いに扶養義務を負うため。夫婦うち年収の高い側は、自分と同程度の生活を送れるように相手に婚姻費用を支払う義務があります。相手が子どもを連れて行った場合にはその養育費も含まれます。
婚姻費用の請求は別居開始から可能です。相手と直接連絡を取りたくない方や、請求しても応じない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てられます。
貯金ナシで子連れ離婚する場合の準備や手順については、こちらの記事を参考にしましょう。
「貯金なしでも子連れ離婚できる?必要な離婚準備と手順、ひとり親家庭向け公的支援制度とは」
違法な連れ去りとみなされないために
自分が子どもを連れて別居した場合、相手に違法な連れ去りとみなされないためには、なるべく平穏な形で、双方の話し合いで合意を得てから別居するのが原則です。逆に親権について激しい争いの最中に連れ出した場合や、無理やり子どもを連れだした場合、一時的な外出を装って連れたした場合には連れ去りが違法と判断される可能性があるので気をつけてください。
配偶者のDV・モラハラがあるとき
ただし配偶者のDVやモラハラが自分だけでなく子どもにも向かうようであれば、一刻も早く子どもを連れて家を出るべきでしょう。たとえ子どもには手を出していないとしても、子どもの前で大きな声で怒鳴ったり物を乱暴に扱う行為は、子どもに対するDV(面前DV)であるとみなされます。
DVやモラハラの加害者は被害者への執着が強く、別居後にトラブルになる可能性が高いです。トラブルが予想されるときには、警察や配偶者暴力相談支援センターなどに相談したうえで、「接近禁止命令」を出し、役所に新住所を開示しないような手続きを取りましょう。場合によっては子どもと共にシェルターなどに入り、身の安全を第一に考えてください。
DVする相手と離婚する方法や、「接近禁止命令」の出し方については、こちらの記事を参考にしましょう。
「DVから身を守る『接近禁止命令』を出すには?手続き方法・注意点・離婚の方法を詳しく解説」
別居後の子どものとのかかわり方
別居は子どもにとって大きなストレスになります。別居した直後は、子どもの体調の変化などに十分に気を付けるようにしましょう。転園・転校をしなければならない場合はもちろんのこと、そうでない場合でも引っ越しによる環境の変化や片方の親がいないことによるストレス、離婚するかもしれないという不安で心身の健康を損なう可能性があります。
親権について争いになった場合には、別居後の子どもの監護状況は調査の対象になります。子どもと一緒に住んでいるからこそ、子どもとの時間を多く取るように心がけ、親から愛されていることを感じさせて子どもの精神面の安定を図ることが大切です。
子どもの連れ去りや離婚に関する疑問・質問
こちらでは、子どもの連れ去りや親権、離婚に関するよくある疑問や質問にお答えしていきます。
子どもの連れ去りで慰謝料請求は可能?
子どもの連れ去りで、連れ去られた側は慰謝料を請求することができるのでしょうか?場合によっては、慰謝料の請求が可能です。例えば連れ去りが不法行為と認められたケースや、違法な連れ去りによって婚姻関係が破綻したと認められたケースなどです。
子どもの連れ去りによって有責配偶者と判断されれば、有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められなくなります。子どもを連れ去った立場で相手から慰謝料を請求されたときは、相手からの虐待やDV、モラハラなどの正当な理由で別居したことを証拠を元に立証していく必要があります。
子どもが虐待されたことによる慰謝料請求の方法については、こちらの記事を参考にしましょう。
「子どもが虐待されたから慰謝料請求したい!配偶者ヘの請求方法を詳しく解説」
連れ去り別居した妻からDVやモラハラをでっちあげられたときは?
最近多いのが、でっちあげ(冤罪)DV・モラハラによる子どもの連れ去りです。実際にはDVやモラハラに該当するような行為がなかったにもかかわらず、虚偽のDV(モラハラ)被害を日記形式にしたものを証拠にし、子どもを連れ去った上で離婚や慰謝料を請求するという手法です。
相手がでっちあげDVの証拠を提出してきた場合には、事実に反する点がないか探し、証拠を集めたうえで事実でないことを証明する必要があります。でっちあげだと立証できなければ、子の福祉の点から親権獲得に不利になる可能性があります。
でっちあげられたDVやモラハラを否定する場合、1人で戦うのは難易度が高いです。必ず法律の専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
別居中から自分の扶養に入れておくべき?
子どもと一緒に家を出た場合、離婚前の別居の段階から自分の扶養に入れるべきかお悩みだったり、親権獲得に有利になるのではとお考えの方がいるかもしれません。子どもが夫婦のどちらの扶養に入っているかは、健康保険や税法上の問題で、親権の判断にほどんど影響がありません。
しかし相手の扶養に入ったままでは、健康保険の更新などの手続きをいちいち相手に依頼する必要があります。そのため子どもを連れて別居した場合は、自分の扶養に入れておいた方がいいでしょう。配偶者の扶養から子どもを外す場合は、相手の会社に「資格喪失証明書」の発行を受ける必要があります。相手が協力を拒否した場合には、相手の健康保険組合に直接対応を求めてください。
連れ去られた子どもを連れ戻すためのポイントは?
連れ去られた子どもを、手元に連れ戻す手続きをすべきかの判断は慎重にすべきでしょう。あらかじめ子の引き渡しが認められやすいのか認められにくいのかを把握したうえで、無謀な挑戦にならないように判断してください。具体的には次のような項目を検討し、総合的に判断してください。
| 連れ去られた状況 | 別居開始時に相手が子どもを連れて出ていったのか
別居後に自分と同居している子どもを連れ去られたのか 連れ去り行為の悪質度合い |
| 連れ去られてからの養育期間 | 相手に連れ去られてから時間が経過すればするほど不利になる |
| これまでの主な養育者はどちらか | 連れ出した側がこれまでの主養育者だった場合、こちらの連れ戻しや親権獲得には不利になる |
| 現在の養育環境に特別な問題があるか | 連れ出した側と子どもとの生活環境に問題がない場合には、不利になる |
| 連れ戻した後に適切な養育環境を確保できるか | 子どもを連れ戻せたとしても、こちらの養育環境が確保できない場合には引き渡しは認められにくい
逆に今まで主養育者でない場合でも、実家の親と同居して子どもの養育を両親と分担できるようなケースでは認められる可能性がある |
まとめ
子どもの連れ去り別居が違法か合法か、親権獲得に有利か不利かは、連れ去られた状況や養育期間、今までの主養育者がどちらかということによって異なります。また相手のDVやモラハラから逃れるための連れ去りは、親権獲得に不利になりません。
どうしても相手から子どもを連れ戻したいときには、子の引渡し調停(審判)・子の監護者の指定調停(審判)・審判前の保全処分(仮処分)・強制執行・人身保護請求などの方法があります。間違っても自力救済したりせず、警察に相談したり弁護士の力を借りながら合法的に連れ戻すようにしましょう。
違法な子どもの連れ去りや不法行為があった場合には、慰謝料請求が可能です。一方で違法な連れ去りとみなされないために注意を怠らず、面会交流は適切に行うようにしましょう。連れ去られた子どもを連れ戻すべきか判断に迷うときには弁護士に相談し、連れ戻せる可能性や親権獲得への影響などを検討しましょう。