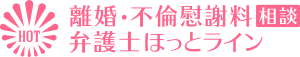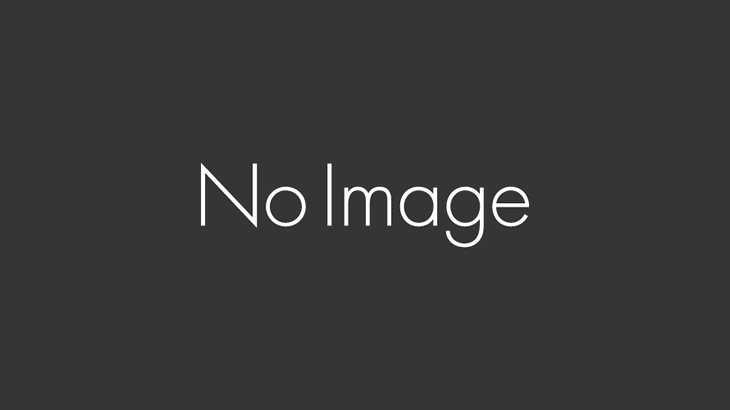- 「共同親権になれば男性でも子どもの親権を取れる?」
- 「父親が親権を取るためのポイントが知りたい」
離婚時に子どもがいる場合、親権をどちらが持つかは争点になりがちです。とくに双方とも親権獲得を希望している場合、壮絶な争いになるのは避けられません。また2026年に導入される予定の共同親権でも、共同親権になるか母親の単独親権になるかの争いは生じます。
どうしても子どもの親権を獲得したいという男性の場合、あらかじめ親権についての知識や重要視されるポイントを知る必要があります。実際に男性が親権を獲得するのはそう簡単なことではありません。親権獲得のために必要なポイントをおさえ、ときには専門家の力を借りながら子どもとの生活を実現できるようにしましょう。
親権の基礎知識と重要視されるポイント
男性が子どもの親権をとるために、まず親権についての基礎知識を紹介していきます。親権獲得で重要視されるポイントもあるので、参考にしましょう。
親権とは未成熟の子どもに対する権利義務
親権とは、未成熟の子どもに対して行使する「権利義務」のことです。文字を見ると「権利」のように思えますが、社会的に未成熟な子どもを保護して心身の成長を促す親の「義務」としての意味合いのほうが強いです。
親権には純粋な権利ではなく親としての義務も伴うため、「子どもと離れたくない」という感情だけで希望するものではありません。親権を獲得した以上、親としての義務を果たさなければならないことも頭に入れておきましょう。
子どものメンタルに配慮した離婚の伝え方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「【離婚】メンタルに配慮した子供への伝え方&ケアの方法|離婚が子供に与える影響と伝えるときの注意点」
親権の中身
親権には「財産管理権」と「監護権」の二つがあります。それぞれの内容は以下の通りです。
財産管理権
財産管理権とは、子ども名義の預貯金や不動産といった財産の維持管理、その他の法律行為の代理及び同意する権利義務のことです。維持管理には具体的に財産の保存・利用・改良・処分といった内容が含まれます。また財産に関する契約などの法律行為を代理で行えます。
子ども自身が財産を持っているというケースがそう多くありませんが、親族からの贈与や相続、離婚後に子どもに支払われる養育費などが想定されます。一方で子どもの行為を目的とする債務(借金)が生じる場合には、本人の同意を得る必要があります。
身上監護権
身上監護権とは、子どもと同居して子どものしつけや身の回りの世話をする義務のことをいいます。単に「監護権」という場合もあります。身上監護権には、次のような内容が含まれます。
| 監護・教育権 | 子どもを保護し、適切な教育を行う権利 |
| 居場所指定権 | 子どもの住む場所を指定できる権利 |
| 懲戒権 | 子どもに対して必要なしつけを行う権利 |
| 職業許可権 | 未成年の子どもの職業や労働の許可、もしくは制限を行う権利 |
| 身分行為の代理権 | 子どもの代理として、特別な手続きなしに身分行為の手続きを行う権利 |
| 身分行為の同意権 | 未成年の子供の婚姻時に必須である親権者の同意 |
二つの権利義務の関係
親権には財産管理権と身上監護権の二つがありますが、一般的にそれら二つをひとまとめにして「親権」と呼びます。例外的に身上監護権のみを別にして、「親権」と「監護権」を分ける場合があります。財産の管理は父親が相応しいものの、海外赴任などで子どもと一緒に暮らせない場合などです。
しかしこの場合は子どもの財産に関する手続きの度に、父親に連絡して同意を得る必要があります。このような手続きの煩雑さが生じることを頭に入れたうえで、親権者と監護権者とを分けるようにしてください。
親権で重要視されるポイント
親権で重要視されるいくつかのポイントがあります。親権者を決める上で大切なことになるので、男性が親権を取りたいと考えたときはよく理解しておきましょう。
子の利益と福祉に反していないか
親権者を決めるときに最も重要視されるのが、「子の利益と福祉に反していないか」という点。「子の利益」というのは「子どもの成長や幸福に取って一番良いこと」という意味です。そして子どもが心身ともに健やかに成長し安心して生活できるような状態を保ち支援するというのが「子の福祉」における基本的な考え方です。
また子どもに対して精神的・肉体的な虐待をしていた場合も、親権者としてふさわしくないと判断されます。経済的に豊かである必要はありませんが、ギャンブルや浪費で借金を繰り返していたり、財産管理能力に問題があると判断されると、親権獲得に不利になります。
これまでの監護実績
親権獲得のためには、離婚前までの子どもの監護実績が重視されます。というのもこれまで子どもの世話を適切にしてきたという実績は、離婚後の監護能力や監護に対する意欲が期待できるため。離婚前まで子どもの世話を母親にまかせっきりにしてきた男性は、この点において不利になる可能性が高いです。
子どもの養育環境
子どもの養育環境で親権者を判断するにあたっては「継続性の原則」がポイントになります。継続性の原則とは、離婚前後で子どもの養育環境に大きな変化がないことが望ましいという考え方です。離婚は夫婦間の問題であり、子どもにかかかる負担やストレスはできるだけ少なくすべきと考えられています。
そのため今まで世話をしてきた方やこれまで育ってきた環境を変えずに済む方の親が、親権獲得に有利になる可能性が高いでしょう。離婚前に家を出て別居していた方は、子どもを連れて家を出たとしても別居先で安定して暮らしていたと判断できれば、別居後の生活を維持する方が子どものためになるとみなされるでしょう。
子どもの年齢
子どもの年齢も親権者の判断に影響します。日本では「母子優先の原則」があり、子どもの年齢が小さいほど特に乳幼児の場合には、母親が親権者を持つのにふさわしいとされています。とはいえ最近では、父親が母親の役割を十分に果たしているケースでは、子どもの年齢が低くても父親に親権を認めるという判決が出ています。
母子優先の原則は10歳までの子どもにより大きな影響が働きます。一方で10歳以上の子どもに対しては、子どもの意思を聞き親権者の判断に参考にする裁判所もあるようです。
監護補助者の有無
子どもの監護を補助してくれる人がいるかどうかも、親権者の判断に影響します。離婚後に子どもを一人で育てていくとなった場合、仕事と育児を自分だけで両立しなければなりません。とくに正社員として働くとなると、どうしても子育てに充てる時間が短くなってしまうでしょう。
子どもの生活への影響が懸念されるため、子どもの世話を助けてくれる人が近くにいるかどうかも親権が獲得できるかにかかわってきます。近くに両親や兄弟など、育児をサポートしてくれる人がいる方が、親権獲得に有利になります。
きょうだいの有無
子どもが複数いる場合、「兄弟姉妹不分離の原則」が影響します。これまで一緒に育ってきたきょうだいがいる場合、離婚後も一人の親権者によって一緒に育てることが望ましいという考えです。この原則は子どもの心理面への影響に配慮した考え方で、兄弟姉妹を一緒に引き取って育てることができる方の親が親権獲得に有利になります。
しかし夫婦がそれぞれ子どもを連れて別居し、その期間が長期間に及んだ場合には、継続性の原則を優先して、一緒に住んでいた親がそれぞれの子どもの親権を持つケースが多いです。また子どもがある程度大きくなっていて、自分でどちらと住むか決められる場合にも、例外的にきょうだいの親権を分離することがあります。
親権者の健康状態
親権者の健康状態も、親権獲得に影響します。子どもを適切に養育するためには、親の心身の健康状態が安定している必要があるからです。精神疾患のために絶えず精神が不安定な場合や、重い病気を抱えて入退院を繰り返しているようなケースでは、子どもを適切に養育できる状態ではないと判断される可能性があります。
子ども自身の意思
子どもの年齢が高い場合、子ども自身の意思が親権に影響します。日本では15歳以上の子どもがいる場合には、必ず裁判所がどちらの親と一緒に暮らしたいかを子ども自身に確認します。子どもの意思を確認したうえで、子どもが望む方を親権者とします。この年齢になるとある程度、自我や価値観が確立しているとみなされるためです。
面会交流についての寛容性
面会交流についての寛容性も、親権の判断で重要視されます。面会交流とは、離婚後に親権を持たない側の親と子どもとが、定期的に会い交流することです。面会交流は子どもの心身の成長に必要で、こどもにとっての権利でもあるので、「別居親と会いたい」という子どもの気持ちを汲んで面会交流により協力的な親の方を親権者とする傾向があります。
ただし別居親に配偶者へのDVや子どもへの虐待があったなど、面会交流を拒否できるような正当な理由があれば、親権の判断に影響しません。
親権をめぐる男性の現状について
こちらでは親権をめぐる男性の現状と共同親権が導入された場合にどうなるか、父親が親権に有利になるケースについて解説していきます。
男性が親権をとれる確率
総務省統計局が行っている2020年の「人口動態調査」によると、夫婦に間のすべての子どもの親権を持つ割合は、父親が11.8%、母親が84.7%と母親の王が圧倒的に多い現状です。子どもの数が多ければ多いほど、母親が親権を持つ確率も高くなります。こちらは子どもの人数ごとに、父親が親権をとる確率の一覧です。
| 子どもの人数 | 確率 |
|---|---|
| 1人 | 12.9~13.2% |
| 2人 | 10.8~11.8% |
| 3人以上 | 9.3~10.0% |
父親が親権を取れる確率について詳しくは、こちらの記事を参考にしましょう。
「父親が親権を取れる確率は?重視されるポイント・親権獲得のためにすべきことを解説」
共同親権について
ニュースや報道でご存じの方がいるかもしれませんが、2026年までに「共同親権」が導入される予定になっています。これまで離婚後は、どちらか一方の親が親権を持つ「単独親権」が一般的でしたが、共同親権などを定める改正民法が2024年5月に可決され、2026年5月までに共同親権制度が開始される見通しです。
共同親権施行後は、共同親権か父母どちらかの単独親権になるかが争点となります。例えば父親が共同親権を希望しているのに対して母親が単独親権を主張しているケースで、次のような事情があれば母親の単独親権になる可能性が高いです。
- 父親が子どもを虐待していた場合
- 父親が母親にDVをしていた場合
- 母親の方が親権者としてふさわしく、かつ父母が共同で親権を持つことが難しい場合
尚3の判断に関しては、共同親権施行前の親権者の判断基準が参考になります。
共同親権のメリット・デメリットは、こちらの記事を参考にしましょう。
「共同親権のメリット・デメリット|民法改正による変更点と親権の決め方を徹底解説」
すでに離婚している場合は変更可能
共同親権が導入される前に離婚している場合は、親権者変更の手続きによって共同親権に変更することができます(改正民法719条6項)。家庭裁判所に「親権者変更調停」を申し立てて変更が相応しいと判断されれば、裁判所からの許可証(審判書謄本)を役所に持参して、子どもの入籍届出を行います。
実際にどの程度共同親権に変更できるかは未知数ですが、今までの傾向から見ると母親が共同親権に強く反対しているケースでは、簡単に変更できない可能性が高いです。
親権争いで男性が有利になるケース
父親は母親に比べると親権獲得の面で不利になりがちです。しかし母親に次のような問題行動がみられるときには、子どもの監護に影響があるとみなされて父親が親権を獲得しやすくなります。
- 子供を虐待している
- 子どもの世話をせず育児放棄している
- 家事を全くしない
- 子どものことより不貞行為相手との関係を優先している
- 薬物依存などの犯罪歴がある
- 重度の精神・身体の病気があり育児ができない
- 子どもが父親と暮らすことを希望している
- すでに子どもが父親と暮らしている
また前出の通り、15歳以上の子どもであれば子ども自身が父親と暮らしたいと望めば、子どもの要望が尊重されて父親が親権を獲得できます。
相手の不倫は親権に影響しない
「母親が不倫をしていたのだから、子どもの親権は父親が持つのが相応しい」と考える人がいるかもしれません。しかし不倫をしていたからといって、それだけで親権者の判断に不利になるとは限りません。前出の通り、親権者を決めるときには子どもの利益にかなうかどうかが重要視されます。
具体的にはこれまでの監護実績や子ども自身の希望、親権者としてふさわしいかによって判断されるという訳です。不倫のために子どもの世話をしていないなどの事情がない限り、不貞行為自体は親権獲得に与える影響は大きくありません。
親権者を決める手続きの流れ
では実際に親権者を決める場合、どのような手続きの流れで進められるのでしょうか。
双方で協議をする
離婚に合意した後は、夫婦の協議によって子どもの親権者を決めていきます。片方が親権を求めない場合はすぐに話がまとまるのですが、双方が親権を希望する場合は対立が免れません。とくに親権に関する話し合いでは、感情的になりがちです。冷静に話し合いを継続するためには、次のような点に注意するといいでしょう。
- 事前に弁護士に依頼し、話し合いの場に代理人として出席してもらう
- 共通の知人など中立な立場の人に立ち会ってもらう
- 自分の希望や決めたい内容について書き出しておいて、内容に沿った話をする
- 話し合うときには合意を得てボイスレコーダーなどに録音する
- 二人きりのときには人目のある場所で話し合う
話し合いの場に来ない、DVや虐待があるときにはこの限りではありません。話し合いが難しいときには、次の方法を検討しましょう。
子持ち男性が離婚を決めた後にすべきことや親権をとるための方法は、こちらの記事を参考にしましょう。
「子持ち男が離婚を決めるとき|離婚を決めた後にすべきこと&親権を取るための方法とは?」
話し合いが難しいときには調停を申し立てる
どちらも譲らないときや話し合いにならないときには、家庭裁判所に調停を申し立ててください。離婚についての話し合いを行う場合は「夫婦関係調整調停」の中で親権の話し合いも行います。
調停では、調停委員や裁判官が双方の主張をまとめたうえで状況を把握し、より子供のために適切な親権者を選び双方が納得できるような解決方法を提案します。場合によっては家庭裁判所の調査官による調査も実施します。調停で親権を決めるときの判断基準は、上で示した「親権で重要視されるポイント」の通りです。
離婚調停に相手が来ないときはどうなるかについては、こちらの記事を参考にしてください。
「離婚調停に相手が来ない場合はどうなる?ケース別の対処法と調停が不成立になった後で離婚する方法とは
最終的には審判・裁判で判断を出す
調停での話し合いが不調に終わった場合や相手が調停に出席してこないときには、家庭裁判所に離婚裁判を提起して、離婚の判決と共に裁判所に親権者を指定してもらいます。なお離婚について合意できている場合は、親権者の指定に関する審判を経て調停離婚が成立します。
離婚裁判を提起したときには、法廷の場で夫婦それぞれの主張を聞き、証拠をもとにして親権者を判断します。裁判は判決や和解によって必ず結論がでる最終的な解決手段です。たとえ裁判所の判断に納得できない場合でも、判決に従う必要があります。
男性が親権をとるためのポイント
男性が子どもの親権を獲得するのはそう簡単なことではありません。次の紹介するポイントを参考にしながら、親権獲得のための行動を起こしていきましょう。
長期間の監護実績を作る
男性が親権を獲得するためには、長期間の監護実績が必須です。親権の判断で重要視されるのが、きめ細やかな監護養育ができるかどうかだからです。生物学的な母親である必要がないものの、愛情を持ったスキンシップをとりながら子どもの年齢に応じた日常的な育児を行っていることが大切です。
監護実績は長ければ長いほど有利になります。短くても半年程度は、次のような記録をとりながら育児実績を作っていきましょう。
- 幼稚園・保育園や学校の連絡ノートをマメに書く
- 通園通学の送り迎えの様子を日記に書く
- 子どもの食事作りや着替えなど、日常の育児の様子を細かくメモにする
- 子どもと出かけたり行事をしたときには必ず写真を撮る
- 子どもの通院や予防接種に付き添った記録を残す
とくに園や学校が関わる連絡帳のやり取りは、偽造が難しいという理由から証拠として有力です。最近ではSNSやブログで育児日記をアップしている人も多いです。とくにSNSはアナログの日記と異なり日時の捏造が難しいので、これから監護実績を作ろうと考えている人におすすめです。
別居時は子どもを連れて
離婚前に別居するときには、必ず子どもを連れて家を出るようにしましょう。というのも上で説明した通り、親権の判断には「継続性の原則」が重視されるため。調停や裁判で親権者を決める場合、別居後の現状維持が優先されます。
この原則をクリアするためには、別居時は子どもを連れて家を出て、その後子どもと安定した生活ができているという実績が必要に。このような実績を作っておけば、無理に現状を変更してまで母親に親権を渡すという判断を回避できるはずです。
合意のない連れ去りはNG
いくら別居時に子どもを連れて行った方がいいといっても、母親の同意なしで子どもを連れ去るのはやめましょう。このような行為は「未成年者略取誘拐罪」という刑事罰の問われる可能性があるだけでなく、親権の判断にも不利になります。具体的には次のようなケースが当てはまります。
- 配偶者がいないときにこっそり子どもを連れていく
- 幼稚園・保育園・学校に子どもを迎えに行って連れ帰る
- 通学路で待ち伏せをして連れ帰る
- 子どもが嫌がっているのに無理やり連れて行く
今までろくに子どもの世話をしていなかったのにもかかわらず違法な連れ去りをした場合、親権争いに不利になるだけでなく、離婚後の連れ去りのリスクを考慮されて面会交流を制限される可能性があります。
連れ去り別居の違法性と親権への影響は、こちらの記事を参考にしましょう。
「連れ去り別居は違法?合法?親権獲得への影響と子どもを連れ去られたときの対処法とは」
相手に子どもを連れ去られたときには
それでは相手に子どもを連れ去られたときには、どうしたらいいのでしょうか。このとき相手と同じように強引に子どもを取り返すのは控えた方がいいでしょう。逆にこちらが親権獲得に不利になってしまうからです。
連れ去られた子どもを取り返したいときには、家庭裁判所に「監護者指定・子の引き渡し審判」を申し立ててください。審判で判断が出るまでに時間がかかり、その間子どもが連れ去られたままになるので、同時に「審判前の保全処分」も申し立てるのがベストです。
母親が親権者に向いていない証拠を確保する
母親が親権者に向かないと判断されると、逆に父親が有利になります。そのための証拠は確実に確保しておきましょう。具体的には次のような証拠が該当します。
- 子どもにケガをさせたときの写真や診断書
- 子どもを大声で怒鳴っているときの音声録音
- 部屋が散らかっているなど家事を怠っている証拠の写真や動画
- 子どもを家に残したまま不倫していた証拠
- ネグレクトを感じさせる周囲の証言
しかし母親が親権者として失格だというアピールばかりしていると、調停委員の心証を悪化させる恐れがあるので、アピールはほどほどにしましょう。
親権争いで母親が負ける理由については、こちらの記事を参考にしましょう。
「親権争いで母親が負ける理由とは?親権争いを勝ち取る6つの対策も解説」
転職や引っ越しを視野に入れる
仕事の拘束時間が長くて育児をする時間が取れないときには、思い切って転職を視野に入れてください。離婚して父親だけになった場合、子どもの世話に十分な時間が取れるかが重要だからです。職場に事情を話して、部署異動や勤務時間の調整ができないときには、転職を考える必要があります。
また周囲のサポートが受けられるよう、実家近くに引っ越すという方法も有効です。日常的に自分の両親やきょうだいに子どもを見てもらえる環境であるかどうかが親権獲得の判断材料に。こちらが引っ越すのが難しければ、親族に引っ越してきてもらうという手段もあります。
周囲のサポート体制を整える
親権を獲得するのが母親でも父親でも、周囲のサポート体制の有無は重要です。仕事で家にいないときやいざというときに代わりに子どもの面倒を見てもらえるよう、離婚前からお願いしておきましょう。もし近くに頼れる親族がいない場合には、シッターやヘルパーなどのサービスが受けられないか調べておいてください。
子どもが15歳になるまで離婚しない
子どもの意思が尊重される15歳まで離婚しないのも、男性が親権をとるための方法です。15歳以下の子どもの場合、よほど母親にふさわしくない事情がない限りは親権が母親に行きます。しかし15歳以上の子どもの場合は子ども自身の意思が尊重されます。
普段から子どもとの関係が良く、子どもが父親と一緒に暮らしたいと思っている場合は、離婚の時期を後ろ倒しにするのも一つの手といえます。
子どものために離婚しない方がいいのでは?とお悩みの方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「『子どものために離婚しない』は本当?離婚の判断基準や子どもの本音を知って後悔しない生き方を
面会交流は継続的に
やむを得ない事情があり子どもを連れて別居できないときには、面会交流を継続して行うようにしましょう。子どもとの面会すらろくに実施できていない状況だと、子どもへの愛情や監護に意欲の有無に疑問符がついてしまいます。面会交流への積極性は、育児に携わりたいという意思表示になるということを覚えておきましょう。
面会交流やその他の交流に関しては、次のような点に気を付けてください。
- 面会予定は極力キャンセルしない
- 面会頻度を増やしたいという希望を書面で送付する
- 子どもの養育費や学費を積極的に負担する
- 子どもに自分の気持ちを手紙やメールなどで伝える
面会交流の第三者機関を利用したいとお考えの方は、こちらの記事を参考にしてください。
「面会交流の第三者機関とは|組織の種類と支援内容・費用相場を知り利用するかどうか検討しよう」
調停委員を味方につける
親権問題がこじれて調停になった場合、調停委員を味方につけるようにするといいでしょう。調停委員は第三者として客観的な判断を出すのが役割ですが、いくら裁判所から選任されているとはいえ、調停委員も人間です。より印象が良い方に親権を渡したいと考えるのが当然です。
そのため、最低限の社会人としてのマナーを守るのは当然として、父親として子どもを養育するのにふさわしいふるまいを心がけてください。そのためには自分がいかに親権者としてふさわしいかを、客観的事実を提示して誠実に伝えてください。
「子どもの手続き代理人制度」の活用
男性が親権を得るために「子どもの手続き代理人制度」を利用するという方法があります。子どもの手続き代理人制度とは、調停や審判など家庭裁判所の手続きのときに利用できる制度。裁判所での子ども自身の意思を表明するために、弁護士が代理人となってサポートします。
15歳以下の子どもが父親と一緒に暮らしたいと考えているときには、子どもの手続き代理人制度を利用してみてはいかがでしょうか。
親権にこだわらず一緒に暮らす方法もある
親権をとらなくても子どもと一緒に暮らせればいいという方は、監護権者の変更を申し入れるという方法があります。通常は親権者が監護権を有していることが一般的ですが、親権と監護権とを分けることもできます。
親権者の変更は必ず裁判所の調停や審判を経る必要がありますが、監護権の変更は父母の話し合いによって変更が可能です。話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて決めることになります。調停が不成立に終われば、そのまま審判に移行するという流れです。
離婚問題に詳しい弁護士に相談
男性が子どもの親権を獲得したいときには、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。今の日本では父親が親権を獲得できる確率は高くなく、法的な知識や裁判所での手続きの進め方、経験に基づいた交渉力が欠かせません。
とくに親権については、子どもをどちらが育てるかというデリケートな問題です。離婚時の親権争いの経験が豊富な弁護士に依頼するのが、希望を叶える秘訣です。
まとめ
男性が子どもの親権を獲得したいと思ったら、親権問題で重要視されるポイントや父親が有利になるケースなどをよく知っておくべきでしょう。また親権獲得までの流れや法的手続きについての知識も必要です。今の日本では父親が親権を取れる確率はそう多くないものの、共同親権導入で変化が期待できます。
男性が親権をとるためには、半年以上の監護実績が必須です。客観的な証拠をもとに、親権者としてふさわしいことをアピールしましょう。また別居時は必ず子どもを連れて出るのもポイント。どうしても一緒に連れていけないときには、継続的な面会交流をするようにしましょう。
ことさらに母親が親権者としてふさわしくないことを主張するのはNGですが、調停委員に良い印象を持ってもらうようにするのも大切。そのためにもなるべく早い段階で、弁護士に相談するようにしましょう。親権問題の実績が豊富な専門家に依頼できれば、男性でも子どもの親権を獲得できる可能性は高まります。