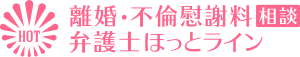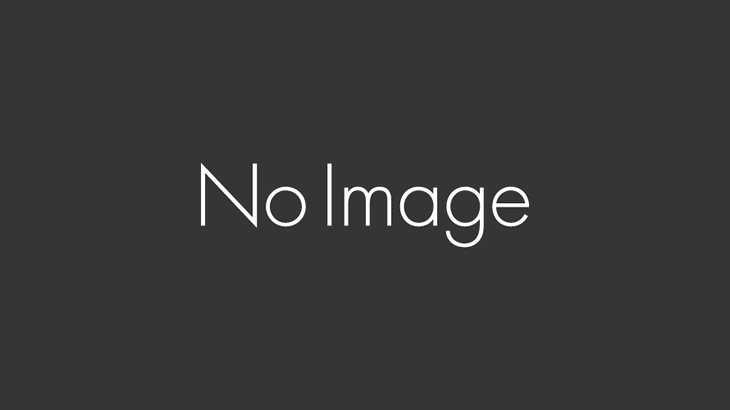- 「正直、離婚後に旧姓に戻りたくない…どうすればいい?」
- 「離婚した後も苗字をそのままにする人って珍しいのかな?」
夫婦が離婚をすると、婚姻によって姓が変わった側は原則として旧姓に戻ります。しかし姓が変わることにより、身分証や銀行口座などの名義変更が必要になる、離婚が周囲に知られるなどのデメリットも。そのため離婚をしても旧姓に戻りたくない、と思う方は少なくありません。
離婚の日から3カ月以内に届出をすることによって離婚後も婚姻時の姓を名乗ることが可能です。このページでは離婚後に苗字を旧姓に戻さないメリットやデメリット、実際の手続きの手順を詳しく紹介します。離婚後の苗字について迷っている方はぜひ参考にしてください。
離婚後に苗字を変えない割合は半数近く
日本では現在夫婦別姓が認められていないため、婚姻の際には夫婦どちらか一方が配偶者の苗字を名乗ることになります。そして婚姻時に苗字を変えた方は、離婚時に何もしなければもとの苗字に戻ります。
そのため、離婚と同時に苗字も変えることは当たり前のことだ、と考えている方もいるでしょう。しかし離婚から3ヵ月以内に婚氏続称の手続きを取ることにより、離婚後も今までの苗字を使い続けることが可能です。
2024年の戸籍統計によると、2023年に離婚を届け出た夫婦18万8239件のうち半数近く(46%)にあたる8万6041件が離婚後も苗字を変えていないことが分かっています。
(参考:戸籍統計|2023年度)
手続きをしなければ苗字は旧姓に戻る
離婚届を提出した場合、婚姻時に苗字を変更した方はもとの苗字に戻るという旨が民法767条で規定されています。
第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
(引用:e-GOV法令検索|民法)
また民法767条では、届出をすることで離婚前の姓を称することができる旨も明示されています。離婚した日から3ヵ月以内に婚氏続称届(こんしぞくしょうとどけ)を市区町村の窓口に提出することで手続きが可能です。
離婚後に苗字変更をしないメリット
離婚後も今までの苗字を名乗るためには、離婚から3ヵ月以内に婚氏続称届を提出する必要があります。すなわち、半数近くの方が意図的に苗字を変更しないことを選択しているということに他なりません。
離婚後に苗字を変更しないメリットとは何なのでしょうか?具体的には以下の3点が挙げられます。
- 銀行口座などの名義変更をしなくてよい
- 周囲に離婚したことを知られにくい
- 子どもへの影響を軽くできる
銀行口座などの名義変更をしなくてよい
苗字を変更した場合、銀行口座やクレジットカード、身分証明書、携帯電話、資格の証書などの名義変更手続きをしなくてはいけません。一度でも苗字が変わったことがある方は変更手続きの煩雑さを覚えているのではないでしょうか。
また仕事で名乗る名前も変える場合、仕事相手への連絡、名刺の変更などの作業も必要です。苗字が変わらなければ、このような手続をわざわざしなくても済みます。このことだけを理由に苗字を変更しない方も少なくありません。
周囲に離婚したことを知られにくい
苗字が変更することにより、離婚したことを周囲に知られてしまいます。しかし婚氏続称の手続きを行い、今までの苗字を名乗ることで今まで通りに過ごすことができます。
苗字が変わったことをきっかけに、自分の状況をすぐに理解してもらえるというメリットはあります。しかし離婚について詮索されるのが嫌な方、気を遣われたくない方にとっては大きなデメリットでしょう。
子どもへの影響を軽くできる
夫婦間に子どもがいる場合、離婚によって子どもにも影響を及ぼすことになります。その一つが姓の問題です。離婚後の親権を獲得したほうが旧姓に戻ったとしても子どもは自動的に同じ姓にはなりません。子どもは変更の手続きをしない限り、今までの姓を名乗ることになります。
子どもの姓が変わらないにも関わらず自分が旧姓に戻った場合、親子でありながら違う姓を名乗ることになります。学校関連の書類では、親子の名前を一緒に記入する機会は多いものです。その際、子どもと親の苗字が異なると目立ってしまう恐れがあります。子どもの友達がそのことに気づき、「お母さん(お父さん)と苗字が違うのはどうして?」と悪気なく質問する可能性もあるでしょう。
手続きをすることで子どもの姓は変更ができるため、離婚後に親子で旧姓を名乗ることは可能です。しかしその場合、子どもの苗字が突然変わることになり、周囲が違和感を抱くようになります。
進学や転校など、周囲の環境が大きく変わるタイミングであれば影響は少なくなりますが、いずれにせよ子どもへの負担は完全に回避できません。しかし親子で共に今までの苗字を名乗り続けることで、子どもへの精神的な負担を軽減することができます。
離婚後旧姓に戻らないとデメリットはある?
ここまでは離婚後に苗字変更をしないメリットについて解説してきました。しかし旧姓に戻らないことは良いことばかりではなく、デメリットもあります。
具体的には以下のような事柄が挙げられます。項目に分け、詳しく解説をしていきます。
- 気持ちの整理がつきにくい
- 後から旧姓に戻す際の手続きに手間がかかる
- 元配偶者側から嫌がられる恐れがある
- 自分の親族と違う苗字になる
気持ちの整理がつきにくい
夫婦関係に悩んできた方にとって、離婚は新しいスタートと言えます。配偶者と別の苗字になることで、過去と決別し新たな一歩を踏み出そうという決心がしやすくなります。
元配偶者へ抱く感情は、離婚の状況によってさまざまです。中には「もう顔も見たくない」と思うほど負の感情を抱いている方もいるでしょう。そのような方でも、子どもや生活のことを考えて元配偶者の姓を使い続けるという事例は多いです。
しかし配偶者の苗字を使い続けることにより、相手のことを思い出すきっかけになり気持ちが整理できない恐れがあります。過去をひきずっている気分になり、なかなか晴れやかな気持になれない方も実際にいます。
後から旧姓に戻す際の手続きに手間がかかる
離婚に際して婚氏続称の手続きを行うと、後から「やっぱり旧姓に戻りたい」と思っても簡単には戻れなくなる点に注意しましょう。婚氏続称の手続後に旧姓に戻りたい場合は、家庭裁判所に氏の変更許可申立書を提出し、許可を得なくてはいけません。
裁判所から姓の変更が認められるためには、社会生活に支障をきたす「やむを得ない理由」が必要です。そのため簡単には変更が認められません。
再婚後に離婚した場合も旧姓に戻せない
婚氏続称の手続きを行った後に再婚をし、また離婚をした場合でも、最初の苗字に戻ることはできませんので注意してください。原則として、一度婚氏続称を届け出た後に旧姓に戻ることは大変難しいとされています。
近年では、1回目の離婚では婚姻時の苗字を名乗っていた人が2回目の離婚で旧姓(最初の苗字)に戻りたいというケースの場合、裁判所から旧姓に戻ることを認められやすい傾向があります。
しかし家庭裁判所に氏の変更許可を申し立てる場合、申立書の作成、今までの結婚や離婚を証明するための戸籍謄本を準備するなど手続きが大変煩雑です。このような自体を避けるためには、一度目の離婚の際に一度旧姓に戻すことが最良でしょう。
元配偶者側から嫌がられる恐れがある
離婚後に元配偶者の姓を使い続けることで、元配偶者から不快感を示される可能性があります。本人は問題ないと思っていても、親族が「なぜうちの姓を名乗っているのか」と反対するケースも。
離婚後に旧姓に戻すかどうかは本人の自由です。婚氏続称届を提出する際には、誰の許可も必要ありません。しかし元配偶者側から嫌味を言われ、不快な思いをする可能性はあり得ます。
自分の親族と違う苗字になる
婚氏続称の手続きを行った場合、自分の親や兄弟、親戚とは違う姓のままです。そのことにより、親族との繋がりを感じにくくなる可能性があります。
また親族と苗字が異なる場合、亡くなったときに同じお墓に入れない可能性がある点にも留意してください。宗派や墓地によって決まりが異なるため一概には言えませんが、苗字が異なる人は同じ墓に埋葬できないという事例もあります。
離婚後の苗字をそのままにするためには?
先述の通り、離婚後に旧姓に戻したい場合は特別な手続は必要ありません。離婚届を提出することで苗字は旧姓になります。しかし離婚後に苗字をそのままにしたい場合は手続きが必要です。ここでは具体的な手続きの手順を解説します。
離婚後3ヵ月以内なら「婚氏続称の届」を提出
離婚から3ヵ月経っていない場合、市区町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」もしくは「婚氏続称届」を提出することで手続きが可能です。婚氏続称届は役所の窓口で入手できるほか、市区町村のホームページからダウンロードすることも可能です。
離婚後しばらくしてから婚氏続称届を提出する場合、届出をするまでは旧姓に戻ってしまいます。そのため離婚届と同時に婚氏続称届を提出するケースが多いです。
手続きに必要な書類
手続きの際に必要なものは以下の通りです。
- 離婚の際に称していた氏を称する届
- 夫婦もしくは自分の戸籍謄本(本籍地以外の市区町村に提出する場合)
同日に離婚届を提出する方は、離婚届と本人確認書類も持っていきましょう。なお婚氏続称届のみの提出の場合、本人が記入した届出書を代理人が提出することも可能です。
離婚後3ヵ月経過後は「氏の変更許可申立」が必要
一度旧姓に戻り、離婚から3ヵ月経過した後に婚姻中の苗字に戻したくなった場合、市区町村では手続きはできません。家庭裁判所に「氏の変更許可申立」を行い、許可を得る必要があります。
氏の変更許可申立を行っても必ず変更が認められるわけではなく「やむを得ない事由」が必要です。旧姓になってから日数が経過するほど変更が認められにくくなるため、手続きは早めに行いましょう。
氏の変更許可申立の手順
まず家庭裁判所、もしくは裁判所のホームページより氏の変更許可の申立書を取得し、申立書を作成します。申立人に自分の氏名や住所を記載し、変更前と変更を希望する姓を記載後、変更を必要とする具体的な事情を記載しましょう。
氏の変更許可申立を行うと同じ戸籍の親族の苗字も変わります。そのため満15歳以上の親族がいる場合、その親族の同意書も取得する必要があります。申立から審判が確定するまでは1~3ヵ月程度かかります。状況によっては裁判所から出廷を求められることもあるため、連絡があった際は必ず応じるようにしましょう。
許可の審判が確定したら裁判所に確定証明書の交付の申請を行い、確定証明書と審判書謄本を市区町村役場に提出して下さい。
手続きに必要な書類
氏の変更許可申立に必要な書類は以下の通りです。審理の際、追加で書類提出を求められることもあります。
- 申立書
- 収入印紙800円分(申立書に貼付)
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 結婚前から現在までの戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
- 同一戸籍内の15歳以上の者の同意書
氏の変更許可申立は弁護士に依頼できる
繰り返しになりますが、氏の変更許可申立によって姓の変更を認められるためには「やむを得ない事由」が不可欠です。どのような理由であれば姓の変更が認められるかは、申立者の個々の状況や管轄の家庭裁判所によって異なるため、一概には言えません。
また氏の変更許可申立は必要な書類が多い点、手続が煩雑な点にも注意が必要です。特に2回以上離婚をしている場合、その都度での戸籍謄本(除籍)がすべて必要となるため、取得だけでも手間がかかります。
氏の変更許可申立は自分でも行えます。しかし忙しくて時間がとれない方、確実に姓の変更を認めてもらいたい方は弁護士に依頼をすることをお勧めします。弁護士に氏の変更許可申立を依頼することにより、申立書の作成や必要書類の取得を全て委任することが可能です。
弁護士はどのような事由であれば改姓が認められるかも熟知していますので、安心して手続きを任せられます。
お住まいの地域で、離婚問題に強い弁護士を見つける>>
離婚後の苗字についての注意点
今回の記事では、離婚に伴う姓の変更に焦点を当てて解説を行いました。最後に、離婚を考えている方に向けて苗字に関する注意点をまとめました。必ず確認し、後悔しないようにしましょう。
配偶者が亡くなった場合は旧姓に戻らない
離婚をすると、婚姻によって姓が変わった側は旧姓に戻ります。しかし配偶者と死別した場合には旧姓に戻りません。そのため配偶者と死別した後に旧姓に戻りたい場合は、市区町村に「復氏届」を提出する必要があります。
復氏届を提出すると配偶者の戸籍から抜け、旧姓に戻ります。あくまでも苗字を変更するだけの手続きですので、配偶者と離婚したことにはならず、遺産相続や遺族年金の受け取りには一切影響を及ぼしません。
また配偶者と死別した後も、配偶者の親族(配偶者の父母、兄弟姉妹など)との関係は変わらず、あなたに扶養義務が残ります。死亡した配偶者の親族との姻族関係を解消したい場合は、復氏届とは別に「婚姻関係終了届」を提出しましょう。
「婚姻関係終了届」の提出方法、メリットやデメリットは以下の記事で詳しくまとめています。
死後離婚をするには?配偶者と死別後の手続きや注意点をすべて解説
両親が離婚しても子どもの姓は変わらない
離婚によって旧姓に戻るのは、あくまでも婚姻によって姓を変更した者のみです。子の姓は離婚による影響を受けず、親権者と苗字が同じになるということもありません。
そのためあなたが旧姓に戻り、子どもも同じ姓を名乗らせたい場合には手続きが必要です。家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し申立を行い、審判を経てから市区町村へ入籍届を提出します。
離婚から3カ月経過した場合に家庭裁判所に申立をする「氏の変更許可申立書」は、やむを得ない事由がないと認められません。しかし子の姓を変える手続きは通常であれば滞りなく進み、早ければその日のうちに審判が完了することもあります。
なぜなら、子が父もしくは母と苗字が異なる場合、家庭裁判所の許可を得て姓を変更できる旨は民法で規定されているためです。
第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
(引用:e-GOV法令検索|民法)
子の姓を変更するための手順
子どもの姓を自分と同じにするための手続きは、以下ような流れです。
- 家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出
- 家庭裁判所から審判書を受け取る
- 市区町村役場へ入籍届を審判書と一緒に提出する
「子の氏の変更許可申立書」は子が15歳以上であれば本人、15歳未満であれば法定代理人(親権者)が申立を行います。「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所もしくはホームページより取得し、本人もしくは法定代理人が記載の上、子の住所を管轄する家庭裁判所に提出してください。
必要な書類は以下の通りです。
- 子の氏の変更許可申立書
- 収入印紙800円分(申立書に貼付)
- 子の戸籍謄本
- 親の戸籍謄本
子の戸籍を自分の戸籍に入れたい場合
離婚をすると、片方が配偶者の戸籍から抜け、筆頭者として新たに戸籍を作ることになります。しかし子どもは離婚をしても父親の戸籍から抜けません。親権と戸籍は全く関係がないため、母親が親権を獲得したとしても、子どもは父親の戸籍に入ったままです。
離婚後も、元夫は子の父親であることに変わりはなく、子どもが父親の戸籍に入ったままでも何も支障はありません。しかし父親が再婚した場合、再婚相手が子どもと同じ戸籍に入ることになり、母親としては受け入れられるものではありません。
子を自分の戸籍に入れる手続きの流れは、子の姓を変更する際の手続きと一緒です。一度家庭裁判所に申立を行い、許可を得てから入籍届を提出します。
まとめ
離婚すると、婚姻によって姓が変わった側は原則として旧姓に戻ります。しかし、姓が変わることで身分証や銀行口座の名義変更が必要になったり、離婚が周囲に知られることを避けたいと考える人も多くいます。
離婚後も婚姻時の姓を名乗り続けたい場合は離婚の日から3カ月以内に「婚氏続称届」を提出すれば、旧姓に戻さずに済みます。しかし離婚後3ヵ月経過後に旧姓へ戻す場合は家庭裁判所の許可を得なければなりません。
改姓の申立ては自分で行うことも可能ですが、弁護士に依頼することで手続きをスムーズに進められます。弁護士に依頼すれば、申立書の作成や必要書類の取得も任せられるため安心です。
旧姓に戻るか姓をそのままにするか、どちらを選ぶ場合もメリット・デメリットを理解した上で慎重に判断することが大切です。