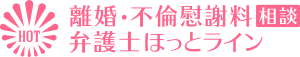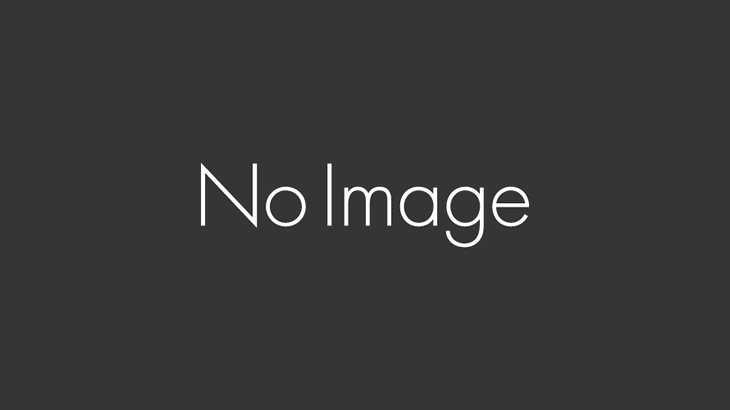- 「すぐにでも離婚したい…離婚届を提出してその日に受理してもらえる?」
- 「忙しくてあまり休みが取れない、できれば一日で手続きを済ませたい」
離婚することが決まったら、市区町村役場に離婚届を提出することになります。普段仕事や育児などで忙しい方は、できるだけ短い期間で手続きを済ませたいと考えるでしょう。
離婚届を窓口に提出をすると、不備がなければその日のうちに受理してもらえます。しかし状況によっては提出を受け付けてもらえないケースも。
離婚届を即日で受理してもらうためには、どうすればよいのでしょうか?この記事では離婚届を即日受理してもらうために注意したいことやあらかじめ準備しておくべきことを紹介します。
また離婚をした際には、住民票の異動などが必要になります。離婚届の提出と同じ日にできる手続きについても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
離婚届を提出できる場所・受理までの流れ
まずは離婚届を提出できる場所や時間、受理までの流れを確認しましょう。離婚届を提出できるのは居住地もしくは本籍地の市区町村役場の窓口、もしくは夜間窓口です。離婚届受理までの流れは、それぞれのパターンでそれぞれ異なります。
市区町村役場の窓口の受付時間
市区町村役場の窓口の受付時間は、各自治体によって若干の違いがあります。一般的に平日の8時30分~17時前後であることが大半です。自治体によっては午後7時程度まで受付時間を延長する曜日を設けていることも。
窓口に離婚届を提出すると、書類の不備がないか、離婚届不受理申出が出されていないかを確認します。もし記載内容に不備があれば修正を求められますが問題がなければその場で「受理」となります。
離婚届を提出し受理された後、すぐに戸籍に反映されるわけではありません。自治体によって処理状況が異なりますが、通常は数日~1週間程度で戸籍に「離婚」の事実が記録されます。
市区町村役場の夜間窓口
平日の夜間や休日など役場が閉庁している時間帯は、夜間受付窓口で離婚届の提出が可能です。役所の支所や支部、出張中などでは、時間外の受付窓口を設置していないケースもあります。かならず事前にホームページ等で確認を行うようにしましょう。
夜間窓口では、あくまでも届出の受領のみを行っています。翌開庁日に内容の確認を行うため、不備があった場合は後日連絡があったり、受理してもらえなかったりする可能性も。翌開庁日に不備がない場合、提出した日が離婚した日として遡って手続きが行われます。
離婚届は一人でも提出できる!
離婚届は、2名の当事者による手続きです。そのため、夫婦両方が揃っていないと提出ができないのでは?と考える方もいるはずです。実際には離婚届は1人で提出しても問題はありません。
離婚届を提出する時には既に夫婦が別居していたり、一緒に外出することを嫌がる程仲が悪化していたりするケースは少なくありません。そのため、離婚届は夫婦いずれかが役所に提出をすれば受理されるようになっています。
しかし離婚届に不備があった場合は書いた本人による訂正が必要になります。相手に記入を依頼した場合は不備がないかをしっかり確認しましょう。
また夫婦両方が役所に足を運べない場合は第三者に離婚届を提出してもらうことも可能です。親族に限らず、友人や知人などが提出しても問題ありません。本人から代理人への委任状は不要ですが、提出する代理人の身分証明書が必要となるため注意してください。
離婚届の提出の際に必要な物は?
離婚の届出をする場合、必要なものは離婚届だけではありません。提出日当日に慌てないよう、あらかじめ必要なものを確認しておきましょう。
離婚届1通
離婚の種類には、話し合いによる協議離婚、調停や裁判を経て離婚するケースがありますが、いずれの場合でも離婚届を準備する必要があります。調停離婚や裁判離婚の場合、相手方や証人の署名は必要がないため、自分で離婚届を記入し提出することが可能です。
しかし夫婦間で話し合いをして離婚を決めた場合(協議離婚)、相手方と証人2人の直筆の署名が必要です。相手や証人に依頼して署名をもらうまでの日数を考慮し、早めに準備を行うことをお勧めします。
離婚届の証人については、以下の記事で詳しくまとめています。証人が見つからない方、お願いできる人がいない方に向けてのアドバイスも記載していますので、ぜひ参考にしてください。
離婚届の証人は必要?証人になるリスク・条件と証人が見つからないときの対処法とは
用紙の取得方法
離婚届は全国共通で書式が定められており、自分で書式を作成をすることはできません。そのため作成前に各市区町村の窓口で取得する必要があります。自治体によっては印刷して利用できる書式をホームページで用意しているところもあります。
離婚届を印刷する際は戸籍法施行規則第59条で定められている通り、必ずA3サイズでなければいけません。A4サイズ、A4を繋げてA3サイズにしたものは認められませんので注意してください。印刷の色は黒で差し支えありませんが、感熱紙ではない白い紙を使用しましょう。
離婚届の記入方法
離婚届は必ず手書きで、黒いペンを使用して記入しましょう。鉛筆や消せるペンは使用できません。住所などは正式な表記を求められるため、住民票などを見ながら書くことをお勧めします。
間違えた場合は修正液や修正テープを使用してはいけません。間違えた箇所を二重線で消し、小さく自筆で署名を書きましょう。用紙の欄外(左)に署名をする欄があるため、修正をした印としてそこにもフルネームで署名をします。
本人確認資料
離婚届を窓口に提出する際には本人確認書類の提示を求められます。運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、写真付きの本人確認書類を用意してください。保険証や年金手帳、年金番号通知書などの写真がない身分証明書の場合、2点以上を提示することで本人確認が可能です。
なお調停や判決など、裁判所での手続きを経て離婚が成立した場合は身分証明書は必要ありません。
離婚の手続きによって必要な書類
離婚調停や離婚裁判で離婚が成立した場合は、そのことを証明する書類を提出します。
- 調停調書の謄本
- 離婚調停が成立したことを証明する文書の写し
- 判決書の謄本
- 離婚裁判の判決の写し
- 判決確定証明書
- 離婚裁判の裁判が確定したことを証明する文書
調停調書の謄本
裁判所に調停の手続きを申し立て、お互いに話し合いのもと成立する離婚を調停離婚と呼びます。調停離婚の場合、調停が成立した時点で離婚が成立しますが、戸籍には反映されないため、調停成立から10日以内に離婚届を提出しなくてはいけません。
調停が成立したら調停調書の写し(調停調書省略謄本(戸籍届出用))を裁判所で取得し、離婚届と一緒に提出しましょう。
判決書の謄本・判決確定証明書
離婚調停が不成立となった場合は裁判所に離婚を申し立て、法的に離婚を認めてもらうことになります。判決で離婚が認められた場合、裁判所からその内容が証明できる書類(判決書の謄本・判決確定証明書)を取得し、離婚届と一緒に提出してください。
法改正により提出不要になったもの
何らかの届出を行う際には、印鑑が不可欠だと考える方が多いでしょう。従来は離婚届には署名だけでなく押印も必要でした。しかし令和3年9月の戸籍法改正より離婚届への押印は任意となったため印鑑は必要ありません。
また本籍地以外の市区町村へ離婚届を提出する際には、戸籍謄本を準備し提出するよう案内をしている方もいます。しかし法改正により令和6年2月1日以降は本籍地以外で離婚届を提出する時でも戸籍謄本は不要になりましたので、準備する必要はありません。
離婚届が即日で受理されないケースは?
市区町村の窓口に離婚届を提出した場合、原則としてその日のうちに離婚届が受理されます。しかし以下のような事情があった場合、離婚届が受理されない可能性があります。
- 離婚届に不備がある
- 親権者が決まっていない
- 離婚届の不受理申出がされている
離婚届に不備がある
離婚届に不備がある場合は受理されず、訂正するよう求められます。些細なミスであればその場で訂正できる可能性があります。しかし以下のようにその場で補正できない場合、書き直しが必要な場合は一旦持ち帰って対応後、再提出をしなくてはいけません。
- 黒ペンで書かれていない
- 名前を旧姓で記載している
- 定められた書式ではない
- 修正液等で訂正がされている
- 相手・証人の署名が抜けている(協議離婚の場合)
親権者が決まっていない
離婚届には夫もしくは妻が親権を行う子を記載する欄があります。夫婦間に子がいるにも関わらず親権者が決まっていない場合、離婚届は受理されません。必ず離婚届を提出する前に親権者を決定しましょう。
離婚届の不受理申出がされている
離婚届の不受理申出は、本人が知らない間に不正に離婚届が提出されることを防ぐ制度です。相手方が離婚届の不受理申出をしていた場合、あなたが離婚届を提出しても受理してもらうことはできません。
不受理申出の有効期限はなく、以下のいずれかの場合に効力が失効します。
- 申出人が離婚届不受理申出の取り下げをした
- 申出人が離婚届を提出した
- 申出人が死亡した
- 裁判によって離婚が成立した
離婚届不受理申出を取り下げるためには、申出人本人が市区町村役場の窓口に行き、取下げ書と本人確認書類を提出して手続きをしなくてはいけません。
離婚届の提出と同時にできる手続き
離婚をすると、それに伴いさまざまな手続きが必要になります。日中はなかなか役所に行けないという方は、効率よく手続きをすませられるよう準備をしましょう。離婚届の提出と同時に窓口で行える手続きは、以下の6つです。
- 住民票の異動
- 新しい戸籍の作成
- 世帯主変更・世帯分離
- 婚氏続称の提出
- マイナンバーカードの変更
- 印鑑登録
住民票の異動
離婚届を提出すると同時に住民票を異動することができます。住民票の異動は、変更があった日から14日以内に届出をするよう住民基本台帳法で義務づけられています。新しい住民票は免許証の変更にも必要になりますので、離婚届と同時に手続きをしましょう。
同じ市区町村内で引っ越す場合は、窓口で転居届を提出するだけで手続きが完了します。別の市区町村に引っ越す場合は、窓口で転出届を提出して転出証明書を所得したあと、新しく住む所の市区町村窓口に転入届と一緒に提出してください。手続きの際には本人確認書類、マイナンバーカードを用意しましょう。
世帯主変更・世帯分離
離婚を機に引っ越しをしないという方でも、世帯主が変わった時は世帯主変更、世帯を元配偶者と分ける時には世帯分離の手続きが必要です。
いずれも転出・転居の際と同様、住民異動届に記入をして提出することで手続きが可能です。具体的にどのようなケースの場合に手続きが必要になるのか、詳しく解説をしていきます。
世帯主変更
夫婦が離婚すると、一般的に夫婦は別々に住むことになります。世帯主でない方が現在の住所に残り、世帯主だった方が家を出て行った場合、世帯の世帯主がいない状態になってしまいます。
このように現在の世帯主がいなくなった場合は新しく世帯主を定める手続きをしなくてはいけません。
世帯分離
離婚した後でも子どもへの影響などを考慮し、元配偶者と同居を続ける人は珍しくありません。しかし離婚後も同居を続けていると同一生計であるとみなされ、行政のさまざまな支援制度が受けられない可能性があります。
世帯分離とは住民票上で別の世帯にする手続きのことを指します。世帯分離によって配偶者と別の世帯になることで、支援制度の算定などにおいて実態に則した判断をしてもらいやすくなります。
なお世帯分離の手続きをしても、必ずしも生計が同一でないと認められるわけではありません。自治体によっては事実婚や内縁の関係であると判断することもあるため注意してください。
新しい戸籍の作成
婚姻によって配偶者の戸籍に入っていた場合、離婚後は自動的に婚姻前の戸籍に戻ることになります。しかし自分を筆頭者として新しい戸籍を作ることも可能です。
新しい戸籍を作成する場合は、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄の「夫は/妻は」「新しい戸籍をつくる」にチェックをするだけで手続きができます。
なお新しい戸籍を作った場合、親の戸籍には簡単に戻れなくなるため注意しましょう。一度戸籍を分けたあとに親の戸籍に戻りたくなった場合、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」の手続きが必要になります。
婚氏続称の提出
離婚届と同時に「婚氏続称の提出」(離婚の際に称していた氏を称する届の提出)の提出もできます。婚氏続称とは、離婚後に旧姓に戻らず、現在の苗字を使い続けることを申請する手続きのことです。
婚姻によって姓が変わった人は、離婚後は自動的に婚姻前の苗字に戻ることになっています。しかし社会生活や子どもへの影響を考え、離婚をしても苗字を戻したくない、と考える方は決して少なくありません。そこで離婚の際に称していた氏を称する届を提出することにより、今までの苗字を名乗り続けることが可能になります。
この手続きは、離婚と同時に行うよう義務づけられているものではありません。離婚後3ヵ月以内であれば、いつでも提出が可能です。離婚した日から3ヵ月を経過した場合、家庭裁判所に申し立てをしないと姓が変更できなくなるため、早めに手続きをするようにしましょう。
婚氏続称の提出方法や注意点については、以下の記事で詳しくまとめています。苗字を変更しないこと・旧姓に戻ることそれぞれのメリットやデメリットもまとめていますので、離婚後に姓をどうするか迷っている方もぜひ参考にしてください。
離婚後に苗字変更したくない!姓をそのままにする人の割合や手続き方法、旧姓にしないデメリットを解説
マイナンバーカードの変更
離婚によって姓や住所が変更になった場合はマイナンバーカードの記載内容も変更しなくてはいけません。窓口で離婚届と一緒にマイナンバーカードを提出することにより、マイナンバーカードの記載内容の手続きも行えます。
変更手続きの際は、マイナンバーカードの交付時に設定した4桁の暗証番号が必要になります。
印鑑登録
離婚届の提出と同時に印鑑登録の変更手続きもできます。離婚によって印鑑登録している氏が変わる方、印鑑登録をしている市区町村から他の市区町村へ引っ越しをする方は印鑑登録の変更手続きが必要です。
手続きの際に必要なものは以下の通りです。
- 印鑑登録廃止申請書
- 印鑑登録申請書
- 本人確認書類
- 登録している印鑑
- 新しく登録する印鑑
市区町村によっては印鑑登録廃止申請書が存在せず、印鑑登録申請書のみで新しい印鑑の申請ができることもあります。市区町村から引っ越しをせず姓が変わらない方、姓が変わっても名前で印鑑登録をしている方は手続きは必要ありません。
離婚届の提出と同じ日にできる手続き
離婚届の提出とは窓口が異なるものの、同じ日に市区町村役場で行える手続きもあります。条件によっては同じ日に行えない場合もあるため、自分が該当するかをあらかじめ確認するようにしてください。それぞれ項目ごとに詳しく説明をしていきます。
- 児童扶養手当の申請
- 国民健康保険の手続き
- ひとり親世帯の医療費助成申請
- 国民年金の変更
- その他、ひとり親向けの助成制度
児童扶養手当の申請
離婚後に子どもの親権をあなたが持ち、一緒に生活をしていく場合、あなたの所得や子どもの年齢によっては児童扶養手当の給付が受けられる可能性があります。児童扶養手当は申請から審査があるため、実際の支給までには日数がかかります。早めに申請をしておきましょう。
申請手続きに必要なものは以下の通りです。
- 申請者・子どもの戸籍謄本
- 申請者の本人確認書類
- 申請者のマイナンバーカード
- 申請者の年金手帳
- 手当を受給する申請者名義の預金通帳
国民健康保険の手続き
離婚に伴い健康保険の手続きも必要になる場合があります。もともと国民健康保険に加入していて、離婚に伴って姓や住所が変更になった方は、離婚届の提出と同じ日に手続きができます。
配偶者の勤務先の健康保険に被扶養者として加入していた方は、配偶者の勤務先から資格喪失証明書を取得し、新しく国民健康保険に加入する際に提出をしなくてはいけないため、その日のうちに手続きはできません。
ひとり親世帯の医療費助成申請
各自治体ではひとり親世帯のための医療費助成制度を設けています。所得の条件があるため全員が助成を受けられるわけではありませんが、条件に該当する見込みがある場合は手続きを行いましょう。
申請手続きに必要なものは以下の通りです。
- 申請者・子どもの戸籍謄本
- 申請者・子どもの健康保険証
- 申請者の本人確認書類
- 最新年度の住民税課税証明書
国民年金の変更
国民年金の変更手続きも、離婚届の提出と同じ日に行えます。年金手帳もしくは基礎年金番号通知書を持参し、年金を管轄する窓口で申請を行いましょう。
しかしあなたが配偶者の扶養に入っていた場合、すなわち第3号被保険者だった場合は健康保険と同様、配偶者の勤務先が発行する資格喪失証明書が必要になります。証明書が交付された後で手続きを行ってください。
その他、ひとり親向けの助成制度
自治体によっては、児童扶養手当や医療費助成だけでなく、住宅手当などの独自の助成制度を設けている場合があります。あらかじめお住まいの自治体に確認をし、申請が可能な手続きは早めに済ませましょう。
離婚届を提出する前には十分な準備を
離婚届を市区町村役場の開庁時間に提出し、作成した離婚届に不備がなければ即日で受理してもらうことが可能です。離婚に至る理由や感情はさまざまですが「一刻も早く相手と縁を切りたい!」という思いから、すぐに離婚届を提出してしまう方も実際にいます。
養育費や財産分与は離婚届の提出後でも取り決めが可能ですが、財産分与は離婚後2年以内でないと行えません。また離婚届の提出の際には氏や戸籍をどうするかについて記載しなければいけません。
離婚届を提出してから「こうすべきだった」と後悔しても、変更手続きが難しいこともあります。離婚届を提出する前に、十分な準備をしておくことを強くお勧めします。
離婚届に不備はないかを確認
離婚届を提出する前に不備がないかどうかをよく確認しておきましょう。軽微なミスであれば役所窓口で訂正が可能ですが、配偶者や証人の署名に不備があった場合、もう一度相手方に書き直しを依頼しなければいけません。
筆記用具は必ず黒のインクペン、ボールペンを利用してください。修正テープや修正ペンは使用してはいけません。
提出前に捨て署名をしておく
捨て署名(捨印)とはあらかじめ直筆で署名をしておくことにより、訂正印の代わりになるものです。捨て署名を記入しておくと、離婚届の軽微なミスが判明した場合に役所窓口で訂正をしてもらえることがあります。
捨て署名欄が離婚届にない場合は、枠外の空いているところに2人で署名をしておくことで捨て署名と同じ扱いとなります。
氏や戸籍をどうするか決める
離婚届には離婚後に戸籍をどうするかを記載する欄があります。先に触れた通り、新しい戸籍を作った後に実家の戸籍に戻る場合は家庭裁判所で申し立てを行わなければならず、煩雑な手続きが必要になります。
離婚後に実家に戻る予定の方や助けを借りようと思っている方は、安易に判断せず親族に相談をするのもよいでしょう。
離婚条件は離婚届提出前に決める
婚姻期間に仕事をしていなかった方、収入が少なかった方が離婚後に安定した生活を送るためには財産分与の取り決めが非常に重要です。夫婦間に子どもがいる場合は養育費も大切な存在です。
離婚前に法的効力のある離婚協議書を作成しておくことで、相手が約束を破った際に法的な手続きを取ることが可能です。離婚届の提出前に弁護士に相談し、離婚条件を定めた離婚協議書を作成することを強くお勧めします。
財産分与には期限がある
財産分与の請求期限は離婚成立から2年と定められています。時効ではなく除斥期間と呼ばれており、時効のように中断や延長はありません。
財産分与は離婚後でも取り決めができます。しかし残念なことに、財産分与をしたくないという思いから離婚後に音信不通になったり、理由をつけて話し合いに応じなかったりする人も存在するのが実態です。
必ず離婚届の前に財産分与について話し合い、離婚協議書を作成するようにしてください。
過去の養育費は請求できない
養育費の場合、財産分与のような請求の期限はありません。離婚してから何年が経過していても、子が成人していない場合はいつでも養育費の請求が可能です。
しかし養育費は原則として過去に遡って請求することはできません。養育費についても財産分与と同様、離婚前に取り決めをしておきましょう。
まとめ
離婚届は受理された日から効力があり、その日から離婚が成立します。ただし休日や夜間に離婚届を提出した場合、審査が翌開庁日以降となるため即日で離婚は成立はしません。不備があると再度役所に行く必要があるので、事前の確認が大切です。
離婚に際してはさまざまな手続きが必要になります。仕事を休んだり、子どもを預けたりして役所へ行く方も多いと思います。効率よく手続きを進められるよう、あらかじめ準備しておきましょう。
財産分与や養育費は離婚後でも取り決めが可能ですが、財産分与には期限があり、養育費は過去に遡って請求することはできません。離婚届を提出する前に必ず話し合いを行い、取り決めをしたうえで離婚手続きを行うようにしてください。