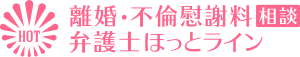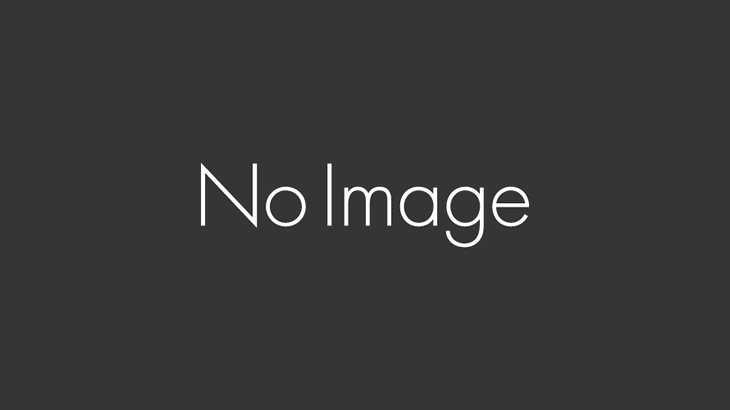- 「妻との離婚を検討している、事前にできる準備は?」
- 「離婚はしたいけど、妻との財産分与や養育費が気になってしまう…」
夫婦が離婚する際は、妻側が夫婦で住んでいた家を出ていくケースが大半です。そのため離婚原因が夫婦どちら側にあるかに関係なく、夫側が財産分与で妻側に支払いを行う事例が多く見られます。
男性が自分の収入や資産を把握しないまま離婚に踏み切った場合、財産分与で自分が損をしていることに気付きにくかったり、相場からかけ離れた養育費を請求されたりする恐れが。
その結果重い負担を強いられ、離婚後に生活が困窮する可能性もあります。今回は男性が離婚する際に事前に行っておくべき準備を解説します。離婚を検討している方はぜひ参考にしてください。
妻と離婚したい!と思った時にまずすべきこと
現代の日本において、夫婦が離婚することは決して珍しくありません。厚生労働省の調査によると、1年の婚姻件数47万4,741件に対し離婚件数は18万3,814件という統計が出ており、3分の1の夫婦が離婚すると言われることもあります。
(参考:厚生労働省|令和5年(2023)人口動態統計)
そのため離婚に抵抗を感じない人も増えつつありますが、だからといって安易に離婚を決断すべきではありません。状況によっては、今後の人生が大きく変わる可能性もあります。離婚をしたいと思ったら、まずは離婚のメリット・デメリット双方をよく考え、離婚条件や離婚後の生活、手続きの進め方のの見通しを立てることが大切です。
離婚するメリットを考える
まずは、離婚することによって得られるメリットを具体的に考えていきましょう。具体的には、以下の4つが挙げられます。
- 相手と離れることができる
- 義務感から解放される
- 時間が自由に使えるようになる
- 収入や貯蓄を自由に使えるようになる
- 異性と交際ができる
相手と離れることができる
離婚を考えるほど「自分と合わない」と感じる相手と一緒にいることは、日々の生活において大きなストレスになります。相手との会話が一切ないほど関係が冷え切っている場合、一緒に生活することに意味を感じられないでしょう。中には妻の姿を見るだけでイライラする、という方もいるはずです。
離婚をすると、相手とは離れて生活ができるようになるため、妻と一緒にいることで生じるストレスとは無縁になります。
義務感から解放される
近年では夫婦の所得が同じくらいの家庭、もしくは妻が中心となって家計を支えている家庭が増えつつあります。しかし多くの家庭の場合、夫が中心に家計を支えています。
そのため自分が家族のために頑張らなくてはいけないという義務感に重みを感じている方もいることでしょう。仕事を辞めたい、資格を取りたいなどと思っていても、家の収入のことを考えて踏み出せなかった方もいるはずです。
しかし離婚をすることによって家族を支えなくてはいけないという義務感からは解放されることになります。仕事を自由に選べるようになり、自分の好きな生き方を選択できるようになるでしょう。
時間が自由に使えるようになる
普段忙しく働いている男性にとって、休日はたいへん貴重なものです。しかし結婚をすると、休日は家事や育児のために時間を使うようになります。結婚や妻の出産をきっかけに、今までの趣味を手放した男性もいるのではないでしょうか。
しかし離婚をすることによって仕事の後の時間や休日を自由に使えるようになります。趣味に没頭したり、キャリアアップのための勉強に専念したりできるようになります。
収入や貯蓄を自由に使えるようになる
収入の管理方法は家庭によってさまざまですが、妻が家計を管理し夫はお小遣い制、という家庭は珍しくありません。妻は色々と買い物をしているのにも関わらず、自分は好きなものをなかなか買えないことにストレスを感じる方もいるのではないでしょうか。
自分の収入を自分で管理している場合でも、家庭のための支出や貯蓄が必要になり、全ての収入を自由に使えるという方は極めて少ないはずです。しかし離婚後は自分の収入は自分の好きなように使えるようになります。自分の趣味にお金を使ったり、貯蓄をして将来に備えたりすることも可能です。
異性と交際ができる
婚姻状態が続いている間に他の異性と関係を持つと不貞行為とみなされます。すると婚姻関係を破綻させた有責配偶者とみなされ、慰謝料を請求される可能性があるだけでなく、離婚において不利な立場に立たされます。
また妻との関係がどれだけ悪化していたとしても、不倫という行為は他人によい印象を与える行為ではありません。周囲に知られた結果、社会的信用を大きく損なうこともあり得ます。
しかし離婚をすれば異性と堂々と交際をすることができます。相手が同意すれば再婚も可能です。このように新しい家族を作るチャンスができることも離婚のメリットと言えるでしょう。
離婚することのデメリットも考える
「離婚をしたい」という気持ちが強まると、離婚のよい面ばかりに目が向きがちです。離婚には以下のようなデメリットもあります。離婚を決断する前にデメリットについても把握しておきましょう。
- 財産分与の支払い義務が発生する
- 親権が得られない可能性がある
- 子がいる場合は養育費の支払い義務が発生する
- 家事を全て自分で行なわなくてはいけない
- 生活費の支出が増えることがある
- 世間体に影響を与える可能性がある
- 体調不良の際に看病等をしてもらえない
- 再婚できない可能性がある
財産分与の支払い義務が発生する
財産分与とは離婚する際に夫婦が築いた財産を分け合うことです。財産を分け合う割合は、裁判所で離婚調停や裁判を行った場合、原則として夫婦2分の1ずつという運用がされています。妻より夫のほうが収入が多い場合でも、婚姻期間の間妻が夫を支えていたことを考慮し、財産は均等に分け合うケースが大半です。
マイホームなどの不動産も財産分与の対象ですが、不動産そのものは分割ができません。そのため不動産を売却して現金で分割する、もしくは一方の配偶者が不動産に住み続け、他方の配偶者に代償金(現金)を支払うことで分与を行います。
もし家を売却せずあなたが住み続ける場合、あなたが相手に不動産の半分に相当する金額を支払わなくてはいけません。
親権が得られない可能性がある
子どもがいる場合、離婚後は夫婦のいずれかが子の親権を持つことになります。自分が子どもを引き取りたいと思っていても親権が得られない可能性も視野に入れなくてはいけません。
子の親権は子どもの環境を重視して決められます。普段母親が子どもの面倒を見ている場合、その環境を維持できるよう母親に親権が渡る可能性が高いです。もちろん男性が親権を獲得できるケースもありますが、あらかじめ入念な準備が必要です。
離婚に際しては、子どもの面会交流のルールを決めることが一般的です。しかし交流のルールがだんだんと守られなくなる事例は少なくありません。子どもがいる場合は子どもと離れることも覚悟した上で離婚を決心しなくてはいけません。
子がいる場合は養育費の支払い義務が発生する
あなたが親権を獲得できなかった場合、子を養育する妻に養育費を支払う必要が生じます。離婚をしても親子関係は続いていくため、自分の子の養育費を支払うことは親として当然のことです。
しかし親権が得られない上に養育費を負担するという二重の痛手は、離婚の大きなデメリットであると言えるでしょう。
家事を全て自分で行なわなくてはいけない
離婚後に実家に帰らず一人暮らしを続ける場合、料理や掃除、洗濯などの家事を全て自分で行うことになります。
婚姻期間に家事を分担していた方、一人暮らしの経験がある方にとってはさほど抵抗がないかもしれません。しかし今まで家事の経験がない場合、家の家事を全て自力で行うことは離婚の大きなデメリットになります。
生活費の支出が増えることがある
夫婦の状況にもよりますが離婚後に支出が増えたと感じる人もいます。妻に収入があり生活費を一緒の家計から支払っていた場合、今まで二人で折半していた支出が全てあなた一人の負担になるためです。
また状況によっては養育費や慰謝料などの支払いが発生することも。離婚後に実際にどれくらいの生活費がかかるのか、必ず把握しておきましょう。
世間体に影響を与える可能性がある
離婚することに抵抗を感じない人が増えてはいますが、日本ではまだ離婚した人に対する偏見があります。そのため離婚をしたということを誰かに知られると、周囲に噂があっという間に広まってしまいます。
中には離婚の原因が妻にあるにも関わらず「嫁に逃げられた人」とあたかも男性側に原因があるように決めつける人も。噂や人目が気にならなければ問題にならないかもしれませんが、勤め先での評価に影響を与えるケースも実際にあります。
体調不良の際に看病等をしてもらえない
男性が離婚をして一人暮らしをする際の懸念材料の一つは、万が一体調不良になった際に看病をしてもらえないことです。
親族などを頼れればよいですが、もし看病に誰も来られない場合は通院や買い物も自力で行わなくてはいけません。体調を崩すと心も不安定になりやすいため、このデメリットを強く感じる方が多いでしょう。
再婚できない可能性がある
離婚するメリットの一つとして、異性との交際や再婚ができることを先にお伝えしました。しかし離婚を経験した男性が必ずしも再婚できるとは限らないことに留意してください。養育費や慰謝料の負担がある場合、それが再婚の障害となる可能性が高いです。
また先にお伝えした通り、離婚経験のある人への偏見はゼロではありません。新たなパートナーが問題ないと思っていても、周囲が再婚の反対をする可能性は多いにあります。
再婚をしない場合は老後までずっと一人で生活していくことになります。退職した後の生活をどうするか等、先のライフプランもよく考えなくてはいけません。
離婚後の生活の見通しを立てる
離婚をすると今までのライフスタイルが急変することになります。離婚後に不慮の事態に陥り「こんなはずではなかった」と後悔をしても、取り返しがつかないことが多いです。以下の項目について離婚後どうするかをよく考え、あらかじめ見通しを立てておきましょう。
- 離婚後の住居を具体的に考える
- 離婚後の家計をシミュレーションする
- 養育費の負担金額を算出する
離婚後の住居を具体的に考える
離婚後は少なくとも夫婦いずれかが今住んでいる家を出ていくことになります。一般的に女性が今の住居を出ていくことが多いですが、必ずそうだとは限りません。相手が環境の変化を嫌がり、現在の住居に残ることを希望するケースもあります。
またマイホームを離婚時に売却することになった場合、相手だけでなくあなたも引っ越しが必要になります。その場合、新しい住居をどうするかについて考えなくてはいけません。
賃貸住宅に引っ越しをすると引っ越し費用だけでなく契約の初期費用や家賃もかかります。実家を頼れる方は一時的に実家に住むという手段も選べますが、勤務先からの距離によっては通勤時間が大きく変化してしまう方もいるでしょう。
またあなたが離婚後に子どもを養育する場合、転居先によっては転校が必要になることも。子どもへの負担も考え、慎重に検討するようにしてください。
離婚後の家計をシミュレーションする
離婚後は収入・支出を全て自分で管理していくことになります。自分の収入が全て自由に使えるようになるため、離婚後の家計は問題ない、と考えている方も中にはいるかもしれません。
しかし長い間妻に家計の管理を任せていた場合、光熱費や通信費などでどれくらいのお金がかかっているのかを把握しにくい傾向があります。
総務省の調査によると、2024年の単身世帯でのひと月あたりの消費支出は169,547円という統計が出ています。
(参考:総務省統計局|家計調査年報(家計収支編) 2024年)
この数値はあくまでも全国の平均です。支出は地域や個人の状況によって変動するため一概には言えませんが、金額の目安が分からない方はこの結果を参考にしてもよいでしょう。
子どもがいて離婚後に自分が養育する場合、子どもにかかる費用も考慮しましょう。離婚後は一人親世帯向けの公的制度が利用できるようになりますが、子の成長に伴って支出は増えていきます。食費はもちろんのこと、進学費用や習い事、部活動などの費用が必要になるケースもあります。
養育費の負担金額を算出する
相手方が親権を獲得した場合、あなたは養育費を負担することになります。表立って口には出せないものの、正直養育費を払いたくないと考えている方も中にはいるでしょう。しかし養育費は民法第877条で定められた扶養義務に則ったものであり、支払い義務があります。
養育費の金額は父母間の問題のため、双方の話し合いで決められます。その際に目安となるのが、裁判所の公表している養育費算定表です。養育費は子の数や年齢、お互いの年収によって変動します。
例えば、以下のようなケースの養育費の算出方法を見てみましょう。
相手の年収:0円
子ども:1人 14歳以下
養育費・子1人表(子0~14歳)を参照し、お互いの年収が交わる部分を確認しましょう。上記の例の場合は毎月6万~8万円が支払う金額の目安になります。
離婚後にあなたの収入が著しく減少するなど、やむを得ない場合は養育費の減額が認められることもあります。しかし離婚後しばらくは決められた金額を支払い続けることになるため、離婚に踏み切る前に必ず確認をしておくようにしてください。
離婚で男性が不利にならないためにすべき準備
ここまで紹介した事柄についてよく検討し、離婚が自分にとって最善であると判断した場合は離婚に向けて準備を進めていくことになります。十分な準備をしないまま離婚に踏み切った場合、男性は不利な立場に置かれやすい傾向があります。離婚を後悔のないものにするために、必ず入念な準備を行うようにしてください。
男性は離婚で不利な立場に置かれやすい
離婚に向けての準備について紹介をする前に、男性が離婚で不利な立場に置かれやすい理由を紹介しましょう。具体的には以下の3つが理由として挙げられます。これらの不利な状況を打破するためには、念入りな準備が不可欠です、
- 妻よりも収入が高い傾向がある
- 財産を完全に把握しにくい
- 子の監護を妻が主に行っていることが多い
妻よりも収入が高い傾向がある
離婚に伴い、婚姻期間中に築いた財産は夫婦で公平に分配されます。妻のほうが収入が少なかったとしても、家庭生活を支えていたことが考慮されます。財産の大半が夫の収入から生み出されたものだったとしても、妻に財産の半分に相応する金額を支払わなくてはいけません。
家事は決して楽なものではなく、それを一人で全てこなしていたのであれば尚更です。しかし毎日責任感に追われながら働いていた男性にとっては不公平であるという印象が拭えないのではないでしょうか。
財産を完全に把握しにくい
財産分与の対象となるのは婚姻後の共有財産です。お互いの預金や株式、保険の積立、不動産などが例として挙げられます。離婚をする際には該当する財産を全て確認し、公平に分与する必要があります。
しかし妻が家計を管理している場合、貯金用に隠し口座を作っていたり、子ども名義の口座に積み立てをしていたりする可能性があります。あなたが離婚を切り出して財産分与をするよう伝えた場合、それらの口座を故意に隠すかもしれません。
子の監護を妻が主に行っていることが多い
夫婦間に子どもがいて親権を獲得したいと考えている場合、父親は極めて不利な立場に立たされます。父親よりも母親が中心に育児を行う家庭が多く、離婚後もそれを継続すべきだとみなされるためです。
総務省の人口動態調査によると、離婚後に母親が親権を獲得するケースは9割近くにのぼります。特に子どもが乳幼児の場合、子は母親と引き離すべきではないという「母性優先の原則」が適用され、母親に優先的に親権が渡ります。
父親が親権を絶対に獲得できないというわけではありませんが、離婚後に子どもの親権を持ちたいのであれば準備は不可欠です。
離婚について正しい知識を持つ
離婚は人生に何度も訪れる出来事ではなく、むしろ縁がない方のほうが多いです。そのため、専門家以外で離婚についての知識を十分に持っている方は多くないでしょう。離婚をスムーズかつ有利に進めるためには、まず離婚について正しい知識を持つことが重要です。
離婚の手段について
まず離婚には手段によって呼び方があること、状況によって離婚までの段取りが違うことを確認しましょう。離婚の手段は以下の3通りです。
- 協議離婚
- 夫婦間の話し合いによって離婚すること
- 調停離婚
- 離婚調停を申し立て、調停での話し合いによって離婚すること
- 裁判離婚
- 離婚裁判で法的に離婚を認めてもらうこと
夫婦の離婚はお互いが離婚に同意し、離婚届を役所に提出すれば成立します。裁判所への申し立て等を行わず、夫婦で話し合った上で成立する離婚を協議離婚と呼びます。
しかし相手が離婚に反対している場合、条件が折り合わない場合は裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員を介して話し合いを行います。この離婚調停によって成立する離婚は調停離婚と呼ばれます。
調停を経ても離婚が成立しない場合、裁判所に裁判の申し立てを行い、法的観点から裁判離婚を認めてもらうことになります。しかし裁判で離婚を認めてもらうためには「離婚に至って当然である」と客観的に判断ができる法定離婚事由が必要です。
法定離婚事由について
協議離婚、調停離婚の場合は相手が同意しないと離婚が成立しません。しかし相手の行為が法定離婚事由に該当する場合、相手の意思に関わらず裁判で離婚を認めてもらうことができます。法定離婚事由は以下の5つです。
- 不貞行為があった
- 配偶者から悪意の遺棄があった
- 配偶者が3年以上生死不明である
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
- その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
離婚が認められる具体的な例
では実際にどのようなケースで離婚が認められるのかを確認しましょう。例えば相手が配偶者以外の異性と肉体関係を持っていた場合は「不貞行為があった」ということを理由に離婚を認めてもらえます。
項目2つ目の「悪意の遺棄」とは、民法で定められた夫婦間の同居義務・協力義務・扶助義務を故意に守らないことを指します。相手が家事や育児を完全に放棄している、無断で別居をしていることなどが該当します。
4つ目の「強度の精神病」とは、症状が重く共同生活が営めないこと、回復の見込みがないことの両方に該当する場合のみ法定離婚事由に該当します。例えばアルコール依存症などは治療によって回復が見込めるため、法定離婚事由とは認められません。
裁判では明白な証拠が必要
離婚裁判では、有責配偶者(離婚の原因がある側)が法定離婚事由に該当しているという客観的な根拠を示さなくてはいけません。
例えば不貞行為を理由にする場合、相手との肉体関係があったことを示す証拠、もしくは誰が見ても「肉体関係があった」と安易に推測できる記録が必要です。相手とのLINEのやりとりを撮影したもの、本人もしくは相手の自白、ホテルに出入りする写真・動画などが有効となります。
不貞行為の際に有効な証拠については、以下の記事で詳しくまとめています。併せて参考にしてください。
「不貞行為」はどこからの行為?不倫・浮気との違いや当てはまるケース、法的に有効な証拠を解説!
相手が離婚を頑なに拒み続けた場合、最終的には裁判で離婚を認めてもらうことになります。その際に証拠がないと「やられた」「やっていない」の繰り返しの水掛け論になり、離婚の決め手になりません。そのため、あらかじめ証拠を準備しておくことが非常に重要です。
婚姻を継続し難い重大な事由とは?
4項目目までの法的離婚事由に該当していない場合、5つ目の「婚姻を継続し難い重大な事由」による離婚を視野に入れていくことになります。婚姻関係が破綻していて、修復の見込みがないと判断されるケースです。具体的には以下のような事例が該当します。
- DVやモラハラがある
- 犯罪行為によって服役中である
- 過度な宗教活動をしている
- 性的不和・セックスレス
- 相手親族との関係が極めて悪化している
- 長い期間別居している
法的に離婚を認めてもらうためには、いずれの場合も第三者が「離婚してもやむを得ない」と判断するに足りる証拠が必要です。繰り返しになりますが、あらかじめ証拠を準備しておくことが離婚の可否の分かれ道になります。
離婚条件について
離婚届を記入する際には、子の親権者を記載しなくてはいけません。他の離婚条件について決めることは当事者の自由ですので、親権者以外の条件を決めないままでも離婚は可能です。しかし離婚後に「話し合っておくべきだった」と後悔しないよう、離婚の際に決める条件についてあらかじめ整理をしておきましょう。
- 親権
- 養育費
- 面会交流
- 財産分与
- 慰謝料
夫婦いずれかが親権を獲得した場合、非監護親との面会交流について定める必要があります。面会交流とは、子と離れて過ごすことになった親が、子と定期的に会ったり交流をしたりすることを指します。本来であれば「月に1回」など具体的な回数やタイミングを決めることが一般的です。
しかし近年では面会交流という形を取るのではなく、離婚後も子の行事に参加したり、習い事や学校の送迎を行ったりなど、育児に協力し続ける非監護親も増えています。子どもの環境のことも考慮し、どのように携わっていくかを検討しましょう。
また相手が有責配偶者の場合は慰謝料を請求することができます。慰謝料は離婚後でも請求が可能ですが、時効があります。不倫の場合は不貞行為を知った日から3年、離婚についての慰謝料は離婚した日から3年です。長いと思うかもしれませんが、離婚後の環境の変化で手続きが疎かになるとも限りません。早めに準備をしておくとよいでしょう。
慰謝料の決め方、相場については以下の記事で解説をしています。慰謝料請求を考えている方はぜひ参考にしてください。
協議離婚の慰謝料相場が知りたい!増額・減額できる秘訣や慰謝料の決め方を解説
離婚時の妻からの請求に備える
男性の場合、離婚時に妻から財産分与などを請求される側の立場であることが多いはずです。相手から請求された時に備え、あらかじめ準備をしておきましょう。
財産分与
財産分与を有利に進めるためには婚姻期間中に夫婦で築いた財産を把握し、相手の財産隠しを予防することが何よりも重要です。
先の項目でも触れましたが、夫は夫婦の財産を把握しにくい傾向があります。特に妻が夫の給与を管理している場合、あなた名義の通帳ではなく、自分もしくは子ども名義の通帳に貯蓄をしている可能性があります。
株式や学資保険、生命保険などの積み立ても財産分与の対象です。家にある通帳やキャッシュカード、郵便物などを手がかりに、可能な限り財産を把握する努力をしてください。
財産隠しを防ぎたい方や相手の財産をきちんと把握したい方は、以下の記事も併せて参考にしてください。貯金を隠すことについての記事ですが、相手の財産を暴く方法についても紹介しています。
離婚時に貯金を隠すことは可能?財産分与の基礎知識と不利にならない方法
慰謝料
あなたが有責配偶者だった場合、離婚に際し慰謝料を請求される可能性があります。慰謝料の請求は自分で、もしくは弁護士に依頼をして請求することができますので、予告なしに慰謝料請求の内容証明郵便が届くこともあります。
相手からの請求金額は相場より高いことが多いため、そのまま支払いに応じることはお勧めできません。特に相手が離婚を拒んでいる場合、故意に法外な請求をすることもあります。そのため自分で判断をするのではなく、弁護士などに相談することをおすすめします。
養育費
夫婦の間に子がいて、相手方が親権を獲得した場合は養育費を請求されます。離婚後もあなたと子が親子であることに変わりはないため、養育費は支払わなくてはいけません。具体的な金額や支払い期間、支払い時期を話し合いで決め、必ず書面で残しておきましょう。
具体的に取り決めるべき項目は以下の通りです。
- 1ヵ月あたりの金額
- 支払い期間
- 支払い日・支払い方法
- 特別費用について
1ヵ月あたりの金額
養育費は原則として月額で支払うため、1ヵ月あたりの支払い金額を話し合いで決めることになります。1ヵ月あたりの養育費の金額は、裁判所の公表している養育費算定表に従って決めることが一般的です。
支払い期間
養育費を支払う期間は、子が成人するまでが目安とされます。しかし「20歳まで」「18歳まで」「大学を卒業するまで」等、さまざまな考え方があるため、夫婦で意見が食い違いやすい傾向があります。
養育費をいつまで支払うかについては、夫婦の意向だけでなく子どもの状況や進路をふまえた上で決めるべきです。離婚によって子どもの進路選択の幅が狭まることがないよう、適切に支払い期間を定めるようにしてください。
支払い日・支払い方法
養育費の支払いは、銀行口座への振り込みによって行う場合が多いです。養育費の取り決めの際に振り込み先と日付を決めておくようにしましょう。
特別費用について
毎月支払いを行う養育費には、子の生活費、学費などが含まれています。しかし子どもが成長する過程で、以下のようなイレギュラーな支出が発生することがあります。
- 部活動の費用
- 習い事や進学塾の費用
- 病気やケガをした際の治療費
- 大学の入学金・授業料
これらの費用は月々の養育費ではカバーができませんが、婚姻期間中であれば夫婦が共に負担すべき費用です。上記のような特別な費用が発生した場合にはどうするか、夫婦で前もって確認をしておくことが好ましいでしょう。
子の親権を獲得したい場合は念入りな準備が必要
親権は継続的な監護実績があることや離婚後の養育環境が整っていることを重要視して決められます。そのためあなたが「親権を獲得したい」と主張しても、優先的に親権が取得できるわけではありません。
子がまだ小さい場合、母親のほうが親権を獲得しやすい傾向があります。しかし今までの養育状況によっては、男性が親権を獲得することもあります。これらを第三者に明確に実証できるよう、早いうちから行動に移すことが重要です。
子に積極的に携わる
まずは育児に積極的に携わることが重要です。休日だけでなく普段から子どもと積極的に接するようにしてください。親権を獲得する際に重要な要素の一つが「監護実績」です。離婚後も子を安定して監護できることを実証するための取り組みとして、挙げられるのは以下のような行動です。
- 子どもの食事を用意する
- 子どもの健康管理を行う
- 子どもの寝かしつけを行う
子どもの食事を作る
食事は子どもの健やかな成長に不可欠です。普段から子どもの食事を用意するようにしましょう。レトルト商品や惣菜を用意するのではなく、自分で栄養バランスのとれた食事を準備していると、監護能力があると判断される可能性が高いです。
子どもの健康管理を行う
健康管理とは子どもが体調を崩したときに病院に連れていったり、予防接種の管理をしたりすることです。子どもの健康管理に携わっている実績があれば、監護能力が高いと判断されるでしょう。
子どもの寝かしつけを行う
親権を決める際には、子どもの環境を変化させないことが極めて重要視されます。子どもが今まで母親と寝ていて自分だけが別に寝ていた場合、親権獲得に極めて不利な状況となるでしょう。子どもがあなたと一緒に安らげる環境を作っていくことが重要です。
客観的に判断できる記録を残す
親権を裁判で争うことになった場合、あなたが「育児に携わっていた」と主張しても、相手方が否定することもあります。実際に子どもの監護をするだけでなく、それを記録に残すことが非常に大切です。具体的には、以下のような行動が有効です。
- 母子健康手帳に記録をする
- 園や学校と積極的に関わる
- 育児の記録を残す
母子健康手帳に記録をする
子どもが小さい場合、母子健康手帳に予防接種や身体状況の記録を行っているかと思います。母子健康手帳には、保護者が子どもの健康状況を記載する欄もあるのをご存知でしょうか。
母子健康手帳は、家庭裁判官が子の健康状態を把握するために提出を求める資料です。日頃より子の様子を記録しておくことにより、父親が育児に密に携わっていると判断される可能性があります。
園や学校と積極的に関わる
子どもが幼稚園や保育園、学校に通っている場合は運動会や授業参観などの行事に積極的に参加しましょう。子との絆が強まることはもちろんのこと、「父親が育児に携わっている」という第三者からの証拠を残すこともできます。
育児の記録を残す
子どもの成長記録を残した日記も客観的な記録として有効です。最近ではブログやSNSなどのインターネット媒体で記録を残す方も増えています。インターネットの場合、紙の記録とは違って日付の改ざんができないため、相手から「偽造だ」等と言いがかりをつけられる心配もありません。
ただしインターネットの場合は子どもの個人情報の保護にはくれぐれも注意しなくてはいけません。記録を目的とする場合は非公開設定、もしくは一部の友人限定で公開するようにしましょう。
親族に協力を求める
あなたが普段仕事で忙しく、かつ子どもが小さい場合、育児に充分に携われないと判断される恐れがあります。親権を獲得するためには離婚後の養育環境が整っていることを主張することも重要です。
可能であれば、親族に監護補助者としての協力を求めましょう。一緒に住むことが理想的ですが、難しい場合は近くに住むなど、いつでも育児の協力を仰げる環境を作るようにしてください。
離婚手続きの具体的な進め方
離婚に向けての準備が整ったら、いよいよ具体的に離婚に向けて手続きを行っていくことになります。男性が妻に離婚を切り出す際のポイントや注意点を確認しましょう。
離婚の意思を相手に伝える
離婚したいと心の中で思っていても、相手にはっきりと「離婚したい」と伝えることは勇気が要ることです。だからといって曖昧に話し合いを始めると、相手に対する不満だけが伝わってしまい、感情的な口論になってしまう恐れがあります。まずははっきりと離婚したいということを伝えるようにしましょう。
条件について話し合う
離婚に際する財産分与や養育費、慰謝料などについて理由や根拠を示しながら伝えるようにしましょう。具体的な条件を提示することにより、離婚の意思が相手に伝わり、お互い冷静に話し合いができるようになるでしょう。
離婚を切り出しても、すぐに離婚に応じない方もいます。別居に踏み切る場合には、必ず理由を伝えるとともに、婚姻費用の支払いについて決めておくようにしてください。
離婚協議書を作成する
離婚について双方の合意ができた場合は、必ず離婚協議書を作成しておきましょう。離婚協議書は、慰謝料・財産分与・養育費などの取り決め内容を明確に書面にしたものです。
養育費などについては口約束だけで書面に残さない、という夫婦も中にはいます。支払う側の場合、書面がなくても問題がないだろう…と思う方もいるかもしれません。
しかし後から「金額を変更してほしい」等と養育費や慰謝料の増額を求めてくるケースもあります。このような合意内容の蒸し返しを防ぐためにも、文書として残しておくことが非常に有効です。
男性が離婚を決意したときに注意すべきこと
最後に離婚を決心した男性に向けて注意すべき行動を解説します。繰り返しになりますが、男性は離婚において不利な立場に置かれやすい傾向があります。今は問題ないと思っていても些細な行動をきっかけに状況が変わることもあり得ますので、注意しましょう。
無断で別居しない
相手が離婚に反対し続け、離婚裁判の申し立てもできない場合は別居に踏み切ることで離婚を認めてもらえる可能性があります。別々に暮らし続けることにより、夫婦仲が修復不可能であることが立証できるためです。
別居をする際には、必ず相手に理由を伝えて家を出ていくようにしてください。また別居期間中は、相手の生活費に相応する婚姻費用を支払わなくてはいけません。
これらを怠ると、夫婦の同居義務・扶養義務を故意に放棄したことになり、法的離婚事由の「悪意の遺棄」に該当する行為になります。有責配偶者になると離婚が著しく不利になるばかりか、慰謝料を請求される恐れもありますので注意しましょう。
別居を考えている方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。別居前の準備や注意点を詳しくまとめています。
【離婚したい人向け】別居前にやること・準備マニュアル|知っておくべきポイント・注意点とは
条件を妥協しない
相手が離婚に強く反対している場合、離婚と引き替えにあなたに極めて不利な条件を提示することがあります。一刻も早く離婚をしたいという気持ちから相手の条件を全て受け入れてしまう方も中にはいます。
財産分与の場合、2年以内であれば錯誤を理由にやり直しができる場合がありますが、2年を超えると原則としてやり直しはできません。
子どもの親権を取り戻したい場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、親権者変更調停と裁判を経て親権者決定を行うことになります。手間と時間がかかるため、仕事をしながら自分で手続きを進めるのは難しいでしょう。
相手が離婚を拒んでいるのであれば、多少の妥協は仕方がないかもしれません。「これは譲れない」というラインをあらかじめ決めておき、後悔のない選択をしてください。
離婚成立までは異性と交際しない
いくら妻との関係がうまくいっていないとしても、法的に離婚が成立するまでは異性と交際しないほうが安全です。離婚成立より前に異性と交際をすると、不貞行為とみなされる可能性があります。するとあなたが有責配偶者となり、法的に不利な立場に立たされます。
不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを指します。では性的関係を持たなければいいのか、というとそうではありません。宿泊を伴う旅行があった場合、相手があなたの家に出入りをしていた場合は「肉体関係がない」と主張しても裁判所には通用しない可能性が高いです。婚姻期間中は異性と交際することを避け、離婚を成立させることに専念すべきでしょう。
有利な条件で離婚したいなら弁護士に相談を
繰り返しになりますが、男性は離婚において不利な立場に立たされやすい傾向があります。少しでも有利な条件で離婚を進めたいのであれば離婚問題に詳しい弁護士に相談をすることをおすすめします。
不利な条件での離婚を防げる
離婚をする際には、財産分与や慰謝料、親権など、決めるべきことがたくさんあります。離婚条件は夫婦での話し合いで決めていくことになりますが「離婚に合意してもらいたい」という気持ちから妻の要求に流されてしまう方もいます。
弁護士に相談することにより相手の主張が法的に正当かを見極めてもらえます。公平な条件での離婚を実現できるよう、代わりに交渉してもらうことも可能です。証拠の収集や書面の作成なども任せることができるため、安心して交渉に臨むことができるでしょう。
相手方への対応や手続きを一任できる
妻との仲が険悪になっている場合、妻にコンタクトを取ること自体が憂鬱だという方もいるでしょう。相手が感情的になり建設的な話し合いができなかったり、話し合い自体に応じてもらえなかったりすることもあります。
離婚問題を弁護士に依頼することで相手との交渉は全て弁護士に任せることができます。精神的なストレスを軽減しながら、スムーズに手続きを進めることができるのは大きなメリットです。
まとめ
今回は妻との離婚を考えている男性に向け、離婚前に行うべき準備について解説しました。離婚を有利に進めるためには、あらかじめ妻からの請求に備え、財産や支払うべき養育費を把握することが重要です。
また不貞行為やモラハラなど、客観的な証拠を収集することも重要です。夫婦間に子どもがいて親権を獲得したい場合には、日頃から育児に積極的に携わり、離婚後も子どもが父親のもとで健全に過ごせる環境を作りましょう。
妻と離婚したい男性は早めに弁護士へ相談して準備を進めることをおすすめします。専門家のサポートを受けながら進めることで、精神的な負担を軽減しつつ、より有利な形での離婚を実現できるでしょう。