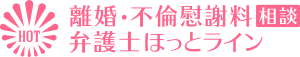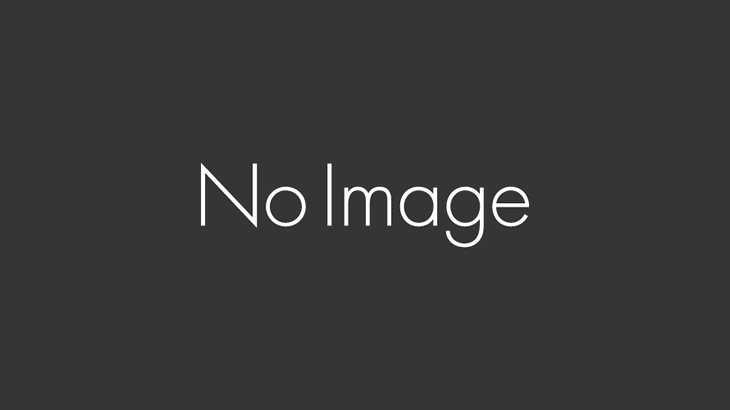- 「共依存夫婦ってどんな夫婦?」
- 「共依存関係から抜け出す方法が知りたい」
お互いに相手に依存しあっている夫婦のことを共依存夫婦といいます。とはいえ、夫婦関係は多かれ少なかれ依存しあっているもの。共依存夫婦でも問題ないのでしょうか?こちらの記事では、共依存夫婦の特徴や主な原因だけでなく、共依存夫婦の末路や危険性についても紹介していきます。
究極的に見ると双方が良ければ共依存夫婦でもいいのかもしれませんが、子どもや周囲の人を巻き込まざるを得なくなると問題は深刻です。場合によっては共依存関係から抜け出す必要があるでしょう。まずは共依存夫婦とは?というところから、問題点や解決方法を明らかにしてきましょう。
共依存夫婦とは
そもそも共依存夫婦とは、どんな夫婦関係なのでしょうか。心理状態などをもとにして、解説していきます。
依存とは
共依存について考える前に「依存」とはどのようなものなのかを見ていきましょう。「アルコール依存症」や「ギャンブル依存」などという言葉を聞いたことも多いでしょうが、依存とは、人と人・物と人などが互いに頼り合う間柄おことをいいます。
そして「依存症」は、特定の何か(アルコール・薬・ギャンブル・買い物など)に心奪われ、止めたくても止められない状態になることと定義されています。夫婦の共依存も、上記と同じような心理状態ですが、対象は物や行為ではなく、人に対して依存している状態といえます。
共に依存しあっている状態
そして共依存とは、互いに依存しあっている状態を表します。夫婦それぞれが配偶者に対して精神的に依存し、依存されている状態です。相手にとって自分はなくてはならない存在と思い込むことで、相手から離れることも自立することもできなくなり、互いに依存しあっている関係です。
ただし共依存夫婦のほとんどは、互いが同じレベルで依存しあっているとは限りません。片方が一方的に依存する状態でも成立しますが、片方からの依存が強すぎると相手が醒めてしまい共依存関係が崩壊する可能性も。最悪の場合、夫婦関係が破綻する場合もあるという訳です。
とくに夫婦間では互いが自分の役割を固定し過ぎるために共依存が生まれるケースが多く、互いに独立した一人の人間として存在するのが難しくなりがちです。
本来夫婦は適度に依存しあっているもの
そもそもでいうと、互いに適度な依存関係にあるのが夫婦です。夫婦は一つの家庭生活を営むために、互いに支え合って生きていくもの。そのため、「夫は家事を妻に依存する」「妻は夫に収入面で依存する」というだけでは、共依存とはいえません。
これに対して共依存夫婦とは、自己を犠牲にしてまで相手に依存するという点で異なります。健全な夫婦関係では、どちらも自分を大切にしながら相手との関係を築けますが、共依存では相手に依存しすぎるあまり自分を見失うケースが多く、夫婦関係のバランスが崩れやすくなります。
共依存夫婦の心理状態
共依存夫婦は互いに「相手は自分がいないと生きていけない存在であり、自分以外の人間に相手は務まらない」と考えています。まさに相手に必要とされることを通じて、自分の存在意義を見出している状態です。そのため、相手に否定されたり嫌われたりすることを極端に恐れる傾向があります。
相手に嫌われないように相手の意見や気持ちを異常なほど気にしてしまい、常に相手の顔色をうかがって、相手が起こっていたりするとその原因が自分にあるのではと考えてしまいがちです。そして自分の感情や言いたいことを相手に伝えられず、相手の気分を害さないように絶えずひやひやしながら生活をしている状態に。
相手の要求に過剰なまでに応じたり、相手の言い分を絶対的に守ろうとするため、相手もその状況に甘えて助長しやすくなります。結果的に夫婦の一方が、他方を精神的に支配している状況に陥りがちです。支配している側はその状況に満足感を得てその状況に依存し、支配されている側はその状況から脱したいという発想になりません。結果として、一方的な精神的支配の関係性が固定化しやすくなります。
夫婦以外で共依存に陥りやすい関係
共依存に陥りやすい関係には、夫婦関係以外でも親子関係や職場の人間関係が該当します。親が子どもに対して過度に干渉したり行動を制限したりするのは、親子間の共依存の特徴です。また職場関係では、頼られたい上司と独り立ちできない部下の組み合わせが共依存に陥りやすいです。
部下を指導することが自己肯定感を高める手段となっていて、部下は煩わしさを感じながらも言うことさえ聞いておけば安心という気持ちから常に上司の指示を待つようになります。この状況は、互いの存在がないと困るという共依存に陥っている可能性が高いです。
そして共依存関係では、相手を思いやるあまりに日常生活でのトラブルを引き起こす傾向にあります。
共依存状態になる主な原因
ではどのような原因から、夫婦は共依存状態に陥りやすいのでしょうか。
経済的依存から
とくに夫婦間では、経済的依存が共依存のきっかけになることが少なくありません。夫のみが仕事をして妻が専業主婦をしている場合、専業主婦の妻には生きるための経済力がなく、仕事をしている夫を立てて生きていくしかありません。
もちろんこのような夫婦のあり方は悪いものではなく、互いに互いの得意なことやできることを補い合って家庭生活を作り上げている夫婦もたくさんいます。しかしこのような経済的な依存関係がきっかけとなり、夫の機嫌を気にしたり自己中心的なふるまいに耐えながら続けていくことで、相手に尽くすことが当たり前となり、相手から嫌われることに恐怖を感じるようになると、相手に精神的に依存する状況に陥ってしまいます。
夫や妻の使い込みで離婚をお考えの方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「夫や妻の貯金使い込みで離婚できる?別居時に気を付けたいこと&財産分与で損しない方法」
アルコールなどの依存症
アルコール依存症の配偶者を献身的に支えるうちに、相手は自分の助けなしに生きていけないと思うようになり、相手を支えることで自分の存在価値を見出すようになるケースも少なくありません。結果として、相手に過剰な世話をしがちな状況になっていきます。
そして依存症の患者側は、そのような支えがあることに安心感を得て、アルコールに依存し続けられる状況が作り出されることでいつまでもお酒がやめられず、依存症からの回復が困難に。このように献身的な支えがあることで依存症はよくならず、支えている側も相手に依存してしまうので、延々とその状況が続いてしまい、依存症の症状だけが悪化していってしまいます。
このような状況は、薬物依存症やギャンブル依存症、買い物依存症など他の依存症にも同様に見られます。
アルコール依存症の相手との離婚については、こちらの記事を参考にしてください。
「アルコール依存症の相手と離婚したい!離婚の可否やスムーズに離婚方法、ポイントなどを徹底解説」
精神疾患
夫婦のどちらかが精神疾患を患ったときにも、共依存の原因になる可能性があります。こちらも支える側と支えられる側という図式が出来、どちらも相手に依存しやすくなるため。支える側は相手のすべてを支配できているような状況に安心感を覚えて、無意識のうちに相手の行動や考えをコントロールするようになります。
支えられる側は相手に甘えてしまうことで、精神疾患がなかなか治らない状態になります。
うつ病で離婚するときの慰謝料については、こちらの記事を参考にしましょう。
「うつ病で離婚するときに慰謝料は発生する?状況別の相場や請求方法、条件を解説」
日本独自の家族制度から
共依存夫婦が生まれる原因の一つに、日本独自の古くからの家族制度があると考えます。現在の夫婦同一姓制度では、ほとんどの女性が男性側の氏を名乗ることから、無意識的に男性に依存する生き方が普通であると考えます。またかつては専業主婦が当たり前で、女性が家で家事や育児を受け持ち、男性は外に働きに出るのが一般的でした。
近年では女性の社会進出が進み、「専業主夫」という言葉も生まれましたが、この場合も一方が経済的に依存する生き方としては、専業主婦と同じです。
過去の心の傷から
過去にDVやモラハラ被害など、心の傷(トラウマ)を受けたことから、共依存夫婦になる可能性があります。とくに「辛いのに加害者から離れることができない」という心理状況は、トラウマを受けたときに形成されてしまうと分かっており、「トラウマティックポンディング(トラウマ性の絆)」といわれています。
トラウマティックポンディングは、虐待した側とされた側の間で生じる感情的な強い結びつきのこと。暴力を振るった配偶者が激しい愛情表現をしてくれるときがある、母親が気に入らないことがあると何度も叩いてくる一方ですごく優しいときがあるなど、罰(ムチ)と飴(報酬)が周期的に繰り返されることで、長期間のうちに徐々に形成されていきます。
被害者が加害者に強い愛着もしくは執着を感じてしまうのは、被害者が生き延びるための当然の反応です。決して被害者に何か問題があるからではありません。
不健全な成育歴から
幼少期に「機能不全家族」といわれる環境で育った場合、共依存夫婦になる可能性があります。機能不全家族とは、家族間のコミュニケーションや役割分担がうまく行われず、家族の心身の成長や健康に悪影響を及ぼす家庭のことを指します。
例えば虐待やDVが日常的に行われている家庭やアルコール依存症患者がいる家庭、親が過度に支配的・過保護・無関心な家庭が該当します。このような過程で育たざるを得なかった子どもは、成長して大人になってからも対人関係の問題や生きづらさを抱えてしまいがちです。このような状態のことを「AC(アダルトチルドレン)」といいます。
家庭にトラウマを抱えて成長した人は、無意識のうちに同じ体験や関係を再現してしまうことがあります。辛い経験をしたにもかかわらず自分もまたその渦中に身を投じるという、一見矛盾して見えるこの行動は「トラウマの再演」といわれ、共依存の原因につながります。
自己肯定感が極端に低い
自己肯定感が極端に低いと、共依存夫婦の原因となります。幼少期に親から褒められた経験がない、学生時代にいじめにあったという経験から、健全な自己肯定感がはぐくまれないケースがあります。また容姿や学力にコンプレックスがある人は、失恋や受験の失敗が自己肯定感の低さにつながる可能性も。
自己肯定感が低いままで大人になると、常に他人に見捨てられる不安を抱えていたり、自分にかけている部分を依存することで埋めようとすることで、共依存夫婦になる原因となります。
共依存夫婦の特徴
共依存夫婦にはいくつかの共通する特徴がありますが、顕著なのは次のような特徴です。
相手は自分でなければ務まらないという思い込みがある
共依存夫婦は互いに、相手にとって自分が代わりのいない唯一無二の存在であるという思い込みがあります。自分以外の人間では、相手が務まらないと考えているため、パートナーには自分が絶対的に必要という自信が。むしろ相手から必要とされていることで、自分自身の存在価値を見出している人さえいます。
常に一緒に居たい
共依存夫婦は、常に行動を共にする一心同体間が強い特徴があります。単に相手を好きだから・仲がいいから一緒に居たいという訳ではなく、相手を独占したい・他の誰かに取られるのが心配という気持ちが潜在的にあり、行動を共にすることで不安な気持ちを満たしているのかもしれません。周りの人からは、仲良し夫婦と映っていることも少なくありません。
連絡頻度が高い
共依存夫婦は常に相手とつながろうとするため、連絡頻度が高いのが特徴です。自分が今どこで何をしているかを相手に報告し、自分のことを気にかけてもらいたがります。同様に相手にも、頻繁な連絡を求めます。単に連絡回数が多いだけでなく「今どこで・誰と・何をしているのか」という相手の状況を根掘り葉掘り聞いてしまいます。
さらに相手が電話に出なかったり、LINEに返信しなかった場合には、その不安がさらに膨らみます。連絡する回数はどんどん増え、ふと気が付くと相手からの着信やLINEの履歴がズラリということも。このような行為がエスカレートし過ぎると、次第に夫婦関係が悪化し、破綻につながるかもしれません。
相手のことをすべて知っていないと気が済まない
共依存夫婦は、絶えず相手のことをすべて知っていないと気が済まないという特徴があります。「相手の助けになるためには、相手の行動を把握して相手の気持ちを知らなければならない」という考えからなのですが、相手が理解してくれないと「監視されている」と思われてしまう可能性が。
相手が何も教えてくれなくなると、ますます相手のすべてを知ることに執着し、手段ではなく目的になってしまいます。やがて双方の間に、大きな溝ができてしまうでしょう。
必要以上の相手の許可を求める
必要以上に相手の許可を求めるのも、共依存夫婦の特徴です。互いの束縛や干渉が強くなると、自分の取った言動が思いがけずに相手を不安にさせたり怒らせてしまうことがあります。このような衝突を避けるために、事前に自分の行動に対して相手の許可を取ろうとします。
本来は相手のことを思っての行動ですが、許可を取ることが当然になってしまうと、夫婦関係が従属と支配といった関係に陥ってしまう可能性があります。
相手の機嫌や気分に左右されやすい
相手の気分や機嫌に左右されやすいのも、共依存夫婦ならではです。共依存夫婦は自分の気持ちを押し殺し、相手の顔色をうかがいながら常に行動します。そして互いに依存しあっているので、相手のことを考えすぎてしまう傾向があります。そのため自分のペースで生活できず、相手の気分にいつも左右されてしまうという訳です。
例えば、相手の機嫌が悪いとビクビクおびえてしまう、相手がイライラしていると自分もイライラする、相手の機嫌が悪いのは自分のせいなのではと不安になるなどです。このような気持ちになりやすい場合は、共依存関係に陥っている可能性があります。
自分よりも相手の意見を尊重する
何かを決めるときでも、自分よりも相手の意見を尊重するのが共依存夫婦の特徴。というのも共依存関係に陥った人が最も恐れるのは、相手から嫌われることだからです。相手に嫌われたくないためだけに、相手の意見を尊重しているのであれば共依存状態といえます。
配偶者の非は自分の責任と思いこむ
配偶者の非は自分の責任と思い込むのも、共依存夫婦の特徴です。相手の機嫌が悪くなった場合はもちろん、相手に何かトラブルがあっても、全て自分の責任だと思い込んでしまいます。客観的に見れば相手に改善すべき点や至らない点があったとしても、配偶者の非を客観的に見られない状態になってしまっているのが共依存状態です。
【チェックリスト】共依存状態になりがちな人の特徴
こちらでは、共依存状態になりやすい人の特徴について見ていきます。当てはまる項目が多い方は、共依存関係に陥りやすい性格といえます。
- 子どものころ親からの愛情が不足していた
- 1人でいるのが苦手
- 相手に尽くし過ぎる傾向がある・頼られるのがうれしい
- 相手のためなら自分を犠牲にしてもいい
- 褒められても素直に受け入れられない
- NOといえない性格
- なんでも自分のせいだと思ってしまう
- つい周りの意見に合わせてしまう
- 同じ失敗を繰り返してしまいがち
- 自分の気持ちを伝えるのが苦手
- 他人との境界があいまい
- 物事を極端にとらえがちで客観的に見られない
- 1人で決断するのが苦手
- 好きになったら一途
- 経済的に自立できていない
- 自己肯定感が低いと感じる
常にネガティブ思考で、ちょっとしたことで落ち込みやすい性格の人は依存しやすいといえます。また自己肯定感が低いために「自分は捨てられてしまうのではないか」などと常に不安な気持ちから、相手を束縛しようとし、その状態が続くことで依存状態になります。
共依存夫婦の末路・危険性とは
共依存夫婦になると、どのような末路を迎えやすいのでしょうか。共依存関係の危険性についても、解説していきます。
支配・服従の関係ができやすい
共依存状態になると、支配と服従の関係ができやすくなります。とくに夫婦のどちらかの自己肯定感が極端い低いと、相手の承認や依存することに喜びを感じてどんどん共依存関係を深めてしまう原因に。夫婦間では習慣やパターン化された行動が日常的にあるので、支配・服従の関係がよりできやすいといえます。
初めのうちは喜びを感じていたことでも、次第に感情的な負担が大きくなり、関係の修復が困難になることも少なくありません。
子どもへの影響
共依存夫婦の間に子どもがいる場合、子どもへの影響は無視できません。
過干渉・子離れができない
夫婦が共依存状態だと、子どもにも同じような関係性を求めるケースが見受けられます。「この子は私がいないとダメだから」と思い込んで、子どもの日常生活だけでなく学校生活や交友関係にも過度に干渉しがちです。子どもは何も分からないので、それが普通だと思い、自分も親に依存する関係になりやすいです。
他の過程などと比較して「うちは何かおかしい」と気づいた子どもが、カウンセリングなどで自立心を取り戻した結果、結婚や自立を希望すると、共依存状態の親は子供の自立にうろたえて阻止しようとします。ここで親の反対を押し切ってでも自立しないと、親がいないと何もできず、自分の意思で何も決められない大人になってしまう恐れがあります。
ネグレクト状態になる
お互いがいれば何もいらないという共依存夫婦の間の子どもは、ネグレクト状態になりがちです。二人だけの世界に入ってしまい、子どもがいても世話を放置するケースがあります。子どもがネグレクト状態に陥ってしまうと、子どもの健康や生命に悪影響を及ぼす可能性があるでしょう。
DV・モラハラになりやすい
共依存夫婦であっても、夫婦で依存度に温度差があると、片方がDVやモラハラになりやすいです。片方がもっと自分に依存して欲しいと思っている場合、自分の意思に従わない言動をした相手に対して、暴力を振るったり言葉の暴力で自分に従わせようとします。被害者も暴力を振るった相手に嫌われたくないため、逆らおうとせず相手の言いなりになってしまいます。このような状態になると誰も周囲に止める人がいないため、状況は悪い方にエスカレートしていきます。
DV・モラハラと共依存の組み合わせは、非常よくみられる現象です。それでいて共依存関係に陥っているので、相手と離れたり離婚したいという発想にさえなりません。このように依存の内容が対等でなく、加害者側の依存が被害者の隠れた我慢の上にある状態は、非常に危険な共依存関係といえます。
すぐキレる旦那と離婚したいと思ったら、こちらの記事を参考にしましょう。
「すぐキレる旦那と離婚する方法|モラハラか?離婚すべきか?の判断基準と有利に離婚するためのポイント」
身体的・精神的に疲弊しやすい
共依存関係にあると、身体的・精神的に疲弊しやすくなります。共依存夫婦は相手に依存することと相手から依存されることで、自分の精神の安定を保っています。しかしこのような生活を続けるのは、自分の意見を押し殺して相手の意見にだけ従う生活になるため、ストレスが蓄積されます。結果的にうつ病などの精神疾患になる可能性も。
また夫婦間でDVがある場合には、暴力を受けることで身体的に傷つけられ、精神的に疲弊して正常な判断ができなくなります。精神的に追い詰められてくると不眠や頭痛・胃痛や動悸などの身体症状に現れることもあるでしょう。DVによりPTSD(心的外傷後ストレス障害)やうつ病などの精神疾患を発症する危険性もあります。
経済的に破たんしても離婚できない
経済的に破たんしても離婚できないのが、共依存夫婦の特徴です。夫婦の一方に浪費癖やギャンブル依存があって絶えずどこからか借金をしてくるケースで、あまりにも借金がひどかったり生活費を稼ごうとしない配偶者を見て、第三者が「離婚を考えた方がいい」というアドバイスをすることもあるでしょう。
しかし夫婦が共依存関係にあると、どれだけ相手の借金が増えようが仕事をせずダラダラしていようが、自分しか相手を救える人はいない、自分が借金問題も解決しなければならないという気持ちに陥りがちです。結果として経済的に破たんしても、離婚の選択肢すら頭に思い浮かばない人がいます。
不倫されても別れられない
共依存関係になると、不倫されても別れられない場合があります。共依存になりやすい人の中には、感情が曲がった形で表現されてしまうケースがあるからです。共依存夫婦の一方が不倫を繰り返している場合、客観的に見れば離婚をした方がいいように考えます。
しかし共依存夫婦の場合は、どれだけ不倫されていても相手から離れられないのが特徴です。気持ちの奥では苦々しく思いながらも相手を許してしまう傾向が。相手との関係に依存してしまっているため、不倫があった場合でも冷静な判断ができなくなります。
不倫がバレたらどうなるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「不倫がバレたらどうなる?トラブルを防ぐ対処法や慰謝料の相場・変動する要素を解説」
お酒や薬物に依存しやすい
夫婦の一方が薬物やアルコール依存症になったとしても、なかなか離れられないのが共依存夫婦の特徴です。とくに共依存夫婦の場合は、強い不安感やストレスによって、薬物やアルコールに依存する傾向があります。それにプラスして相手の依存症問題に対しても、手を差し伸べようとする傾向があります。
依存症までにならない場合でも、お酒を飲むと暴力を振るう、子どもに手を出すといった問題が生じます。共依存がきっかけで他の依存症になりやすく、共依存があるために依存症治療がうまくいかないといった悪循環に陥りがちです。
共依存関係から抜け出す方法
「夫との関係は共依存かも」「妻との共依存関係から抜け出したい」と思ったときには、次のような方法を取りましょう。
共依存状態だと自覚する
共依存関係から抜け出すには、共依存状態だと自覚することから始めましょう。自分だけでなく、相手にも自覚させる必要があります。そのためには自分と相手との関係性を客観的に見つめたり、それぞれの生い立ちを振りかえるのが有効。まずは共依存とはどのような状態なのか、知ることから始めましょう。
自己肯定感を取り戻す
共依存から抜け出すには、自己肯定感を取り戻す作業が必要です。とくに共依存的な関係においては、自分の価値を見失いやすく、日常的に「自分なんて」と否定的な思考に陥りがちだからです。このような思考をやめるには、まずは自分自身をいたわり、小さな成功体験を積み重ねていきましょう。
例えば新しい習い事を始めたり、自分だけの趣味を見つけるなど、自分のための時間を確保しましょう。また「自分には価値がある」と繰り返して自己肯定する自己暗示も効果的。健康的な食生活や規則正しい生活、適度な運動を取り入れて心身の調子を整えることも大切です。
相手の嫌な部分を認める
相手の嫌な部分を認めるのも、共依存関係から抜け出すポイントです。共依存夫婦になると、相手の嫌な部分が見えなくなることがあります。客観的に見ると相手に問題があるのに、「私が悪い」「自分のせいだ」などと思い込み、相手の嫌な部分や悪い点に気が付かなくなります。
しかし完璧な人間などいません。自分に悪い点があるのと同じように、相手にも悪いところがあって当然です。自分だけで気が付けないときには、信頼できる家族や共通の友人などに現状を打ち明けて、客観的な意見をもらうのも有効です。
夫婦で話し合う
夫婦の一方が共依存関係に疲弊し、その関係維持ができない状況になったときには、夫婦で話し合う必要があります。夫婦間で生じた考え方のズレを修正し、新たに円満な夫婦関係を維持できるように再構築してくべきでしょう。そして今後の夫婦の在り方について時間をかけて話し合うことで、共依存状態から抜け出せる可能性があります。
経済的に自立する
経済的に相手に依存している方は、経済的に自立することから始めましょう。経済的な自立とは、自分の意思を持ち自分だけで生活できるだけの収入を得られることをいいます。今まで専業主婦だった方は、アルバイトやパートから働いてみるのもいいでしょう。
経済的dvの仕返しがしたいという方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「経済的dvの仕返しがしたい…dvに当たる行為と離婚を含む具体的な仕返し方法とは」
精神的に自立する
共依存関係から抜け出すには、精神的に自立するのも大切です。精神的な自立とは、判断に迷ったときに他人に頼らずに自分だけの考えや意思で決定すること。とはいえ相手のことを何も考えずに自分勝手に振舞っている状況は、精神的自立とはいえません。他者の気持ちや考えを理解したうえで、自分の考えや意思に基づいて決定するということです。
具体的には次のような方法で、周囲の意見や考えを受け入れつつ、自分の考えを持つ練習をはじめてみてください。
- 1人で行動してみる
- 新聞や本を読む
- 一人でできる趣味を持つ
- 自分の目標や決断を意識する
- 短期・中期・長期の目標を立てる
支援グループに参加する
共依存関係の解消には、支援グループへの参加が有効です。共依存から抜け出す道のりは決して容易ではなく、専門家や同じ悩みを抱えている人と問題を共有することで、孤立感をなくし自分の気持ちを正直に言える場が持てるようになります。
支援グループでは、DVやモラハラに対する具体的な対策、自分の心の整理方法などについて話し合いができます。共依存症者向けの自助グループには「CoDA(コーダ Co-DEPENDENTS ANONYMOUS)」という組織があります。全国各地でミーティングが行われています。
カウンセリングを受ける
共依存夫婦から脱却するために、カウンセリングを受けるのもおすすめです。カウンセリングでは幼少期の経験やトラウマ、それによって歪んだ認知といった共依存を生み出した原因と向き合い、自分自身をどう変えていくかのアドバイスが受けられます。
とくに共依存関係では、いくつかのステップを経て脱却する必要があります。強い共依存となっている状態から抜け出すには、自分一人だけの努力では不可能です。専門的な知識を持つカウンセラーのサポートを受けながら、精神的安定を図ったうえで共依存関係から抜け出していきましょう。
別居する
共依存関係から本当に抜け出したいと思ったら、別居することも検討してください。共依存夫婦が一緒に生活を続ける中で共依存状態から抜け出すのは大変難しいため。相手と物理的に距離を置いて、もう一度夫婦の関係を見直してみる必要があるでしょう。
相手の入院など、やむを得ず離れ離れになったことで、共依存関係にあったことに気が付いたという人も少なくありません。別居をきっかけとして、夫婦関係に限定されないそれぞれの新しい世界を作りだせる可能性も。別居するときには、別居後の生活や子どものことなどを考える必要があります。
連れ去り別居は違法か知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「連れ去り別居は違法?合法?親権獲得への影響と子どもを連れ去られたときの対処法とは」
離婚が最適な場合も
今の夫婦関係が自分や子どもの人生の妨げになっていると感じたら、離婚を視野に入れる必要があるかもしれません。とくにDVやモラハラ、子どもへの虐待がある家庭では、子どもへの直接的な影響だけではなく、人格形成にも重大な影響を及ぼす可能性が。なるべく早めに別居に踏み切りましょう。
とはいえ離婚はとても簡単にできるものではありません。共依存関係に陥っているとなればなおさらです。自分だけでは離婚にまでこぎつけるのは難しいでしょう。そこで離婚問題に強い弁護士に相談するのがおすすめです。本当に離婚すべきなのかや適切な離婚条件、相手との交渉などを任せられます。
とくに夫婦問題に詳しい弁護士なら、離婚だけでなく夫婦関係の立て直し方にも詳しいでしょう。離婚すべきかどうか迷っているときには、なるべく早めに弁護士に相談しましょう。
まとめ
共依存夫婦とは、互いに「自分は相手がいなければ生きていけない」「相手も自分と同じように思っているはず」と思い依存しあっている夫婦のこと。経済的依存や他の依存症、過去の成育歴や心の傷が原因で、自己肯定感が極端に低いのが根底にあります。
支配と服従の関係ができやすく、子どもへの過干渉やネグレクトといった影響も。DVやモラハラ、アルコールや薬物への依存になりやすく、精神的・肉体的に疲弊しがちです。一方で借金や不倫など様々な問題があっても、離婚に踏み切りにくいという特徴もあります。
共依存関係から抜け出すには、自己肯定感を取り戻す作業や相手の嫌な部分を認める努力が必要です。またカウンセラーへの相談や自助グループへの参加も有効。物理的に別居や離婚を検討するときには、弁護士に相談したうえで、その後の生活のためのアドバイスを受けましょう。