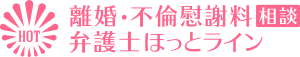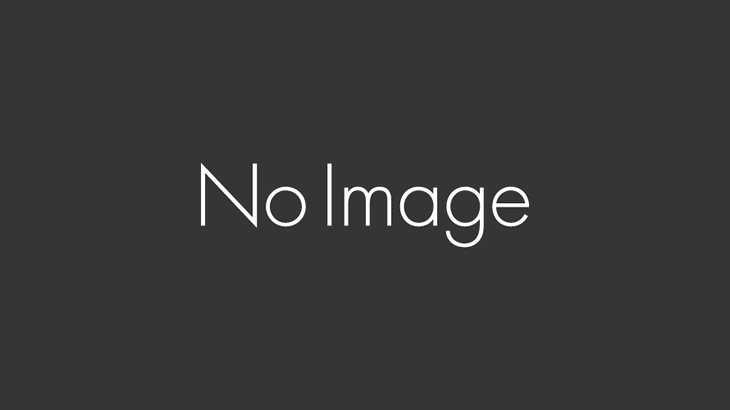- 「離婚について子どもへの伝え方が知りたい」
- 「親の離婚が子供に与える影響は?」
今の日本ではおよそ3組に1組の夫婦が離婚しているとはいえ、子供にとって親の離婚は人生に一度きりの重大な出来事です。子供に少なくない影響があることは、想像に難くありません。では親として、子供にどのように離婚の事実を伝えていけば、悪影響を最小限にできるのでしょうか?
こちらの記事では、子供のメンタルに配慮した離婚の伝え方を詳しく解説。さらに離婚を伝えるときのポイントも紹介するので、子供への伝え方の参考にしましょう。
親の離婚が子供に与える悪影響
親の離婚は子供に様々な影響を与えます。まずは生活が変わることでの生活面への影響です。そして子供自身の将来への影響もあります。さらには離婚前後で経験した様々な出来事によって、子供の心理面への影響も少なくありません。こちらでは親の離婚が子供に与える影響について、詳しく解説していきます。
離婚後の生活になじめずに不安定になる
親の離婚によって離婚後の生活になじめずに、子供自身が不安定になることが考えられます。親権を持った多くの親は、離婚後の生活のために働く時間を増やします。当然のように子供と過ごす時間は減ってしまいます。それにより、子供とのすれ違いが生じるようになったケースも少なくありません。
結果として子供が精神的に不安定になることも考えられます。また同居親との二人きりの生活になじめないという子供もいるでしょう。離婚後の生活の変化や親との関係によっては、親の離婚でストレスなどマイナスの影響が出る可能性があります。
離婚による情緒不安定
親の離婚によって仲の悪い親の姿を見ずに済むメリットがある一方で、親の離婚で情緒不安定になる子供もいます。親の離婚というのは子供にとって、自分が育った家庭が壊れることを意味します。家庭の崩壊による喪失感は深く、自分の家庭を否定するようになる子供も。
また親に見捨てられるのではないかという不安感も生じます。子供は別居親に対しては自分が見捨てられたと感じる一方で、同居親に対しても別居親のときのように自分も見捨てられるのではないかという不安感を持ちます。このようなことから、親の離婚によって子供が情緒不安定になることも十分に考えられます。
片親が離れることへの孤独感
親の離婚によって、片方の親と離れることへの孤独感も感じるようになります。とくに愛着関係を築いてきた親と離れ離れになるケースでは、子供は淋しさや孤独感を感じるでしょう。このような孤独感や喪失感は子どもの中でずっと残り続け、将来的な人間関係にも影響を与えます。
離婚後の両親とのかかわり方に悩む
離婚後の両親とのかかわり方に悩んでしまう子供もいます。子供にとって離婚していても、自分の親であることに変わりはありません。しかし離婚によって両親が別々の人生を歩むことになるため、子供が親とのかかわり方で悩んだり関係性に遠慮が生まれる可能性が。
例えば離婚後母親と一緒に暮らしていて、定期的に父親と面会交流をしていたとします。やがて父親は再婚して、別の女性と暮らし始めます。父親が再婚したとしても、親子であることに変わりはありません。しかしながら父親に別の家庭ができたことで子供の中に遠慮が生じ、どのように付き合っていったらいいか分からなくなることも。
父親との関係に戸惑い、悩みやストレスを抱える子供もいるでしょう。子供が父親との付き合い方に悩んだ結果、父子の間に溝が生じるケースもあります。
進学などの夢を諦めなければならなくなる
離婚後の経済状況によっては、子供の大学進学や留学などの夢を諦めなければならないデメリットも生じます。親権を持つ親が負担できる教育費には限界があり、仮に養育費をもらっていたとしても夫婦そろっていたときよりも世帯収入が低くなっているケースが多いです。
そのため私立の高校に進学を予定していたり、医学部などのお金がかかる学部を目指していた場合などは、教育費の問題で子供の進学の夢が叶わなくなる可能性も。奨学金などを利用するにも限界があり、子供にとっても非常に辛い状況になるでしょう。
物や人への愛着を失う
両親の離婚により、物や人への愛着を失う場合もあります。子供は日常生活で両親や兄弟姉妹、ペットなどに様々な形の愛着を持って成長します。しかし両親の離婚によって愛着に変化が生じると、子供の愛着関係の形成に影響して愛着障害を生じるケースも。
愛着障害は子供の頃に親との間で、愛着がうまく芽生えないことが原因で起きます。極端に人を恐れたり、人との距離感を保つのが苦手になったりします。また怒りのコントロールが苦手だったり、柔軟に対応しにくいという特徴も。これらは愛着障害によって自己評価が極端に低くなったり、自己防衛力が強くなることが原因です。
恋愛や結婚にマイナスイメージを抱く
親の離婚によって、子供自身が恋愛や結婚にマイナスイメージを抱く可能性があります。子供がカップルや夫婦を思い描くときに参考にするのは、最も身近な両親の姿です。その両親の離婚によって、カップル(夫婦)間の愛情を信じにくくしてしまいます。
結果として成長して恋人ができても「どうせすぐに嫌いになるに違いない」と疑心暗鬼になり、自分への愛情を過剰に試したり、自暴自棄な行動を取ったりします。また親の離婚が波乱に満ちたものであった場合には「結婚しても離婚が待っているだけだ」と結婚をはじめとする男女関係全般に冷めた視点になる人もいるでしょう。
実際に離婚した親を持つ子供が結婚した場合、離婚していない親を持つ子供に比べて離婚率が3倍になることが分かっています。夫婦間で問題解決するためのコミュニケーション方法や夫婦関係を維持するためのソーシャルスキル(社会技能)が得られにくいからと考えられます。
何かしらの依存症になる可能性
親の離婚によって強い孤独感や淋しさを抱いた子供は、成長すると何かしらの依存症になる確率が高くなります。イギリスの大学の研究者によると、死別や離婚などによって親との別れを経験した子供は、そうでない子供に比べて11歳までに喫煙する割合が2倍以上、飲酒では46%高いという結果が出ました。
幼少期における生活習慣の形成は、成人後の健康状態に大きく影響します。アルコール依存や煙草依存、薬物依存などに陥るケースが少なくありません。また幼いころ自分は愛されなかったという事実が重なり、セックス依存症に陥るケースも。このように親の離婚は、子供を依存症にするリスクをはらんでいます。
参考:11歳までの子どもの喫煙、親と別れたケースで倍増 英調査|CNN
精神疾患を抱えるようになる
親の離婚には、子供が精神疾患を抱えるリスクがあります。離婚による急激な変化から、子供の情緒にマイナスの影響を与えたり強いストレスを受けた結果、明るかった子どもが自分の殻に閉じこもるようになったり、優しかった子どもが急に攻撃的になるケースが見られます。
多くの場合は、離婚後2年目になると徐々に落ち着きを取り戻すものの、様々な悪条件が重なってしまうと一時的な変化にとどまらず、10年、20年と長期化する場合があります。このように精神的な問題を抱えたまま大人になるケースは少なくありません。精神科を受診した子供を対象にした調査によると、親が離婚した子供はそうでない子供に比べて受診率が2倍というデータがあります。
参考:離婚の子どもに与える影響 事例分析を通して|京都女子大学現代社会研究
短命になる
親の離婚が原因で依存症になったり精神疾患を抱えた子どもは、老化現象が人よりも早く現れる場合があります。成長の過程で心の傷が回復できればいいのですが、そうでないと短命になる可能性も。
アメリカの小児科学雑誌に掲載された研究によると、離婚などによる父親の喪失経験が、テロメリアという細胞の増殖に影響を与えることが分かりました。テロメリアは成長に必要な細胞で、親の離婚によってテロメリアの劣化が早まり平均よりも寿命が短くなるという結果に。このような研究からも、親の離婚が子供に悪影響を与えることが分かります。
参考:ストレスは遺伝子を変える|CHILD RESEARCH NET
子供のメンタルに配慮した離婚の伝え方
子供の年齢にかかわらず、親の離婚は子供に影響を与えます。とはいえ離婚をしないままで両親がいがみ合っている状況も、子供にとってはよくありません。そこで子供のメンタルに配慮した離婚の伝え方が重要に。こちらでは、子供のメンタルケアに焦点を当てて、離婚の伝え方について解説していきます。
年齢によって伝え方・ケアの方法を工夫する
子供の年齢によって、伝え方を変えるのは重要です。伝え方を間違ってしまうと、かえって子供を傷つけてしまう恐れがあるため。こちらでは、子供の年齢ごとの伝え方やケアの方法を紹介いたします。
乳幼児の場合
乳幼児の場合は、親の離婚というものを理解できません。別居親についても、記憶として覚えていないくらいの時期です。そのため具体的な言葉はなくても構いませんが、いつもより積極的にスキンシップを取る、一緒に過ごす時間を増やすなどして、子供の心の安定に欠かせないおやとの「絆」や「愛着関係」を作る努力をしましょう。
言葉を話せない乳幼児であっても、感覚的に物事を受け止めているので、周囲の緊張や母親の不安定さが伝わります。子供の前では極力いつも通りに過ごし、十分な愛情をかけるようにしてください。もう少し大きくなったら離婚のことを伝えるにしろ、この時期は子供が落ち着いて過ごせるよう、十分に目をかけるようにしましょう。
就園児の場合
幼稚園や保育園に通うようになった年齢の子供には、言葉を話せなくても親が言っていることを理解できています。「どうせ離婚のことは分からないから」と決めつけず、しっかりと向き合うことが大切です。離婚という言葉を理解できなくても「パパとママは別々に暮らす方がいいと思ったから、これから別々に暮らすことにしたよ」という言葉で、親が別居するということを伝えるようにしましょう。
このとき「どっちと暮らしたい?」という質問をして、子供に選ばせるようなことをしてはいけません。またこの時期の子供は社会性を身に着ける時期でもあるため「どうして自分にはパパがいないの?」と聞いてくることもあります。ここでその場しのぎの嘘をついてしまうと、子供を余計に傷つけてしまいます。子供への伝え方は十分に注意しましょう。
小学生の場合
目安ですが小学校1年生くらいになると、結婚や離婚について理解できるようになってきます。離婚を理解できるほどの年齢になった子供に対しては、離婚するということをしっかりと伝えるようにしましょう。同時に離婚する理由についても、極力事実を伝えるべきでしょう。離婚理由について別の言い方をした場合には、正直に話すタイミングを考えてください。
もしも子供の不安を感じたときには、一度立ち止まって子どもと向き合い、愛情をかけて精神的なサポートに徹してください。「どうして離婚しなきゃいけないの?」「一緒にいたい」と言われるかもしれず、子供が離婚について受け止めるのに時間がかかるかもしれません。このようなときには、両親が決めた決断だということを丁寧に説明しましょう。
中学生の場合
中学生になるとなぜ両親が離婚しなければならないのか、離婚の事実を冷静に受け止められるようになります。しかし成長している分だけ、内面を正直に見せてくれない子供もいます。このような子供には配慮が必要です。一方で親に反発したり、離婚を期に引きこもりや不登校になる子供も。
中学生の子供の場合は、子供の話をしっかり聞くことが重要。親の離婚だけでなく、学校生活で抱えている不安や悩みを誰にも相談できずに苦しんでいる子供も少なくありません。子供が孤独感や疎外感を感じないよう、子供の意見を尊重しながら、親子で話し合う機会を出来るだけ持つようにしましょう。
子供によっては、学校や習い事の関係から住む場所について明確な希望を持っている可能性も。子供の意見を聞いて、できるだけ今まで通りの活動ができるような環境を整えることも大切です。
高校生の場合
子供が高校生になると、子供自身の性格によってその後の状況が変わってきます。精神的に成熟した子供の場合は、親の離婚を受け入れられる場合があります。また友人に相談することで、精神的不安や悲しみを昇華できる子供も。その一方でどこにも不安や悲しみの気持ちをぶつけられない子供も少なくありません。
高校生の子供に対しては、心のゆとりや余裕を与え、選択肢の多い人生があることを教える必要が。子供にはできる限り将来への可能性を閉ざさない方向で、進学など離婚後の進路の話し合いをしてください。経済的に無理な場合には、本人が納得できるようにきちんと話し合いの場を持つことが大切。ときには別居親に追加で養育費の負担ができないか頼んでみてください。
タイミングに配慮する
に配慮してください。具体的には卒業や入学など、環境の変化があるときが望ましいでしょう。住所や名字が変わることの影響を最小限に抑えられるタイミングです。
逆に悪いタイミングなのは、子供の人生にとって重要な時期。部活の大会を控えている時期や受験時期は、子供に余計な心の負担をかけるべきではありません。やむを得ないときには、離婚以外の別居に見せかけるような工夫をしてください。
そして子供に伝えるタイミングは、子供と両親の双方がリラックスしている状態で、子供が離婚の事実を受け止められる状態のときにしましょう。
配偶者に離婚を切り出すのに適したタイミングについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚を切り出すのに適したタイミングは?切り出す前の注意点とケース別対処法」
離婚を決めていない段階で伝える
場合によっては、離婚を決めていない段階で徐々に離婚になるかもしれないということを伝える方法があります。離婚を決意するまでには、不仲なときや献花、別居など様々な過程があります。そのような過程で、将来離婚になるかもしれないということと、離婚したとしても子供への愛情は変わらないということを少しずつ伝えるようにしましょう。
離婚に踏み切るきっかけについて知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「離婚に踏み切るきっかけとは?統計からみる理由と決め手、後悔しないためのチェックポイントを解説」
なるべく嘘はつかない
子供に離婚について伝えるときには、なるべく嘘をつかないようにしてください。離婚について理解できない年齢の子どもには、別々に暮らすことだけを話すのも一つの方法です。「もう少し大きくなったら話すね」などと伝え、子供が離婚の事実を受け入れられるようになったタイミングで伝えるのもいいでしょう。
受験など子供にとって重要な時期に重なってしまったときには、ストレスを与えないように離婚について隠す人もいるでしょう。このような状況では、(元)配偶者が子供に言ってしまわないように口裏を合わせる必要があります。
離婚の理由もなるべく正直に伝えた方がいいのですが、どうしても理由をいえないときには「お父さんのことが好きじゃなくなったので結婚をやめたの」や「いつも喧嘩ばっかりだったから一緒にいるのが楽しくなくなった」など、嘘をつくのではなく子供に理解できる言葉で、できるだけショックが少なくなるようにあなたの気持ちを伝えてください。
離婚しても親であることに変わりがないと伝える
子供には、「離婚してもあなたの親であることには変わりない」ということをしっかりと伝えましょう。離婚はあくまでも夫婦関係を解消することで、子供の親をやめるということではありません。離婚して別々に暮らすことになったとしても、親として子どもを大切に思っており、子供の親であることに変わりがないという点をしっかりと伝えてください。
中には「離婚すると片方の親に会えなくなるのでは?」と不安になる子供もいます。そのような子供には、面会交流権というものがあって、一緒に暮らせないが別居親と会えない訳でないことを伝えてあげてください。
離婚の原因は子どもではないと伝える
子供の中には、両親が離婚するのは自分のせいなのでは?と考える子供がいます。「僕がいうことを聞かなかったからお父さんが出ていっちゃうの?」「私が約束を破ったからママに嫌われたの?」などと、自分のせいにしてしまう子供が少なくありません。
子供は世界の中心に自分がいるという認識をしやすいので、全てを自分の責任にしがちです。また理解できない事柄に対しては、自分自身の中に原因を作ってしまうので注意が必要です。親の何気ない「あなたのために離婚することにしたのよ」という言葉をそのまま受け止めて「自分のせいで離婚になった」と考える子供も。このようなことは絶対に子供に言わないようにしましょう。
子供に離婚を伝えるときには、「離婚は親の都合である」ということと「離婚の責任は子供にはない」ということを子供に分かるよう丁寧に何度も伝えてください。
「子供のために離婚しない」は本当か?という点については、こちらの記事を参考にしましょう。
「『子どものために離婚しない』は本当?離婚の判断基準や子どもの本音を知って後悔しない生き方を」
配偶者の悪口は言わない
子供に離婚を伝えるときには、配偶者の悪口は絶対に言わないようにしてください。夫婦にとって配偶者は離婚すれば他人になる存在ですが、子供にとっての親というのは単なる好きな人や信頼できる人以上の存在だからです。自分を形作っているいわば、自分の分身のような存在として親を見ています。
その親の悪口を聞くと、子供はひどく傷つきます。子供の年齢によっては、悪口をいう親に対して悪感情を抱く可能性も。たとえ不倫やDVなど相手が原因で離婚する場合であっても、子供の心を尊重し、離婚前はもちろんのこと離婚後も子供の前で配偶者の悪口をいうのは控えてください。
子供に決断を迫らない
子供に両親の離婚を伝えるときには、子供自身に決断を迫ってはいけません。これは親権問題で争いのある夫婦でよくあるのですが、子ども本人に「離婚したらどっちと暮らしたい?」と詰め寄る親がいます。子供自身が即決できればいいのですが、そうでない場合にはどちらも選べずに子供の心に心配や淋しさを増やしてしまうでしょう。無理にどちらかを選んだ場合には、罪悪感を抱く子どもも。
子供のことがかわいいと思うのであれば、絶対に子供に決断を迫るべきではありません。子供自身が選んだことと言い訳をして、自分の希望を通そうとしている親のエゴでしかありません。
親の離婚について子どもの気持ちを聞く
離婚することを子供に伝えた後は、子供自身の気持ちを聞いてしっかりと受け止めてあげてください。親の離婚は親自身が決めるのは当然のこと。しかし親の離婚は、子供の人生にも大きな影響を与えます。親に対して思っていることや離婚について子供が感じることもあるでしょう。
そのような子供の気持ちを聞く機会を作らなければ、子供は一生その気持ちを昇華できないまま生きることになります。親の言い分だけを押し付けず、子供の気持ちにも配慮する姿勢が大切です。子供の声をおざなりにせずきちんと気持ちに耳を傾け、親としてできることを真剣に考えていけば、離婚は親も成長する機会となるはずです。
絶対に見捨てないことを強調する
離婚の話し合いをした後は、絶対に子供を見捨てたりしないことを伝えてください。子供にとって両親の離婚で一番気になるのは「自分はこれからどうなってしまうのか」ということ。そのため子供はとにかく不安になります。
子供の不安を解消するには、「ずっと一緒にいるよ」など絶対に見捨てないことを伝え、子供の不安を取り除く言葉をかけるようにしましょう。
離婚後も別居親と会えることを伝える
別居親が子供との関係が良好だった場合、離婚により子供がふさぎ込む可能性があります。そのような子供には、面会交流をすることで、親子の絆が切れないことや離婚しても親子であることに変わりないことを伝えましょう。子供が希望すれば、いつでも親に会えると伝えてもいいでしょう。
離婚後も別居親と定期的に会えると知ることで、子供のマイナスの影響やストレスを軽減できる可能性があります。
2026年に導入が予定されている共同親権のメリットやデメリットについては、こちらの記事を参考にして下さい。
「共同親権のメリット・デメリット|民法改正による変更点と親権の決め方を徹底解説」
子供に離婚を伝えるときのポイント
子供に離婚の事実を伝えるときには、次のような点に気を付けましょう。
配偶者と子どもへの伝え方を相談する
子供に離婚を伝える前には、必ず伝え方や伝えるタイミングについて夫婦で話し合ってください。夫婦の不仲は多くの場合親の問題。子供はそれに巻き込まれるに過ぎません。離婚すると聞かされてもすぐに受け止められる子どもはごくわずかです。
一方的に離婚の話をするのではなく、子供の様子や状況を見ながら、どのように伝えたらいいのかを夫婦で相談してから伝えましょう。できれば両親が揃っているタイミングで伝えるのがベストです。
スキンシップ・愛情を示しながら伝える
離婚のことを伝えて冷静さを失っている子供には、抱きしめたりスキンシップをしながら愛情を示してください。ハグをしながら「離婚してもパパとママはあなたのことをずっと大好きだからね」「離れて暮らすけれども、あなたが合いたいときには会えるようにするからね」などと伝えるようにして下さい。
そのときは落ち着きを取り戻しても、寝る前など何かのきっかけで再び感情が揺れて泣き出す子供もいます。この場合も、その都度子供が落ち着くまで抱きしめてあげるのがいいでしょう。大人でもスキンシップで安心を取り戻せることがあります。もう小さい子どもではないのだからと思わずに、中学生でも高校生でもスキンシップをしてあげてください。
別居するときも配慮が必要
離婚前に別居する場合も、子供への配慮が必要です。子供は別居親が寂しい想いをしているのではないかと、優しい感情を持つことも多いです。別居親はその点にも配慮して、一緒に暮らせなくて寂しい、辛いという感情は子供に見せない方がいいでしょう。とはいえ寂しいのは事実なので、なるべく子供と交流する時間を取るようにしましょう。
連れ去り別居が親権獲得に与える影響については、こちらの記事を参考にしましょう。
「連れ去り別居は違法?合法?親権獲得への影響と子どもを連れ去られたときの対処法とは」
離婚原因はケースバイケースで説明する
離婚原因については、ケースバイケースで時期を見ながら説明するのがいいでしょう。離婚を子供に伝えるとき、離婚原因をどの程度説明すべきか悩む人は多いです。離婚原因が何だったのかや子供の年齢によって、どの程度伝えるかはケースバイケースで考えてください。
初めて離婚を伝えたときには、大まかに説明するにとどめ、子供が新生活になじんだタイミングや成長したタイミングで詳しく説明するという方法もあります。いずれの場合でも子供が質問したときには誠実な対応を心がけてください。
「離婚について聞くのはタブーだ」と感じると、離婚そのものが理解できないものになり、自分のせいではないのか、別居親に捨てられたのではないかという想いが子供の心の中にくすぶってしまう可能性があります。
離婚で変わることは早めに伝える
子供に離婚を伝えた後には、離婚で変わることは早めに伝えるようにしましょう。子供は精神的にも経済的にも親から自立していません。とはいえ離婚に伴う様々なことについて、直前に伝えられただけでは親に振り回されてしまうでしょう。それでは親への不信感につながるだけでなく、子供の無力感にも影響します。
住む場所や学校、名字など子供に関係のある離婚後の変更点については、先のことでも決定した時点で子供に伝えるようにしてください。子どもなりに心の整理をしたり、準備する期間を設けられます。常に「自分が子供だったらどうして欲しいか」を考えて、子供と接するようにしましょう。
離婚後の子どもの戸籍や名字については、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚後の戸籍はどうなる?チャート式選択肢と子どもの戸籍・名字について徹底解説」
聞き分けがいいことを良しとしない
親の離婚を子どもに伝えたときに、逆に心配になるのは聞き分けが良すぎる場合です。一度心に蓋をしてしまうと、この先もずっと本心をいえない子供になってしまう恐れがあります。聞き分けがいいことを良しとせず、離婚後の生活が落ち着いた頃にでも、再度子どもと向き合って、子供が感じている不安や恐れといった感情をしっかりと受け止めてください。
子供にとっては子供らしくいられる環境が何よりも大切。親として子供らしくいられる環境づくりに注力することが大切になります。
スムーズに離婚するには専門家に相談
離婚時には子供の親権や養育費、面会交流など子供に関して決めなければならないことがたくさんあります。それ以外にも財産分与や慰謝料請求なども、離婚時には決める必要があります。しかし一方で、離婚を決意するほど関係がこじれた相手と冷静な話し合いをするのは、当然のことながらとても難しく、話が進まないこともあるでしょう。
そのようなときに頼りにしたいのが、法律の専門家である弁護士です。弁護士に依頼すると聞くと、大げさではないかと感じる方がいるかもしれませんが、当事者同士で冷静な話し合いができない場合には、離婚にまつわるトラブル解決のプロで交渉のプロである弁護士に任せた方が、ご自身にとっても子供にとってもベストな解決法です。
多くの弁護士事務所では、初回無料の法律相談を実施しています。自分の聞きたいことをある程度まとめた上で、初回相談を利用して弁護士に相談してください。信頼できる弁護士を見つけられれば、より少ないストレスでスピーディーに離婚できるでしょう。
離婚時の弁護士費用について知りたい方は、こちらの記事を参考にして下さい。
「離婚時の弁護士費用を徹底解剖!費用をおさえるコツや注意点を紹介」
まとめ
子供にとって両親の離婚は、心理面や経済面だけでなく、将来への不安や成長後のトラブルにつながります。家族にとってベストな選択が離婚しかないのであれば、子供の精神面に配慮しストレスを最小限にできる方法を考え、子供が安心して子供らしく暮らせる生活を作ってあげるべきでしょう。
子供に両親の離婚について伝えるときには、子供の年齢に応じた伝え方やケアの仕方を実践してください。伝えるタイミングに配慮し、スキンシップを取りながら伝えるのも有効。なるべく嘘はつかずに、離婚の原因は子供でないことを伝えるようにしましょう。
子供に伝える前には夫婦で話し合って、伝え方やタイミングを共有しましょう。なるべく夫婦そろって伝えるのがベストです。離婚時には子供のことやお金のことなど、決めなければならない事柄がたくさんあります。子供のためにも離婚後の生活にスムーズに移行するには、離婚問題に詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。