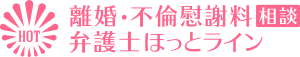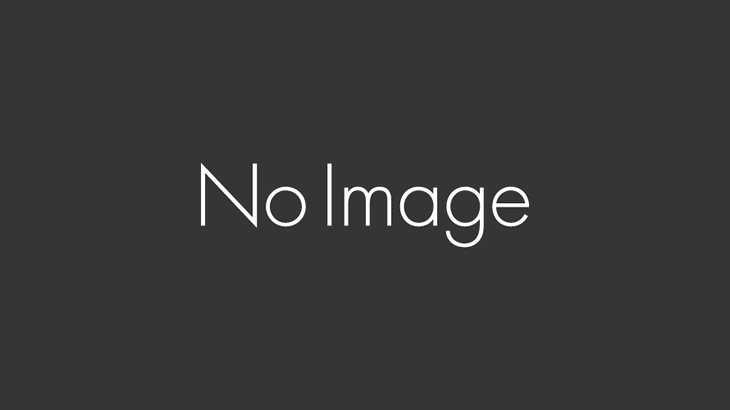- 「宗教観の違いで夫婦喧嘩が絶えない…離婚できる?」
- 「宗教観の違いで離婚をしたいときのポイントが知りたい」
夫婦であっても宗教観をはじめとする価値観の違いがあるのは、ある意味当然のこと。しかし夫婦の一方またはその両方に熱心に信仰する宗教があるときには、それが夫婦不和の原因になることも少なくありません。そこでこちらの記事では、宗教観の違いで離婚ができるかについてや判断のポイント、離婚が認められたケースを、過去の判例をもとにして解説していきます。
実際に離婚をするときには、財産分与や子どもの親権といった離婚条件を決めなければなりません。慰謝料請求できるかという点と併せて、宗教観の違いで離婚するときの注意点も紹介していきます。
宗教観の違いによる離婚は可能?
宗教観の違いで夫婦関係が悪化すると、離婚を考えるようになります。ではこのような理由で離婚することはできるのでしょうか?
相手が合意すれば離婚できる
相手が合意すれば、問題なく離婚できます。日本では夫婦の話し合いのみで離婚できる「協議離婚」が認められています。理由が宗教観の違いであっても、極端にいうと理由が特になくても、双方の合意があれば役所に離婚届を提出し受理されれば、離婚が成立します。
また離婚調停になった場合でも、相手の合意があれば調停は成立となります。実際の離婚成立日は調停成立日となりますが、成立後10日以内に調停調書の謄本と離婚届を提出して離婚の成立を役所に報告します。
相手が拒否する場合は離婚裁判となる
相手が離婚を拒否する場合、離婚裁判に進む可能性があります。
離婚裁判では「法定離婚事由」が必要
離婚裁判では、民法第770条で定められている「法定離婚事由」が必要です。具体的には次のような内容です。
| 1.配偶者に不貞な行為があったとき | 配偶者以外の異性と性的関係を持ったとき |
| 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき | 働いているのに生活費を払わない、理由もなく無断で家を出ていった、不倫相手と生活するために家出したなど |
| 3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき | 3年以上行方不明で連絡が全く取れない、遭難して生死が分からないなど |
| 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき | 統合失調症や偏執病、認知症や失外套症候群などを発病し回復の見込みがないとき |
| 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき | DV、モラハラ、セックスレス、性的異常、ギャンブルやアルコールなどの依存症、過度の浪費や借金、親族との不和、長期の別居、犯罪による服役、過度な宗教活動への傾倒など |
宗教を理由に離婚が認められないケース
宗教観の違いによって夫婦仲が悪化した場合でも、裁判で離婚が認められない可能性があります。というのも宗教や信教の自由は、日本国憲法第20条で定められている権利です。個人において尊重されるのはもちろん、夫婦間であっても尊重されるべきと考えます。
そのため「妻が信仰している宗教が気に食わない」「特定の宗教を信仰していることが気持ち悪い」といった理由があっても、信仰の内容が一般的な範疇にとどまる場合には、離婚裁判で宗教を理由とした離婚が認められない可能性が高いでしょう。
宗教を理由に離婚が認められるケース
一方で、宗教を理由に離婚が認められる場合があります。民法第770条や民法第90条の解釈によって、「社会的な相当性」や「公の秩序又は善良な風俗」が損なわれていると判断されたときには、これを理由として離婚が認められる可能性があります。具体的には次のような場合です。
配偶者以外の異性と性交渉を行った
宗教活動の一環であっても、配偶者以外の異性と性交渉を行った場合、法定離婚事由の一番目「不貞な行為」に該当します。不貞行為は法律に違反する不法行為でもあるため、離婚時に慰謝料請求が可能です。裁判で離婚や慰謝料を請求する場合には、不貞行為があったと認められるような法的に有効な証拠が必要です。
不貞行為がどこからか知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「『不貞行為』はどこからの行為?不倫・浮気との違いや当てはまるケース、法的に有効な証拠を解説!」
悪意の遺棄があるとき
宗教活動を理由に「悪意の遺棄」があった場合には、離婚裁判で離婚が認められない可能性があります。悪意の遺棄とは、夫婦間の同居・協力・扶助義務を正当な理由がなく履行しないこと。相手を害する意図がなくても、夫婦関係の破綻を容認するような行為があれば、悪意の遺棄があったとして離婚が認められるでしょう。
具体的には夫の収入で生活しているのに給料のほとんどを宗教活動やお布施につぎ込んでいるといったケースや、出家するといって勝手に家を出ていってしまったといった行為です。
悪意の遺棄で離婚が認められるケースについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「悪意の遺棄での離婚|認められる条件と必要な証拠、スムーズに離婚するためのポイントとは」
「婚姻を継続し難い重要な事由」があるとき
法定離婚事由の5番目「婚姻を継続し難い重要な事由」があると判断されたときにも、裁判上の離婚が認められます。どのようなケースで離婚が認められるかに関しては、夫婦間の事情や宗教に関する事情など個別の事情によって決まるため、一概に「このような場合」とはいえません。
しかしながら宗教観の違いや実際の宗教活動により一方が耐えられない場合や、夫婦関係が破綻したり家庭生活が崩壊するような事態に陥った場合には、婚姻を継続し難い重要な事由があるとして、裁判で離婚が認められる可能性があります。
実際の裁判において宗教が原因で離婚が認められた事例では、次の3つのパターンがあります。
政治観の違いで離婚をお考えの方は、こちらの記事を参考にしてください。
「政治観の違いで離婚したい…価値観の違いによる離婚の可否と離婚を回避する7の方法」
宗教観の不一致
こちらの判例では、夫婦間の決定的な宗教観の違いによって、双方の離婚調停を認めています。異なる宗教を信仰している男女が結婚したのですが、互いの信仰が異なることから夫婦の対立が激化し、夫と妻それぞれから離婚の請求と慰謝料の請求がなされました。
こちらのケースでは夫が自分の宗教心を隠して結婚したことから、妻に対して100万円の慰謝料支払い義務が認められました。
参考:東京高裁昭58.9.20判決|判例タイムズアーカイブス
祭祀の拒否
宗教が理由になり離婚が認められた事例の二つ目は、祭祀の拒否をしたケースです。結婚後妻が新興宗教に入信、その後妻は仏事等の先祖への祭祀を行わなくなったことから、夫婦間で深刻な対立が発生。それでも妻は宗教活動を控えようとしなかったことから長期に及ぶ別居となりました。
夫は妻に対して「婚姻関係が破綻している」として離婚を請求。妻が夫婦関係を修復するために宗教活動を控えようとしない姿勢や、同居を再開しても子どもの養育や日常生活に支障が生じかねないこと、これらを夫が容認できずに離婚の意思が固いことを理由として、離婚が認められました。
参考:名古屋地裁昭63.4.18判決|法令タイムズアーカイブス
子どもへの強要
子どもへの強要があった場合にも、宗教を理由とした離婚が認められる可能性があります。こちらのケースでは、結婚後に妻がある宗教に入信。布教活動を熱心に行う傍ら、仏式の祭祀や節句などの行事への参加を拒むようになりました。
そして次第に子どもに対しても入信している宗教の教義を教えたり、行事に参加させるように。このような妻の行動に対して、夫は強い不満を抱くようになりました。妻に信仰を止めるよう説得したものの、妻はこれを聞き入れず次第に夫婦関係が破綻していきました。
憲法では個人の信仰の自由が認められている一方で、夫婦としての同居協力扶助義務もあることから、宗教活動にも限界があるとみなされるのは当然。裁判所では妻の宗教活動が夫婦間の義務の限度を超える行為とみなし、婚姻関係の破綻を認めました。
周辺の事情も考慮される
宗教観の違いや宗教活動によって離婚が認められるかどうかは、周辺の事情も考慮されます。具体的には次のような内容です。
| 夫婦の状況について | 宗教活動について |
|---|---|
|
|
このような個別の事情に応じて、婚姻関係の破綻もしくは回復の可能性の有無が判断されます。
宗教観の違いで離婚するためのポイント
宗教観の違いで離婚するためには、次のような流れで行います。注意すべきポイントもあるので、参考にしましょう。
証拠を集める
裁判で離婚や慰謝料を請求するには、証拠を確保する必要があります。宗教は個人の自由なので、夫婦の信仰が違ってもそれだけで離婚の理由にはなりません。相手はこれを理由に離婚を拒否する可能性があります。
そこで相手がどれだけ宗教にハマっていて、家庭生活に影響が出ているかを証明する必要が。夫婦関係が悪化したのは、相手が宗教にのめり込んだためという明確な証拠を集めてください。たとえば仕事や家事を放棄して宗教活動にのめり込んでいる、子どもの学校を休ませて集会に参加させている、生活費を持ち出して宗教に寄付するなど、明らかに行き過ぎた宗教活動があったことを事実として証明してください。
宗教活動以外にDVがあるという方は、こちらの記事を参考にして証拠を確保しましょう。
「DVの証拠の残し方|離婚に有利になる10種類の証拠の取り方&証拠を集めるときの注意点とは」
日記やメモ
配偶者が頻繁に宗教の集まりや布教活動に行っているときには、その日時を日記やメモに記録しましょう。そこには家庭を顧みるように説得したことや宗教を控えるようにとの話し合いなど、家庭生活を取り戻すためにどのような行動をしたかも記しておきます。
また相手の言動が一般の常識では考えられないところがあれば、それも記録してください。日記はできれば毎日記録することで、日記の信用性がアップします。結婚生活を協力して行っていたかを判断する材料になるだけでなく、様々な努力をしても相手が変わらなかったことの証明にもなります。
録音・録画データ
配偶者が発した宗教に関する言動については、録音や録画データに記録しておきましょう。上記の日記やメモとあわせると、有力な証拠となります。他にも家事や育児を行わなかったことが分かる部屋の様子や、宗教にかかわる内容で夫婦喧嘩した音声なども証拠として残しておきます。
寄付の履歴
配偶者が宗教団体に寄付(会費・献金・賽銭・奉納金・お布施)をしている場合には、寄付の履歴も証拠となります。宗教団体に入金した履歴が分かる振込明細書や預金通帳、ネット銀行の取引履歴などを手に入れてください。またあなたに生活費を渡さずに宗教活動につぎ込んでいるときには、その日時や金額を記録したメモ、家計簿なども証拠として残しておきます。
また相手が通帳を管理しているときには、配偶者であるあなたが金融機関から入出金履歴を入手できる場合も。紙の通帳の場合は破棄される可能性がありますが、金融機関からは10年分の履歴が取れます。万が一通帳が手元になくても諦める必要はありません。
中には現金以外のキャッシュレス決済や不動産、有価証券などで寄付をしている可能性も。現金や預貯金が減っていないからと安心せず、夫婦の財産全てに目を光らせておきましょう。
別居を検討する
離婚を切り出しても相手が同意しないときには、別居を検討すべきでしょう。ケースバイケースですが、長期間の別居の事実がある場合には、夫婦関係が破綻して修復できないとみなされて裁判で離婚が認められる可能性があります。
具体的な期間は個別の事情によりますが、一般的に3年~5年の別居期間で離婚が認められる傾向があります。ただし別居するときには、必ず相手に断りを入れてからにしましょう。無断で別居してしまうと、あなたの方が「悪意の遺棄」とみなされる恐れがあるためです。
また離婚後に子どもの親権者を希望しているときには、必ず子どもを連れて別居してください。子どもを相手の元において出てしまうと、親権者の判断に不利になる可能性があります。
離婚したい人が別居前にすべきことについては、こちらの記事を参考にしてください。
「【離婚したい人向け】別居前にやること・準備マニュアル|知っておくべきポイント・注意点とは」
別居中の生活費について
別居中の生活費は、婚姻費用として収入の少ない側が多い側に請求できます。別居したとはいえ夫婦であることに変わりなく、夫婦は助け合って生活する義務があるからです。婚姻費用は請求した時点から支払い義務が発生します。そのため、別居したらすぐに婚姻費用を請求する手続きを始めるといいでしょう。
婚姻費用の金額は夫婦の収入や子どもの人数、年齢などによって相場が決まっています。実務では、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」をもとに算出されるので、婚姻費用をいくらもらえそうか事前に確認しましょう。
婚姻費用をもらい続ける方法が知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「婚姻費用をもらい続ける方法は?損しないための対抗策とよくある質問に答えます!」
慰謝料請求の可否
相手が離婚原因を作ったときには、離婚時に慰謝料請求できる場合があります。しかし慰謝料を請求するには相手の不法行為によって婚姻関係が破綻したことを証明する必要が。そのため単に配偶者が宗教活動にハマっていただけでは、慰謝料請求が認められないでしょう。
具体的には次のような行為があれば、慰謝料請求が認められる可能性があります。
- 生活費まで宗教への寄付に使ってしまう
- 同じ宗教に入信するようにしつこく迫ったり、暴言・暴力がある
- 自宅を宗教活動のために開放するなど、家族の生活を巻き込む
- 時間を問わず宗教活動にのめり込み、連絡なしに外泊したりする
- 学校などを休ませて子どもを宗教活動に連れ出す・強要する
慰謝料を増額するには、これらのことを確実に証明する証拠が必要です。離婚を切り出した後や別居した後では、これらの証拠が取れない可能性があるので、証拠を確保するためにはタイミングを考えるようにしましょう。
慰謝料請求を控えた方がいいケースについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「慰謝料請求しない方がいい? 控えた方がいい11のケースと【離婚理由別】取るべき対策とは」
財産分与について
離婚時には、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産は、基本的に1/2ずつ分けられます。これを財産分与といいます。財産分与の対象となるのは、同居を始めてから離婚(別居)するまでの間で築いた次のような共有財産です。
- 現金
- 預貯金
- 不動産
- 有価証券
- 不動産
- 年金
- 動産(貴金属・骨とう品・車・家具など)
財産分与で損をしないためには、事前にどのような財産があるかしっかりと調べるようにしましょう。共有財産から勝手に寄付やお布施をした場合には、それらの金額についても明確にしておく必要があります。
離婚時の財産分与で不動産をどうするかについては、こちらの記事を参考にしてください。
「離婚時の財産分与で不動産どうする?【ケース別】財産分与の方法と事前の確認ポイントとは」
子供の親権
未成熟の子どもがいる場合、離婚時に子どもの親権を父母のどちらが持つかを決めなければなりません。相手の宗教活動で離婚を決めた場合には、そのような相手に子どもの親権を渡したくないと考える人もいるでしょう。しかし残念ながら離婚の原因と親権を取れるかどうかは、全くの別問題です。
子どもの親権で一番にポイントになるのが「子の福祉」。どちらが親権を持つ方が子どもの幸せにつながるかということが、親権を判断する上で一番重要になります。具体的には次のような点が重視されます。
- 監護の意欲や実績
- 監護の継続性(これまで主として子どもの世話をしてきた側はどちらか)
- 離婚後の監護の環境
- 看護補助者の有無(子育てに協力してくれる人はいるか)
- 面会交流に許容的かどうか
- 子供自身の意思(15歳以上の子どもの場合は本人の意思が尊重される)
- きょうだい不分離の原則(きょうだいは離れ離れにさせず同じ親権者の元で暮らすべきという考え)
- 母子優先の原則(子どもの年齢が小さいほど母親が有利)
母親が宗教にハマっていたとしても、子どもへの虐待やネグレクトなどの事情が認められない限り、それだけで親権の判断に不利になることはありません。そのため父親が親権を獲得するためには、監護実績を作ること、相手が子どもを虐待・ネグレクトしていたという証拠の確保がポイントです。
男性が離婚を有利に進める方法については、こちらの記事を参考にしてください。
「男性が離婚を有利に進める方法|離婚方法・離婚条件別ポイントといざというときの対処法とは」
養育費
離婚後に子どもを引き取って養育する側には、他方から養育費を受け取れる可能性があります。養育費は子どもの生活や教育のために必要なお金。離婚後に子どもと幸せに暮らすためにも、養育費はきちんともらうようにしましょう。
養育費の金額は、婚姻費用と同様に裁判所の算定表で算出できます。できれば離婚前に、養育費に関する次のような内容を取り決めしておきましょう。
- 子ども1人あたりの養育費の金額(月額)
- 支払期間(支払い開始日と終了日 成人するまで・大学を卒業するまでなど)
- 支払時期(月末・年末払いなど)
- 支払方法(振込・手渡しなど)
- 特別費用について(私学への入学金・学費・習い事代・入院費・治療費など)
養育費の支払い期間についてや減額方法に関して詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。
「養育費は何歳まで支払う?支払期間の考え方や変更・減額方法を解説」
確実に貰うポイント
養育費を確実に受け取るには、事前の準備が必須です。養育費について取決めた内容については、合意書や離婚協議書にまとめるのはもちろんのこと、公的な信用性が高い公正証書で作成することをおすすめします。万が一不払いが発生したときのことを考えて、公正証書には「強制執行認諾文言」を入れておくといいでしょう。
強制執行認諾文言とは、公正証書に記載される条項で、相手が養育費を支払わなくなったときに裁判を経ずに強制執行が可能になるもの。通常給与や預貯金を差し押さえするには、裁判所の確定判決や仮執行宣言付判決といった「債権名義」が必要です。
強制執行認諾文言付き公正証書はこの債権名義に当たるため、法的手続きの必要なく強制執行ができます。
養育費を強制執行するメリット・デメリットについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「養育費を強制執行する・されるデメリットとは?強制執行の基礎知識とデメリット回避方法」
離婚問題に詳しい弁護士に相談
宗教観の違いや信仰を理由に離婚を検討しているときには、離婚問題に強い弁護士に相談してください。前出の通り日本では信教の自由が認められているので、信仰を理由に離婚を請求するには、専門的で高度な法律の知識が必要になるため。
どの程度の宗教活動なら離婚が認められるかは、個々のケースによって異なります。また婚姻関係の破綻を証明するためには、法的に有効な証拠が必要です。そのようなときでも弁護士なら、調停や裁判に向けた証拠集めの段階から、専門的なアドバイスができます。また宗教的な問題を専門とする支援団体やカウンセラーとの連携も可能です。
とくに宗教の問題がある家庭では、個人の意思が尊重されにくい傾向があります。そのような場合でも第三者の介入により解決に至る可能性も。また宗教にのめり込んでいる相手との離婚は、精神的負担が大きくなりがち。心理的サポートも期待できる弁護士への依頼が解決に向けた糸口となるでしょう。
まとめ
配偶者が信仰している宗教が理解できないといった宗教観の違いだけで離婚するには、相手の同意が必要です。相手の同意なく裁判で離婚が認められるためには、宗教問題の他に不貞行為や悪意の遺棄の有無がポイントに。他にも子どもへの強要や祭祀の拒否、信仰の違いによる夫婦関係の破綻によって離婚が認められる可能性があります。
宗教問題で離婚・慰謝料請求をするには、宗教によって修復の余地がないほど夫婦関係が悪化したという証拠が必要です。子どもの親権に関しては、離婚原因が問題にならないものの、虐待やネグレクト等があった場合には不利になります。財産分与や養育費の受け取りで不利にならないためには、離婚前の調査や準備が必須です。
宗教にのめり込んでいる相手との離婚は一筋縄ではいきません。また信教の自由が関係するため、離婚の判断も難しくなりがち。そのためなるべく早期の段階で、弁護士に相談することをおすすめします。まずは無料相談を利用して、安心して任せられる弁護士を探しましょう。