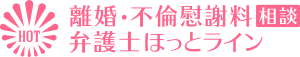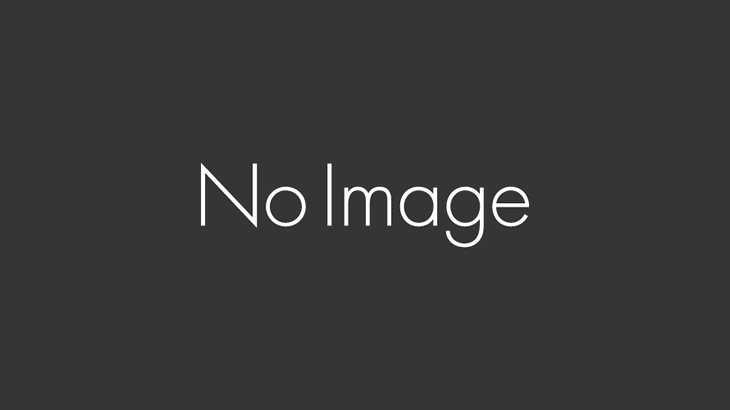- 「男性が離婚を有利に進める秘訣が知りたい」
- 「どのような点に注意すれば有利な離婚条件を勝ち取れる?」
一般的に女性よりも男性の方が、離婚で不利になりやすいといわれています。それはどのような理由からなのでしょうか?そして男性が有利に離婚をすすめるには、どのようなポイントに注意した方がいいのでしょうか?こちらでは男性向けに、離婚を有利に進める方法について徹底解説していきます。
さらに離婚を有利に進めるために弁護士に依頼するメリットも紹介。男性の離婚では、離婚方法や離婚条件ごとに気を付ける点や抑えるべきポイントが異なります。「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、離婚に関する正しい知識を身に付けましょう。
離婚で不利にならないために男性がすべき準備
男性が離婚する場合、女性よりも不利になりやすいといわれています。ではなぜ男性の方が不利になってしまうのでしょうか。こちらでは男性が不利になりやすい理由や、不利にならないためにすべき準備を紹介していきます。
男性が離婚で不利になりやすい理由
離婚に時間がかかればかかるほど男性にとっては負担が増えるということが起こりえます。こうしたことから、一般的には男の離婚は不利になりやすいといわれているのです。
妻の方が収入が低い傾向がある
男性の方が離婚は不利といわれる一番の理由は、離婚時に男性の方が金銭的な負担を強いられることが多いため。多くの家庭では家計の主収入は男性が担っており、女性は専業主婦やパート勤めという場合も少なくありません。離婚を前提とした別居では婚姻費用の支払い、離婚後は子どもの養育費など、収入の多い側が金銭的な負担を求められるのが一般的。
また財産分与では、収入や職業の違いにかかわらず、基本的に夫婦で半分ずつ分けられるのが原則となっています。このように離婚においては、収入が多い男性の方に金銭的な負担が大きくなりがちというのが不利といわれる理由です。
住宅など男性名義の財産が多い
住宅や車など、家族が使用する財産の名義を男性側にすることがよくあります。しかし離婚時の財産分与では、名義がどちらになっているかにかかわらず、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した共有財産に関しては、公平に分け合うのが原則です。こちらも男性が離婚で不利になると考えられる理由です。
子どもの監護を主に妻が行ってるケースが多い
2025年現在、離婚後は父と母のどちらを子どもの親権者にするか決めないと離婚ができません。子どもの年齢が小さいほど母親が親権獲得に有利になるため、離婚をすると子どもと離れて暮らさなければならない男性が増えるということに。これも離婚で男性が不利になるといわれる原因の一つです。
そして親権を持たない側の親は、収入の少ない側に養育費として子どもの生活費や教育費を負担しなければなりません。一般的には男性の方が収入が多いので、男性側から女性側に養育費を支払うことになります。
離婚に関する正しい知識を持つ
男性が離婚で不利にならないためには、離婚に関する正しい知識を持つことが重要です。離婚において男性が金銭的に負担するケースは多いですが、離婚に関する法的な知識の不足から必要以上に負担している人も少なくありません。男性が離婚で不利にならないためにも、離婚に関する正しい知識をもつ必要があるでしょう。
離婚方法について
離婚方法には①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3つの種類があります。それぞれの手続き方法や、進め方は次のように異なります。
| ① 協議離婚 | 夫婦間の協議で離婚に合意できれば、離婚届に双方が署名し役所に提出するだけで離婚が成立する
費用や時間をかけず簡単な手続きで離婚が可能 早く離婚したい場合には、離婚条件で妥協しがち 離婚条件に関する知識が無いと、不利な条件で離婚してしまう |
| ② 調停離婚 | 家庭裁判所に離婚そのものや離婚条件について申し立てて当事者間の話し合いで解決を目指す法的手続き
話し合いでは調停委員や裁判官を間に入れ、夫婦が直接顔を合わせることがない 自分の意見をうまく主張できないと、不利な条件で離婚が成立してしまう |
| ③ 裁判離婚 | 離婚調停が不調に終わった場合、最終的に離婚裁判を提起して離婚の可否を裁判所に判断してもらう
民法第770条に定められている「法定離婚事由」に該当しないと離婚が認められない 判決には強制力があり、法律に基づいて公平に判断してもらえる 経済的な負担が大きく時間や手間がかかる |
上記の他に、離婚条件にのみ争いがある場合は「審判離婚」があり、離婚裁判による解決方法として「判決離婚」「和解離婚」「認諾離婚」というものがあります。離婚方法それぞれにメリットとデメリットがあるので、どのような方法で離婚が可能か検討しましょう。
離婚の仕方や手続き方法については、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚の仕方と手続き方法|後悔しないための離婚条件とを切り出す前にすべき離婚準備を徹底解説」
離婚原因について
男性が離婚で不利にならないためには、離婚原因についての知識も必要です。離婚協議や離婚調停でも双方の合意が得られなければ、最終的に裁判で離婚を求めることになります。裁判で離婚が認められるためには、民法で定められている次の5つの「法定離婚事由」が必要です。
| 1.配偶者に不貞な行為があったとき | 配偶者以外の異性と性的関係を持ったとき |
| 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき | 働いているのに生活費を払わない、理由もなく無断で家を出ていった、不倫相手と生活するために家出したなど |
| 3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき | 3年以上行方不明で連絡が全く取れない、遭難して生死が分からないなど |
| 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき | 統合失調症や偏執病、認知症や失外套症候群などを発病し回復の見込みがないとき |
| 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき | DV、モラハラ、セックスレス、性的異常、ギャンブルやアルコールなどの依存症、過度の浪費や借金、親族との不和、長期の別居、犯罪による服役、過度な宗教活動への傾倒など |
男性の側の不貞行為やDV、モラハラといった行為によって離婚問題に発展している場合、離婚原因を作った側が「有責配偶者」となります。証拠を確保した妻から慰謝料を請求されれば、離婚裁判で慰謝料の支払いを命じられる可能性も。
逆に上記のような離婚理由がないときには、別居を経て調停や裁判へと進み、長期間の別居が「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性があります。具体的な別居時期は個々のケースで異なりますが、一般的に裁判で離婚が認められるには3~5年の別居期間が必要です。
別居期間1年で離婚が可能かについては、こちらの記事を参考にしてください。
「別居期間1年で離婚できる?長引く・認められないケースと早く離婚するポイント」
離婚条件について
男性が離婚で不利にならないためには、離婚条件についての正しい知識が必須です。なるべく有利に離婚するには、離婚を考えた時点で様々な準備をすることが大切。具体的には次のような離婚条件について、どのようなことができるか考えていきましょう。
| 婚姻費用 | 離婚前に別居期間を設ける場合、夫婦の収入の多い側が少ない側に別居期間中の生活費を負担する
夫婦双方の収入や子どもの人数、年齢をもとにして裁判所の「婚姻費用算定表」で算出する |
| 慰謝料 | 離婚時に必ず発生するものではなく、不倫やDVなど民法上の不法行為による離婚原因を作った側に対して請求可能 |
| 財産分与 | 夫婦の職業や収入にかかわらず、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産は、離婚時に1/2ずつ分け合うのが原則
財産分与の対象となるのは共有財産で、基準となるタイミングは離婚時(別居時) |
| 親権 | 夫婦の間に未成熟の子どもがいる場合は、子どもの親権を父母のどちらにするか決めなければならない
2026年5月以降は、単独親権の他に共同親権の運用が開始される |
| 養育費 | 子どもの親権を持たない側の親は、子どもが自立するまでの期間養育費を支払う義務がある
具体的な毎月の支払金額は、裁判所の「養育費算定表」で算出が可能 離婚時に決めた養育費は、離婚後の失業や転職、再婚などの理由で減額が可能 |
| 面会交流 | 養育費を支払う側は定期的に子どもと会い交流が持てる権利がある
離婚時に交流の内容を決めて離婚協議書などにまとめておくとのちのトラブルが防げる |
離婚条件は大きく分けて「お金(財産)」に関することと「子ども」に関することに分けられます。すべての離婚条件について自分の希望が通るという訳でないので、離婚協議を始める前に自分の中で譲れない条件と妥協できる条件を明らかにし、場合によってはある程度の譲歩が必要です。
男性が離婚時にすべきことや注意点は、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚したい男性必見!男性が離婚したい理由と離婚時にすべきこと、注意点とは?」
離婚方法別|男性が有利に離婚するポイント
前出の通り、離婚方法には主に3つの方法があります。それではそれぞれの方法で男性が有利に離婚するには、どのような点に気を付ければいいのでしょうか。
協議離婚
協議離婚を目指す場合のポイントは、以下の通りです。
妻の話に耳を傾ける
離婚の話し合いの時には、相手の話を十分に聞いて妻の主張を理解する必要があります。とはいえ夫婦関係が圧壊している状況で対立が激化すると、相手が感情的になったりして話し合いにならないこともあるでしょう。そのようなときはこちらも感情的になるのではなく、努めて冷静に理論立てて話をする姿勢が必要です。
場合によってはしばらく時間を置き、双方が冷静になったタイミングで話し合いを再開させる方法も有効です。できるだけ相手の話を聞くことで、妻の離婚に対する考えや譲れない条件が分かるもしれません。妻の本音を引き出せれば、その後の離婚条件の交渉時に有利に進められる材料が得られる可能性があります。
妻が離婚に応じない理由や早く離婚するための方法を知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「妻が離婚してくれない。離婚に応じない理由と1日でも早く離婚するための方法」
弁護士に協議を依頼する
普通の話し合いができない相手であれば、自分一人で対処するのは困難でしょう。そのようなときには離婚問題に詳しい弁護士に相談したうえで、妻との協議を依頼してください。弁護士に依頼することで、相手に離婚に関する本気度を示せます。
また弁護士は交渉のプロでもあるので、個々のケースに応じた方法で交渉し、離婚の協議を進めていけるでしょう。弁護士費用などを考えると、当事者同士で話がまとまるに越したことはありませんが、離婚裁判にまで発展しそうな場合やどうしても譲れない条件があるときなどは、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
離婚時の弁護士費用が気になる方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚時の弁護士費用を徹底解剖!費用をおさえるコツや注意点を紹介」
離婚協議書を作成する
離婚そのものや離婚条件で双方が合意した場合、「合意書」や「離婚協議書」という形で合意した内容をまとめておくといいでしょう。とくに慰謝料の分割払いや養育費の支払いなど離婚後も金銭のやり取りが続く場合には、後のトラブルを防ぐ意味でも離婚協議書の作成は重要です。
しかし離婚協議書は法律文書になるので、書き方に不備があったりすると法的に無効になる可能性があります。せっかく作成したにもかかわらず、離婚後にトラブルになることも十分考えられます。そのため、できれば最後の離婚協議書の作成だけは、弁護士に依頼するのがいいでしょう。
調停離婚
夫婦の話し合いが進まないときには、話し合いの場を家庭裁判所に移すのが有効です。離婚調停では、第三者である調停委員や裁判官を介して話し合いが進められるため、夫婦だけの話し合いが難しくても双方が冷静になって話し合いが進むケースが少なくありません。離婚調停では、次のような点に気を付けると有利に進められるでしょう。
主張は書面を準備
こちらの主張はあらかじめ書面にまとめておくと、要点を整理して言いたいことが主張できます。1回の調停の時間は、1時間から1時間半程度のことがほとんどで、妻と夫が交互に調停委員と話をするので、自分の意見を伝える時間はかなり限られてしまうでしょう。
また頭で考えた内容を伝えようとすると、言いたいことをいい忘れてしまったり、主張を十分に理解してもらえないことも。そこで自分が伝えたい内容は、あらかじめ書面にまとめておくといいでしょう。さらに書面は期日の1週間前までを目安に家庭裁判所に提出しておくと、事前に調停委員が目を通してくれます。次の調停でスムーズに話し合いが進められるでしょう。
離婚調停を短くする秘訣や有利に進めるポイントは、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚調停の期間を短く有利にするには?長引く原因や疑問を解決して新たな一歩を」
証拠を確保する
相手のモラハラや不倫が原因で離婚請求や慰謝料請求する場合、その証拠を確保しておくことが重要です。集めた証拠は調停に提出することができます。調停を申し立てた後で証拠を集めようとすると、相手が警戒して思うように証拠が集められない可能性が高いでしょう。なるべく離婚を切り出す前や別居する前に証拠は集めておきましょう。
ゆくゆくは離婚裁判を視野に入れているという場合、法的に有効な証拠が必須です。最近では妻からのDVやモラハラで離婚を考えている男性が増えています。離婚したい理由ごとに次のような証拠を確保しましょう。
| 不貞行為 |
|
| DV・モラハラ |
|
| セックスレス |
|
| 悪意の遺棄 | (無断別居・外泊・家出の証拠)
(家事や育児を放棄している証拠) 家事や育児に関するメッセージのやり取り(全く返信がない、非協力的な返事をしているなど) |
証拠集めで重要なのが、第三者が客観的な視点で相手に離婚原因があることを証明できるかどうかです。複数の証拠を組み合わせて証拠とできる可能性もあるので、どんな些細な証拠でも集めるようにしましょう。
モラハラで慰謝料請求する場合のポイントや証拠の残し方は、こちらの記事を参考にしてください。
「夫婦や恋人間のモラハラで慰謝料請求できる?相場や方法を知って有効な証拠を確保しよう」
調停委員を味方につける
離婚調停を有利に進めるには、調停委員を自分の味方につけるのがポイントです。調停委員は夫婦の間に立ち、中立の立場で進めていくのが前提です。とはいえ調停委員も人間です、無意識のうちにどちらかに偏って調停を進める可能性があることも否定できません。
そのためには調停委員に好印象を持ってもらう必要が。具体的には次のような点に気を付けましょう。
- 身だしなみを整える
- 言葉遣いは丁寧に
- 嘘をつかない
- 感情的にならない
- 無茶な要求をしない
大人として礼儀正しい姿勢でいることは当然ですが、自分の意見を言うときには冷静に理論立てて伝えることがポイント。このような点を注意して、自分の意見の正当性や妥当性を理解してもらえるよう、調停委員を味方に付けましょう。
裁判離婚
離婚調停が不調に終わった場合、法定離婚事由があるようなケースでは離婚裁判に移行します。離婚裁判で有利に進めるには、次のような点が重要です。
離婚問題に詳しい弁護士に依頼する
離婚問題にかかわらず、裁判となれば法律の専門家である弁護士に依頼するのが一般的。数ある弁護士事務所の中でも、夫婦問題や離婚問題に詳しいところに依頼すれば、有利に裁判を進めるための方針を検討してもらえます。
裁判の期日は基本的に平日に行われるため、期日の度に仕事を休んで裁判所に行くのは大変です。また提出すべき書類もたくさんあります。その書き方も法律文書ならではの用語や作法があるので、法律の知識がない一般の人が作成するのは困難です。
また妥当な離婚条件については、個々のケースによって変わってきます。そのような面でも、弁護士に依頼した方が裁判を長引かせずに納得できる条件で離婚が可能になるでしょう。
離婚時に依頼したい弁護士の選び方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚時に依頼したい弁護士の選び方|相談前・相談時のポイントと費用に関する注意点を解説
離婚前の別居で不利にならないために
離婚前に別居を検討している方は、別居で不利にならないために次のような注意点があります。
- 相手に無断で家を出ない(悪意の遺棄とみなされる可能性)
- 自分に非がある場合の別居は慎重に
- 別居前に妻の不倫・DVなどの証拠を確保する
- 別居前に妻名義の財産や共有財産の調査をする
- 妻に婚姻費用を請求されたときにはきちんと支払う(悪意の遺棄とみなされる可能性)
- 別居中は異性と交際しない
別居すると決めたら離婚で不利にならないよう準備は念入りに行いましょう。また妻に黙って家を出たり、請求された婚姻費用を支払わないでいると、悪意の遺棄とみなされてあなたが有責配偶者となってしまいます。離婚で不利になる可能性が高いので、気を付けましょう。
別居に必要な準備と注意点は、こちらの記事を参考にしてください。
「別居に必要な準備をシチュエーション別に解説!別居に関する注意点とは?」
離婚条件別|男性が有利になるポイント
こちらでは離婚条件別に、男性が有利になるポイントを解説していきます。
婚姻費用
妻から別居中の婚姻費用を請求された場合、基本的に男性は支払いを拒否できません。そのため、男性側はまず婚姻費用の支払いをおさえることを考える必要があります。
請求金額が相場の範囲内かチェック
まずは妻から請求された婚姻費用の金額が、相場の範囲内かチェックしましょう。裁判所の「婚姻費用算定表」をもとに、自分たち夫婦のケースに当てはめて金額を算出してください。相場よりも高い金額を請求されたときには、調停などを経て相場に減額できる可能性が高いです。
また妻の不倫などで別居に至った場合には、支払う婚姻費用を減額できる可能性が高いです。またあなたの収入よりも妻の収入の方が多いときには、妻に対して婚姻費用を請求できます。
交渉が長引きそうなときには離婚調停を申し立てる
別居後の離婚協議が長引きそうなときには、早めに離婚調停を申し立てることを検討してください。一般的に婚姻費用には、妻と同居している子どもの生活費にプラスして、妻自身の生活費も含まれます。離婚後の養育費よりも高めに設定されているので、高額な婚姻費用を受け取り続けたいとあえて協議を長引かせようとする場合があります。
そこでこのような場合には、早めに協議を切り上げて、できるだけ早く離婚調停に移行するという選択をするといいでしょう。
一部の条件は離婚後に交渉
一部の条件を離婚後に交渉すると決めると、より早く離婚を成立させられます。子どもの親権だけは離婚前に決めなければ離婚届が受理されず離婚が成立しません。しかしそれ以外の財産分与や慰謝料、養育費や面会交流といった条件は、離婚をした後でも話し合いが可能です。
相手次第ではありますが、婚姻費用の負担を減らすためにあえて一部の条件を離婚後に交渉するという方法もあります。
離婚条件に優先順位をつける
離婚協議を長引かせないために、離婚条件に優先順位を付けるのも大切です。離婚成立まで長引いて余分な婚姻費用を支払うくらいなら、財産分与などの条件面で少々妥協しても早めに離婚を成立させた方が良い場合もあるでしょう。どちらの方が損をしないかよく検討し、譲れる条件がないか考えてみましょう。
離婚調停が不成立になった後の対処法は、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚調停が不成立…その後どうすれば?注意点と確実に離婚するためのポイントとは」
慰謝料
離婚時の慰謝料は、全てのケースで発生するわけではありません。自分や相手に不貞行為などの民法上の不法行為があった場合に限り、精神的苦痛に対する損害賠償の意味で苦痛を与えた側に慰謝料の支払いが発生します。
慰謝料の相場を知る
こちらに離婚理由があるときには、妻から慰謝料を請求される可能性があります。請求された慰謝料の金額が相場よりも高い場合には、減額交渉の余地があります。慰謝料の相場は、離婚理由ごとに次のように変わります。
| 離婚理由 | 慰謝料の相場 |
|---|---|
| 不貞行為 | 100万~300万円 |
| DV・モラハラ | 50万~300万円 |
| 性の不一致・セックスレス | 0円~100万円 |
| 悪意の遺棄 | 50万~300万円 |
| 婚姻を継続し難い重大な事由 | 100万~300万円 |
慰謝料の相場に幅があるのは、次のような様々な要素によって変動するためです。離婚裁判では、離婚原因について具体的な証拠をもとにして慰謝料の金額を決めていきます。
- 婚姻期間
- 子どもの有無・人数・年齢
- 離婚の原因
- 離婚原因が行われた期間・回数・有責度
- 夫婦の年齢
- 夫婦の職業・年収・資産
- 離婚原因を作った側の反省の度合い
- 精神的苦痛の大きさ
離婚慰謝料の相場が知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「離婚慰謝料の相場が知りたい!離婚理由や婚姻期間による相場・金額をアップさせるポイントを解説」
相手の不法行為の証拠を確保
妻の方に離婚原因があるときには、慰謝料を請求できるだけの法的に有効な証拠が必要です。証拠は裁判で離婚を請求するときにも必要に。より有利な条件で離婚するためには、妻が有責配偶者である証拠をしっかりと確保しておきましょう。
妻の浮気で離婚を決意したときに取るべき行動は、こちらの記事を参考にしましょう。
「妻の浮気で離婚を決意したら…親権・慰謝料など損をしないために取るべき行動」
財産分与
離婚する場合、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を夫婦で原則1/2ずつに分けるのが財産分与です。とくに妻が夫の給料を含めて家計を管理していた場合には、妻が財産を隠し持っている可能性も。財産分与を有利に進めるためには、何よりも財産の把握が重要となります。
共有財産のリストアップ
結婚後に取得したり購入した財産は、基本的にすべて財産分与の対象です。名義がどちらになっているかは関係なく、半分ずつに分配するのが原則。財産分与で損をしないために、まずは共有財産のリストアップから始めましょう。具体的な財産の種類や、調査方法については以下の通りです。
| 現金や預貯金 |
|
| 住宅等の不動産 |
|
| 自動車 |
|
| 有価証券 |
|
| 貴金属や骨とう品などの動産 |
|
| 年金 |
|
| 退職金 |
|
| 生命保険や学資保険の解約返戻金 | 離婚時に解約した場合の返戻金を計算し、その半分を現金で渡す |
離婚前の口座整理のポイントは、こちらの記事を参考にしてください。
「【離婚前】口座整理の注意点とは?ケース別・口座整理のポイントとよくある疑問質問にお答えします!
相手の財産をもれなく調査する
財産分与は男性が払うものと思い込んでいる方が多いですが、妻の方がより多くの財産を持っているときには、逆に妻の側から支払うということになります。財産分与で損をしないためには、妻名義の財産をもれなく調査する必要があるでしょう。
同居中であれば、相手名義の預金通帳を確認するなどの方法があります。また弁護士に依頼して、妻が保有している財産の一覧の開示を請求するという方法も。
財産を適切に評価する
財産分与を適正に行うには、財産の評価も適切に行わなければなりません。現金や預貯金は単純に1/2にすればいいのですが、不動産や株式はその価値の評価が難しいという特徴があります。これらの財産は共有財産の中でも大きなウエイトを占めるケースが多いので、特に注意が必要。不動産を適正に評価するポイントは以下の通りです。
| 査定の方法 | 内容 |
| 複数の不動産会社に依頼 | 最低でも3社から査定を取るようにし、それぞれの評価額を比較検討する
各社の査定根拠を確認して、納得できる評価を採用する |
| 公的な評価を参考にする | 路線価や固定資産税評価額などを参考にする
ただし実勢価格と乖離があるので、あくまでも一つの目安として活用する |
| 最新の市場動向を見る | 不動産市場は常に変動しているため、最新の動向を探ることも大切
直近の取引事例や近隣の価格、市場トレンドなどを参考にする |
| 将来的な価値変動の検討 | 現在の評価額だけでなく、将来的な価値変動の可能性がないかも検討する
再開発計画の有無や地域の人口増加、周辺のインフラ整備が進んでいるかなどを調査する |
| 専門家のアドバイスを受ける | 不動産の専門家のアドバイスを受け、物件の適正な価値や将来的な資産価値の見通しなどの情報を得る |
株式の評価に関しては、財産分与時点すなわち離婚時の価値を基準とします。上場企業であればその時点での株価を見ればいいのですが、非上場企業の場合はその計算方法が複雑になります。財産の評価の仕方について不安な方は、弁護士に相談するといいでしょう。
年金分割の方法や離婚後に後悔しないポイントは、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚で年金はどうなる?財産分与における年金分割の種類と方法、離婚後に後悔しないポイントとは
特有財産がないか調査する
財産分与で損をしないためには、今持っている財産の中に特有財産がないかチェックしましょう。特有財産とは妻の協力なしに形成された財産で、財産分与の対象から外れる財産のことです。次のようなものが該当します。
- 結婚以前から保有していた財産
- 親などから相続・贈与で受け取った財産
- 個人名義で得た財産
- 個人的な身の回りのもの(衣類・化粧品・趣味の道具など)
結婚前から持っている銀行口座を結婚後も生活費の出し入れに使用している場合には、結婚時点でいくら残高があったかの切り分けが必要です。
妻の貯金の使い込みで離婚を決意した方は、こちらの記事を参考にしてください。
「夫や妻の貯金使い込みで離婚できる?別居時に気を付けたいこと&財産分与で損しない方法」
1/2ルールの例外を知る
財産分与は夫婦で1/2ずつ分けるのが原則ですが、夫婦が合意すれば必ずしも1/2ずつでなくても構いません。また夫婦の一方に特別な能力や資格があったり、過酷な条件での労働をして得た収入の場合は、夫婦の財産形成においてより一方の貢献度が高いと判断されて、半分ではなくより多くの分与を受けられる可能性があります。
子どもの親権
未成年の子供がいる場合、親権をどちらが持つか大きな問題になる場合があります。2025年現在では離婚後は単独親権となるので、親権者を決めないと離婚が認められません。
親権獲得の要件とは
父親が親権を得るには、離婚後の養育環境やこれまでの子どもとの関係が重要視されます。親権を決めるときの判断ポイントは以下の通りです。
- 監護の意欲や実績
- 監護の継続性(これまで主として子どもの世話をしてきた側はどちらか)
- 離婚後の監護の環境
- 看護補助者の有無(子育てに協力してくれる人はいるか)
- 面会交流に許容的かどうか
- 子供自身の意思(15歳以上の子どもの場合は本人の意思が尊重される)
- きょうだい不分離の原則(きょうだいは離れ離れにさせず同じ親権者の元で暮らすべきという考え)
- 母子優先の原則(子どもの年齢が小さいほど母親が有利)
子どもの親権を考えたとき母親である妻が親権を獲得するケースが多いですが、母親側に次のような状況がある場合には、父親の方に有利になる可能性があります。
- 子どもを虐待していた
- 育児放棄(ネグレクト)をしていた
- 精神疾患があり育児ができない状態
- 子ども自身が父親と暮らすことを希望している
- 父親に育児を任せきりにしていた
- すでに父親と子どもが一緒に暮らしている
- 監護補助者が全くいない
親権争いで母親が負ける理由や対策は、こちらの記事を参考にしましょう。
「親権争いで母親が負ける理由とは?親権争いを勝ち取る6つの対策も解説」
親権獲得のためにできることをする
上記のような父親に有利なケースに当てはまらない場合でも、離婚までには親権獲得のためにできることをしていきましょう。具体的には毎日の子どもの世話を積極的に行って、監護実績を作ってください。また離婚後の監護への協力体制を整えるのもポイント。
とはいえいくら親権を獲得したくても、母親に無断で子どもを連れて別居するのはおすすめできません。連れ去り別居は親権の判断に不利になります。いくら子どもの親権を獲得したくても、強引な方法はとらないようにしましょう。
父親が親権を取れる確率が知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「父親が親権を取れる確率は?重視されるポイント・親権獲得のためにすべきことを解説」
養育費
子どもの親権者でない側の親は、離婚後の子どもの養育費の支払い義務があります。支払期間は子どもが成人を迎えるまでや学校を卒業して就職するまでなど夫婦の合意で決められます。養育費の支払いで損をしないためには、次のような点に気を付けましょう。
適正金額を把握する
養育費については、婚姻費用と同様に適正金額があります。こちらも裁判所が公表している算定表を目安にしましょう。双方の収入にもよりますが、一般的には子ども1人に対して3万~5万円程度が相場です。こどもがおさない場合には長期間にわたって養育費の支払いが続くので、金額はきちんと決めたいものです。
また子どもが怪我や病気をして予想以上の医療費がかかったケースや、子どもが重度の障害を負ったケース、留学や大学院への進学などで教育費が必要になったケースでは養育費支払いの延長や増額が認められる場合も。離婚時に養育費をいつまで支払うかや増額の要件などを決めておきましょう。
離婚時の養育費の相場が知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚時の養育費の相場が知りたい!ケース別の相場や増額方法、請求方法とは?」
場合によっては減額も可能
離婚後に状況が変わったときには、支払う養育費の減額を請求できる可能性があります。例えば支払う側(義務者)と受け取る側(権利者)の次のようなケースで、養育費の減額が認められるでしょう。
- 義務者の収入が病気やけが、倒産などやむを得ない事情で減少した
- 義務者が再婚して扶養家族が増えた
- 権利者の収入が離婚時よりも増えた
- 権利者が再婚して世帯収入が増えた
- 権利者が再婚し、子どもと再婚相手が養子縁組した
一方で義務者の都合で収入が減少した場合や再婚したが扶養家族が増えなかった場合には、減額が認められない可能性があります。減額を希望する場合は、任意の話し合いの他に養育費減額調停や審判を申し立てて減額を求めていきます。
養育費の減額請求の方法やポイントは、こちらの記事を参考にしてください。
「養育費を勝手に減額できる?減額請求時のポイント&減額されたときの対処法を解説」
面会交流
親権を妻に譲らざるを得ないときは、子どもとの面会交流について離婚前に決めておきましょう。離婚して夫婦でなくなっても、子どもの親であるという事実は変わりません。親のためだけでなく子どものためにも面会交流は必要です。子どもを虐待していたなどの危険性がない限り、元妻が面会交流を拒否しても認められません。
離婚前に詳細を決める
子どもとの面会交流をスムーズにするためには、離婚前に面会交流について詳細を決めた方がいいでしょう。決める内容は以下の通りです。
- 面会交流の頻度
- 面会交流の時間や場所
- 連絡方法
- 都合が悪い時の対応
- 学校行事へ参加するかどうか
- 宿泊・旅行は可能かどうか
- 祖父母との面会をどうするか
- 交通費の負担はどうするか(遠方の場合)
夫婦の話し合いで決めるのが一般的ですが、合意できないときには家庭裁判所の調停や審判によって面会交流の頻度などを決めたうえで実施していきます。法的手続きで決められたにもかかわらず、元妻が面会交流に応じないときには、裁判所による履行勧告や強制執行という手続きが取れます。
面会交流を拒否できるかについては、こちらの記事を参考にしてください。
「面会交流を拒否したい!子供に会わせないことの違法性と対処法を解説!」
決めた内容は合意書に作成
面会交流の回数や方法を決めたら、しっかり実施してもらえるよう決めた内容は合意書にまとめて証拠として残しておきましょう。離婚後に面会交流を拒否して子どもと会わせてくれないケースでは、調停を起こして面会の機会を確保しなければなりません。このような場面でも、合意書は必要です。
まとめ
男性は女性に比べて収入が高いケースが多いことから別居時の婚姻費用や離婚時の養育費支払いで金銭の負担が生じます。また男性名義の財産あっても、共有名義の場合には原則として1/2ずつに分けなければならないのも男性が不利だといわれる一因です。子どもの親権を持ちたくても希望通りにならないケースが多く、子どもを一緒に暮らしたい男性は、離婚を躊躇するかもしれません。
男性が離婚で不利にならないためには、離婚方法や離婚条件についての法的知識を知っておくのがポイント。金銭のやり取りが発生する場合は相場の金額をおさえておきましょう。またなるべく早いタイミングで離婚問題に詳しい弁護士に相談するのもおすすめです。
弁護士に相談することで、男性ならではのポイントが分かります。実際に妻との交渉を任せられるだけでなく、調停や裁判になったときにも手続きを任せられます。親権など譲れない離婚条件がある人ほど、綿密な準備や対策が必要です。離婚を後悔しないためにも、安心して任せられる弁護士を見つけましょう。