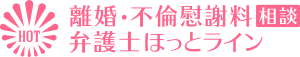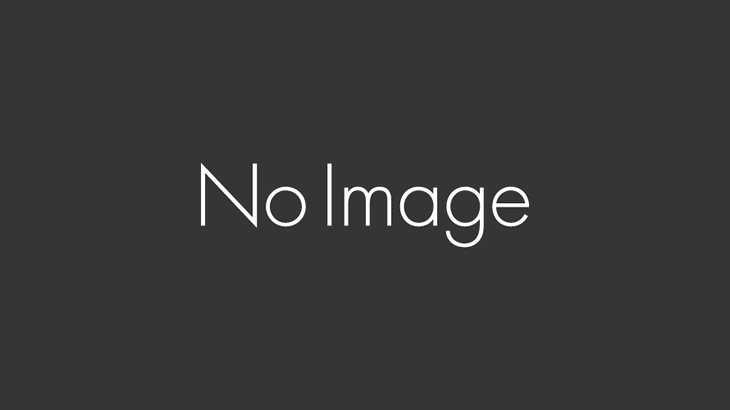- 「離婚を考えているが、手続き方法が知りたい」
- 「後悔しないために必要な離婚準備とは?」
夫婦仲が悪化して離婚を考えたとき、気になるのがスムーズに離婚できるかという点や離婚の方法です。どのような離婚の方法があるか分からなければ、離婚を実現できません。そこでこちらの記事では、離婚の仕方を中心に手続き方法や離婚時に決めるべき離婚条件について詳しく解説していきます。
さらに相手に離婚を切り出す前にやっておくべき離婚準備や、円満離婚を実現するためのポイントも紹介。スムーズに離婚するためには、やっておくべきことがたくさんあります。離婚についての知識をしっかりと頭に入れ、新しい人生への一歩を踏み出す準備を進めましょう。
離婚する方法は6種類|手続き方法とメリット・デメリット
今の日本で離婚する方法は、全部で6種類あります。それぞれの種類ごとの手続き方法や必要書類、必要な期間や有利に進めるポイントはこちらです。
1.協議離婚
協議離婚とは、夫婦間の話し合いのみで離婚する方法です。令和二年の統計によると、協議離婚の割合は全体の88.3%と圧倒的に多いのが現状です。協議離婚は夫婦の協議に基づく離婚なので、双方が離婚に合意すればどのような理由であっても離婚が可能です。
離婚届を提出する場合は、本人たちの署名捺印の他、成人2名の証人の署名捺印も必要です。また夫婦の間に未成年の子供がいる場合には、父母のどちらを親権者とするか決めないと離婚届を提出できません。離婚届は届出人の本籍地またはお住いの市区町村役場です。届出人が窓口に離婚届を持参するほか、郵送や代理人による提出も可能です。
価値観の違いで離婚したいとお考えの方は、こちらの記事を参考にしてください。
「価値観の違いで離婚したい…よくある理由と離婚の可否、迷ったときの相談機関を紹介」
必要書類
離婚届を窓口に提出するときに必要な書類は以下の通りです。
- 離婚届
- 本人確認書類
- 戸籍謄本(本籍地以外の市区町村役場に提出するとき)
離婚届は代筆できるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚届けは代筆できる?有効性や認められる要件を解説!相手の同意なしに離婚する方法とは」
有利に進めるポイント
協議離婚で離婚する場合、離婚後のトラブルを避けるためには、話し合いで決めた内容(養育費・財産分与・慰謝料)などを離婚協議書や公正証書として残しておくことをおすすめします。とくに養育費や慰謝料など、金銭の取り決めをしたときなどは、認諾文言付きの公正証書とすることで、離婚後の支払いが滞ったときに、裁判手続きなしに強制執行の申立てが可能です。
なお離婚時に公正証書を作成するときには、戸籍謄本や年金手帳、不動産の登記簿謄本や固定資産評価証明書などの書類が必要になる場合があります。慰謝料を請求するときなどは、請求する金額が適正であるかなどを弁護士に相談するといいでしょう。
必要な期間
協議離婚にかかる期間は、平均して半年程度です。夫婦の話し合いのみで離婚が可能なので、話し合いがすぐにまとまれば離婚までの期間は短くなります。一方で夫婦のどちらかが離婚に合意しないときや、離婚条件で揉めている場合などは離婚成立までの期間が長くなります。場合によっては離婚調停に進んだ方が良いケースもあるので、このまま話し合いを続けるべきか慎重に判断しましょう。
メリット・デメリット
協議離婚には、次のようなメリットとデメリットがあります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
2.調停離婚
離婚調停は、家庭裁判所に離婚そのものや離婚条件について申し立てる法的手続きのこと。離婚したいと考えている側が申立て、裁判官と調停委員を双方の間に入れ、当事者間の話し合いによって解決を目指します。話し合いでは調停委員がまず申立人から話を聞き、その後に相手方から言い分を聞きます。
このように交互に言い分を聞きながら、話し合いによって離婚の合意や離婚条件の妥協点を見出していきます。片方の言い分を聞くときには、原則として相手方は同じ場所に同席しません。とはいえあくまでも話し合いによる合意を目指す手続きなので、合意できない場合には調停は不成立となり、その後は審判や裁判に移行します。
調停を申し立てるのは、相手方配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所です。申立てから約1カ月後に、第一回目の調停期日が開かれます。1回につき約2時間の調停で、およそ30分ずつ夫婦交互に話を聞くケースが多いです。
必要書類・かかる費用
離婚調停に必要な書類は、以下の通りです。
- 調停申立書
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割を希望する場合)
その他、家庭裁判所が求める証拠資料などを適宜提出します。離婚調停を申し立てる場合は、次のような費用がかかります。
- 収入印紙1,200円分
- 切手代1,000円程度(裁判所によって異なる)
- 戸籍謄本取得費用450円
このほかにも必要書類の取得手数料や実費などの費用が必要です。詳しくは調停を申し立てる予定の家庭裁判所にご確認ください。
離婚調停にかかる費用については、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚調停にかかる費用とは?裁判所・弁護士費用の詳細や一括で払えないときの対処法も」
有利に進めるポイント
離婚調停を有利に進めるには、調停委員を味方につけるようにしましょう。調停委員は夫婦のことを知らない全くの第三者です。相手方から聞き取った離婚したい理由や調停に至る経緯が事実かを、こちら側に訪ねてきます。このときに相手から直接言われたような反応をして、感情的になる人がいますが、これは逆効果です。
冷静に調停委員の言葉を受け止め、真実でないところは淡々と事実と違うことを反論してください。相手に婚姻生活を継続しがたい理由があるときには、それを裏付ける証拠を提出したうえで説明してください。
離婚調停が不成立になったときの対処法は、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚調停が不成立…その後どうすれば?注意点と確実に離婚するためのポイントとは」
必要な期間
離婚調停は1カ月もしくは2カ月に1度行われ、トータルで3回から5回程度開かれます。最低でも3カ月、長いと半年程度かかると覚えておきましょう。調停の結果合意できた場合には、調停成立となり調停調書が作成されます。そして調停成立から10日以内に、離婚届と調停調書謄本を市区町村役場に提出すれば晴れて離婚が成立します。
離婚調停の期間を短くするコツは、こちらの記事を参考にしてください。
「離婚調停の期間を短く有利にするには?長引く原因や疑問を解決して新たな一歩を」
メリット・デメリット
調停離婚のメリットとデメリットはこちらです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
離婚調停は弁護士なしで対応可能かについては、こちらの記事を参考にしてください。
「離婚調停は弁護士なしで対応できる?依頼したほうがよいケースとメリット・デメリット」
3.審判離婚
離婚調停において離婚条件の一部で合意が得られずに調停が不成立になりそうなときなどには、家庭裁判所の裁判官の職権により審判に進むケースがあります。この審判の中で裁判官が必要な決定を下して離婚に至ることを、審判離婚といいます。具体的には次のような場合に、審判に移行します。
- 離婚自体の合意は得られているが、離婚条件でわずかな意見の食い違いがある
- 当事者の一方が遠隔地にいて裁判所に出頭できないが離婚意思は確認できている
- 相手方が理由なく調停に出席せず、婚姻関係が破綻していると認められる
審判が下されると、その内容を記した審判書が作成され、審判の告知を受けた翌日から2週間以内に夫婦の双方から異議申し立てが無ければ、審判が確定します。ここで審判離婚は成立となります。審判離婚が成立してから10日以内に、離婚届、審判書謄本、審判確定証明書、戸籍謄本(本籍地以外に提出するとき)を市区町村役場に提出してください。
必要な期間
審判の前には必ず調停が必要になるため、調停申し立てから審判離婚が成立するまでは最低でも半年程度かかります。場合によっては1年前後の期間を要する可能性があります。
メリット・デメリット
審判離婚のメリットとデメリットは、こちらの通りです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
審判離婚になる条件や流れについて詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。
「審判離婚とは?審判離婚になる条件や離婚までの流れを知ろう」
4.裁判離婚
裁判離婚とは、家庭裁判所に離婚裁判を提起して、判決によって離婚の可否や離婚条件を決定する法的手続き。離婚裁判を提起するには必ず離婚調停を経る必要があるので(調停前置主義)、基本的には調停が不成立になった後で裁判を提起することになります。夫婦のどちらかの住所地を管轄する家庭裁判所に訴状を提出するのが原則です。
ただし住所地と異なる家庭裁判所で離婚調停を行ったときには、裁判所の許可があれば離婚調停を行った裁判所に訴状を提出できます。
必要書類・かかる費用
離婚裁判を提起するのに必要な書類は以下の通りです。
- 訴状(2通)
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 法定離婚事由を証明する資料
- 年金分割のための情報通知書(年金分割を希望するとき)
- 源泉徴収票や預金通帳など証拠資料のコピー(財産分与・養育費を請求するとき)
また離婚裁判を提起するときには、次のような費用がかかります。
- 収入印紙13,000円~
- 切手代6,000円程度
- 戸籍謄本取得費用450円
このほかに実費や取得手数料などの費用がかかります。また裁判を提起する場合は、弁護士に依頼する必要があります。このとき弁護士費用が追加でかかることも覚えておきましょう。具体的な費用の内訳は以下の通りです。
| 相談料 | 無料~1万円程度 |
| 着手金 | 10万~50万円 |
| 報酬金 | 得られる経済的利益の5~20%
減額できた金額の月数×10%~ |
| 実費 | 弁護士の日当、宿泊費、交通費など |
費用の相場や算出方法は、依頼する弁護士事務所によって変動します。詳しい金額は相談時に確認してください。
離婚時の弁護士費用について詳しくは、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚時の弁護士費用を徹底解剖!費用をおさえるコツや注意点を紹介」
法定離婚事由が必要
離婚裁判を提起するためには、民法第770条に定められている法定離婚事由が必要です。具体的には次のような内容をいいます。
| 1.配偶者に不貞な行為があったとき | 配偶者以外の異性と性的関係を持ったとき |
| 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき | 働いているのに生活費を払わない、理由もなく無断で家を出ていった、不倫相手と生活するために家出したなど |
| 3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき | 3年以上行方不明で連絡が全く取れない、遭難して生死が分からないなど |
| 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき | 統合失調症や偏執病、認知症や失外套症候群などを発病し回復の見込みがないとき |
| 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき | DV、モラハラ、セックスレス、性的異常、過度の浪費や借金、親族との不和、長期の別居、犯罪による服役など |
離婚したい理由が法定離婚事由に該当しない場合には、協議離婚もしくは調停離婚で離婚成立を目指す方が離婚できる可能性が高いです。
離婚裁判で負ける理由が知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚裁判で負ける理由|統計からみる裁判結果と裁判を進めるコツ&負けたときの対処法とは」
離婚裁判の流れ
離婚裁判を提起した後は、必要に応じて月1回程度の裁判期日が設定されます。期日には夫婦それぞれの意見を主張し、それを証明する資料を提出することで、争いの内容を整理していきます。争点や証拠が整理された後は「証拠調べ」として当事者それぞれへの本人尋問が行われます。
本人尋問では、当事者本人が裁判官や代理人からの質問に答える形で進められます。夫婦関係について最も詳しく事情を把握している当事者本人への尋問となるため、本人尋問はとても重視されます。なお本人尋問の前に、それぞれが自分の主張をまとめた「陳述書」を裁判所に提出することもあります。
有利に進めるポイント
離婚裁判を有利に進めるためには、何よりも法律の専門家である弁護士に依頼するのが一番です。離婚問題を専門としている弁護士なら、法定離婚事由として認められそうかや妥当な離婚条件についてアドバイスが得られるでしょう。実際の裁判手続きにおいても、離婚裁判をスムーズに進められます。
必要な期間
離婚裁判は平均して、半年から2年程度で終わるのが一般的です。稀に数カ月程度で終わるケースもありますが、長期化すると数年単位となることも。最低でも1年程度はかかると覚悟しておいた方がいいかもしれません。
離婚裁判に必要な期間については、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚裁判の期間を手続きの流れごとに解説!長引くケース・期間を短縮する秘訣とは?」
4-1判決離婚
本人尋問の結果、和解の見込みがないときには、裁判官から判決が言い渡されます。これを判決離婚といいます。判決離婚では、たとえ相手が離婚に同意しなくても離婚が成立します。この点で協議離婚や調停離婚とは大きく異なります。判決内容に不服があるときには、判決書の送達から2週間以内に控訴する必要があります。
メリット・デメリット
判決離婚のメリットとデメリットは以下の通りです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
4-2和解離婚
離婚裁判中に当事者同士の話し合いで合意できれば、その時点で裁判が終了し離婚が成立します。これを和解離婚といいます。和解離婚は平成16年の人事訴訟法によってつくられた、比較的新しい離婚方法です。和解離婚が成立した後は、成立日から10日以内に離婚届を役所に提出してください。
離婚届、戸籍謄本、和解調書の謄本などが必要です。必要書類をそろえて離婚届を提出、無事に受理されれば和解離婚は終了となります。
メリット・デメリット
和解離婚のメリットとデメリットはこちらの通りです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
4-3認諾離婚
認諾離婚とは、離婚裁判中に離婚裁判を提起した側(原告)の離婚請求を、提起された側(被告)が全面的に受け入れることで裁判を終わらせる解決方法。和解離婚と同じく、平成16年から創設された比較的新しい離婚方法といえます。
ただし認諾離婚できるのは、離婚することのみを争点としている裁判に限られます。そのため財産分与や養育費といった離婚条件を含めて離婚裁判を提起しているときには、基本的に認諾離婚ができません。また夫婦の間に未成年の子供がいる場合も、子どもの親権者を決める必要があるため認諾離婚できないことになっています。
必要な期間
認諾してから2週間以内なら、異議申し立てが可能です。異議申し立てがない場合はそのまま認諾が確定します。認諾離婚が成立した後は「認諾調書」という書面が裁判所で作成されるので、離婚が成立してから10日以内に離婚届と一緒に役所に提出してください。
メリット・デメリット
認諾離婚のメリットとデメリットはこちらの通りです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 裁判を途中で終わらせられるので早期に解決できる | 相手の要求をすべて受け入れなければならない |
離婚を決めたら…離婚条件の把握
離婚すると自分の中で決めた後には、様々な離婚条件について現状を把握したうえで、希望がかなえられるか検討する必要があります。こちらでは、離婚時に最低限把握しておくべき離婚条件について解説していきます。
【財産分与】資産(共有財産)の把握
離婚すると決めたら、財産分与のための共有財産の把握が必須です。そもそも財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した「共有財産」を離婚時に分ける手続き。分与割合は基本的に1/2ずつで、働いていても専業主婦でも半分ずつが原則です。
共有財産とは
財産分与の対象となるのは、上で説明した通り「共有財産」です。結婚後に形成した財産は、名義にかかわらず共有財産となります。また共有財産には、ローンなどのマイナスの財産も含まれます。家族が住むための家をローンで購入したときは住宅ローンが、生活費が足りないときにキャッシングした場合はその借入金が共有財産となります。
一方で結婚前から保有していた財産や、自分の親族から贈与又は相続で得た財産は「特有財産」となり、財産分与の対象から外れます。また結婚期間中に作った借金であっても、個人的な浪費やギャンブル、投資などが原因の借金は、財産分与の対象外です。
財産分与の対象となる期間は、基本的に結婚してから離婚するまでの期間(婚姻期間)です。離婚前に別居を経た場合は、別居するまでの期間が対象となります。
共有財産のリストアップ
財産分与を確実に行うには、共有財産のリストアップが欠かせません。相手が内緒で保有している財産がないかも、しっかりとチェックしましょう。具体的には次のような財産について、どんな財産がいくら分あるかリストアップしていきましょう。
| 財産の種類 | 評価方法 |
|---|---|
| 住宅などの不動産 |
|
| 自動車 |
|
| 株式などの債権 |
|
| 学資保険、生命保険などの解約返戻金 |
|
| 貴金属などの動産 |
|
| 退職金 |
|
| 年金分割 |
|
離婚時に年金分割するときの計算方法や手続き方法については、こちらの記事を参考にしてください。
「離婚で年金はどうなる?財産分与における年金分割の種類と方法、離婚後に後悔しないポイントとは」
【親権】どちらが獲得するか
夫婦の間に未成年の子供がいる場合は、どちらが親権を獲得するか決めないと離婚できません。親権獲得に争いがないときはスムーズですが、どちらも親権獲得を希望する場合は、争いが激化して裁判にまで発展する可能性が。自分がぜひとも親権を獲得したいと考えるときには、獲得できそうかよく検討しましょう。
親権獲得の条件
親権を獲得するためにはいくつかの条件があります。基本は「子どもの利益や福祉に反していないか」が条件となり、子どもにとってどちらが親権を持つ方が子どものためになるかを第一に考えます。そのうえで、次のような状況を見ながら、どちらが親権者にふさわしいか判断していきます。
| 母性優先の原則 | 子どもの年齢が低いほど、母親が親権を持つ方が相応しいという考え
ただし最近では、父親であっても母親の役割を果たせる場合は、父親に親権を認める判例が出ている |
| 継続性の原則 | 子どもの養育環境に大きな変化がないことが望ましいという考え
離婚前もしくは別居後の生活が安定していたと判断されれば、それらの生活を維持できる方が子どものためになるとみなされる |
| 兄弟姉妹不分離の原則 | 子どもが複数いる場合は、一緒に育ってきた兄弟姉妹と離婚後も暮らせるほうが子どものために望ましいという考え |
| これまでの監護実績 | 離婚前まで適切に子どもの世話をしてきたという実績が重要視される |
| 親権者の健康状態 | 子どもを適切に養育するためには、親権者の心身の健康状態も重視される
病気で入退院を繰り返しているケースや、精神疾患のため安定して子どもを養育できないような場合には、親権者としてふさわしくないと判断される |
| 子どもの意思 | 15歳以上の子どもの場合、裁判所はどちらの親と一緒に暮らしたいか確認し、子ども自身の希望が重視される |
| 面会交流についての寛容性 | 別居親との定期的な面会は子どもの心身の成長においてとても重要だという考えから、離婚後の面会交流により協力的な親の方が親権獲得に有利になる |
親権獲得で重視されるポイントや父親が親権を取れる確率については、こちらの記事を参考にしましょう。
「父親が親権を取れる確率は?重視されるポイント・親権獲得のためにすべきことを解説」
【養育費】子どもがいる場合
子どもを監護しない側の親は、子どもの生活費や教育費として、離婚後は養育費を支払わなければなりません。こちらでは養育費の金額の決め方や、支払を拒否できるケースについて解説してきます。
金額の算出方法
養育費の金額は、離婚時に双方が合意すればいくらで決めても構いません。とはいえ収入には限りがあり、なるべく支払いを抑えたいと考える人もいるでしょう。厚生労働省がまとめた「全国ひとり親世帯等調査の結果」によると、養育費の平均月額は、母子家庭で43,707円、父子家庭で32,550円となっています。
具体的に養育費の金額を決める場合には、裁判所が公表している「養育費算定表」を元に算出する方法が一般的。子どもの年齢と人数を元にして該当する算定表を選択し、養育費支払い義務者と権利者それぞれの収入が交わる部分で金額を見ます。
養育費の相場が知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚時の養育費の相場が知りたい!ケース別の相場や増額方法、請求方法とは?」
減額できるケース
養育費の支払いは、基本的に拒否できません。養育費というのは子どもの生活に欠かせないお金だからです。とはいえ離婚後の状況の変化など様々な事情により、養育費の減額請求が認められる可能性があります。
- 義務者の収入が想定外の事情で減少した
- 義務者が再婚し、再婚相手が扶養家族となった
- 義務者が再婚し、再婚相手との間に子どもが生まれた
- 義務者が再婚し、再婚相手との子どもと養子縁組した
- 権利者の収入が、養育費算定時よりも大幅に増えた
- 権利者が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組した
このような状況となり養育費の減額を希望する場合は、まずは相手方に減額したい旨の交渉をしてください。交渉がまとまらないときには、家庭裁判所に「養育費減額調停」を申し立てるという方法があります。
養育費の減額請求の詳しい手続き方法については、こちらの記事を参考にしてください。
「再婚で養育費を減額できる?減額請求の方法と勝手に減額されたときの7つの対処法」
【面会交流】決めておくべきこと
離婚後は別居親と子どもが定期的に会って、交流を持つ機会を設けることも重要です。離婚原因によっては「子どもと会わせたくない」と思う方もいるでしょうが、子どもの成長や幸せのためにも、離婚時には面会交流について取り決めをしておきましょう。
決める内容
面会交流で決めるべき内容には、次のような項目があります。
- 面会交流の頻度
- 面会交流の時間や場所
- 連絡方法
- 都合が悪い時の対応
- 学校行事へ参加するかどうか
- 宿泊・旅行は可能かどうか
- 祖父母との面会をどうするか
- 交通費の負担はどうするか(遠方の場合)
他にも「相手の悪口を子どもに言わない」「急な宿泊はさせない」など、個別にルールを決めておくのもいいでしょう。
面会交流を拒否したいと思っている方は、こちらの記事を参考にしてください。
「面会交流を拒否したい!子供に会わせないことの違法性と対処法を解説!」
【離婚慰謝料】請求の可否と請求方法
離婚時に相手に慰謝料を請求したいと考える人もいるでしょう。こちらでは請求可能なケースや金額の相場について見ていきます。
有責配偶者に請求可能
謝料は、離婚時に常に発生するわけではないということをご存じですか?単なる性格の不一致や価値観の違いなど、どちらが悪いといえないケースでは慰謝料は発生しません。離婚時に慰謝料が請求できるのは、浮気やDVなどの不法行為によって明らかに離婚の原因を作った「有責配偶者」に限られます。
請求可能なケースと相場
次のようなケースでは、離婚時に慰謝料請求が可能です。請求する慰謝料の相場と共に見ていきます。
| 離婚原因 | 内容 | 慰謝料の相場 |
|---|---|---|
| 不貞行為(浮気や不倫) | 配偶者以外の異性と性交渉を伴う浮気や不倫があった場合 | 100万~300万円 |
| DV・虐待 | 身体への暴力の頻度や期間、けがの程度によって変動
治療費や休業による損害金、後遺障害に対する慰謝料請求も可能 |
50万~300万円 |
| モラハラ | 暴力や暴言がない場合のモラハラでは、証拠の確保がポイント | 50万~120万円 |
| 悪意の遺棄 | 浪費やギャンブルなどで生活費を入れない
健康なのに家事や仕事をしない 理由もなく家出をする・一緒に暮らすのを拒否する・家を追い出す |
20万~200万円 |
| 性交渉の拒否(セックスレス) | 正当な理由なく性交渉を拒否する
単独では離婚理由として認められにくく、証拠が取りにくい |
0~100万円 |
上記以外の借金問題や嫁姑問題での慰謝料請求では、相場は50万~200万円ほどです。
離婚慰謝料の相場について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「離婚慰謝料の相場が知りたい!離婚理由や婚姻期間による相場・金額をアップさせるポイントを解説」
証拠の確保がポイント
離婚慰謝料を請求する場合には、証拠の確保がポイントになります。相手が交渉によって慰謝料を支払ってくれない場合、最終的には裁判を起こす必要があるため。裁判では、第三者でも分かる客観的な証拠が必須です。もし慰謝料請求を考えているのであれば、相手に離婚を切り出す前に証拠を確保しておいた方がいいでしょう。
例えば相手の不貞行為が原因で離婚を考えているときには、次のような証拠が必要です。
| 証拠の確度 | 証拠の内容 |
|---|---|
| 裁判で有効な確実性の高い証拠 |
|
| 複数を組み合わせることにより浮気が類推できる証拠 |
|
妻の浮気で離婚を決意したときのポイントは、こちらの記事を参考にしてください。
「妻の浮気で離婚を決意したら…親権・慰謝料など損をしないために取るべき行動」
【婚姻費用】別居中の生活費
別居時に夫婦のうちで収入の低い側は、収入の多い側に対して「婚姻費用」を請求できます。婚姻費用の負担は、夫婦の同居、協力及び扶助義務に基づくもので、別居中であっても互いの生活費を分担する必要があります。
婚姻費用で負担するのは食費や日用品などの生活費の他、子どもの養育費や教育費も含みます。
金額の算出方法
婚姻費用の金額は、裁判所で定めている「婚姻費用算定表」で算出できます。基本的な計算方法は養育費算定表と同様です。
婚姻費用をもらい続けたいという方は、こちらの記事を参考にしてください。
「婚姻費用をもらい続ける方法は?損しないための対抗策とよくある質問に答えます!」
離婚を切り出す前に…やっておくべき離婚準備
スムーズに離婚するためには、相手に離婚を切り出す前に次のような準備をしておいた方がいいでしょう。
証拠集め・財産調査
離婚を相手に切り出す前には、離婚原因についての証拠を確保しておきましょう。証拠は離婚を認めさせるのに役立ち、慰謝料請求や財産分与の場面でも有利に働きます。別居したり相手に離婚を切り出してからでは、証拠集めが難しくなるので、相手が油断しているうちにしっかりと確保しましょう。
同時に、相手の財産についての調査も必須です。相手が持っている財産をきちんと把握していないと、財産分与で不利になる可能性があるため。また子どもの養育費を請求する場面でも、相手の財産によって請求金額が変動します。具体的には次のような方法で、財産を調査してください。
- 預貯金(通帳のコピー)
- 収入を証明する書類(源泉徴収票・確定申告書・納税証明書など)
- 不動産登記簿
- 生命保険証書
- 証券口座に関する書類
財産分与で不利にならないためのポイントは、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚時に貯金を隠すことは可能?財産分与の基礎知識と不利にならない方法」
別居・離婚準備
相手に離婚を切り出す前には、別居や離婚の準備を進めておく方がスムーズに次の行動に移せます。具体的には次のような準備をしておくといいでしょう。
- 住む場所の確保(賃貸・実家)
- 別居費用の確保
- 子どもの学校・幼稚園・保育園・習い事の調整
- 仕事(収入)の確保
別居に必要な準備に関して詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。
「別居に必要な準備をシチュエーション別に解説!別居に関する注意点とは?」
ひとり親家庭が利用できる制度をチェック
離婚後子どもを一人で育てていくことになった場合、自分の収入や受け取る養育費だけでは十分でない可能性があります。そこで事前にひとり親家庭が利用できる公的制度について調べておくといいでしょう。
- 児童手当
- 児童扶養手当
- 特別児童扶養手当
- 障害児童福祉手当
- 児童育成手当
- 住宅手当
- 医療費助成制度
- こども医療費助成制度
- 税金・国民年金・国民健康保険の減免
- 上下水道の割引
- 交通機関の割引
離婚後の児童手当、児童扶養手当の手続き方法については、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚後の児童手当・児童扶養手当の手続きについて|ケース別の変更方法と基礎知識」
離婚後の戸籍・姓を選ぶ
女性が離婚する場合、自分と子どもの戸籍や姓(名字)どうするかについて、事前に考えておきましょう。というのも夫が筆頭者の戸籍に入っている場合、離婚によって夫の戸籍から抜けてしまうため。具体的には次のような方法があります。
| 戸籍 | 姓(名字) |
|---|---|
| 結婚前の実家の戸籍に戻る
自分が筆頭者の新しい戸籍を作り、そこに入る |
結婚前の旧姓に戻る
結婚時の姓のままにする |
結婚前の実家の戸籍に戻る場合には、旧姓に戻す必要があります。一方自分が筆頭者の新しい戸籍を作る場合には、姓をどちらにしても問題ありません。
夫婦の間に子どもがいる場合、両親が離婚しても、子どもの戸籍や姓は夫側のままで変わりません。子どもを連れて離婚する場合には、何も手続きをしないと母親と子どもの戸籍や姓が異なる状態になってします。そのままだと様々な不都合が出てくるため、子どもと同じ戸籍・姓にするためには次のような離婚後の手続きが必要です。
- 離婚後に自分が筆頭者の新しい戸籍を作成
- 家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」を申請
- 役所に入籍届を提出
自分と子どもの戸籍・姓を変更する手続きについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚後の戸籍はどうなる?チャート式選択肢と子どもの戸籍・名字について徹底解説」
円満離婚をするためのポイント
なるべくスムーズに離婚するには、円満離婚を目指すのがポイント。こちらでは円満離婚をするために必要なコツについて見ていきます。
離婚条件に優先順位を付ける
スムーズに離婚するためには、自分なりに離婚条件に優先順位を付けておくといいでしょう。夫婦が離婚する場合、財産分与や子どもの親権など、様々な離婚条件を取り決めなければなりません。このような場面ですべて自分の希望通りの条件を通そうと思うと、離婚協議がまとまらない可能性があります。
そのためスムーズに離婚を成立させるには、どこかで譲歩する必要も。相手と離婚の協議を始める前には、自分自身で離婚条件に優先順位を付けておくと話し合いがスムーズに進みます。親権などどうしても譲れない条件については強く主張しつつ、慰謝料や財産分与などの条件では都度譲歩することで、離婚を早期に成立させられる可能性が高まります。
相手に切り出すのは適したタイミングで
離婚を相手に切り出すのは、適したタイミングで行うのがベストです。離婚を切り出す最適なタイミングは、夫婦それぞれで異なるので一概には言えないものの、子どもが自立したときや相手が定年退職したときなどが適したタイミングと考えます。
とくに離婚話は感情的になりやすい事柄なので、子どもがいない場所でお互いに時間があり冷静に話し合いできるときに話し合いをしましょう。
離婚を切り出すのに適したタイミングについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚を切り出すのに適したタイミングは?切り出す前の注意点とケース別対処法」
場合によっては何度も話し合いをする
突然離婚したいと相手に切り出しても、その場で離婚の合意が得られるケースはほとんどありません。場合によっては時間をかけて何度も離婚の話し合いをすべきでしょう。まずは相手が離婚を拒否する理由を明らかにし、その理由ごとに離婚を納得させるための話し合いを継続すべきでしょう。
また自分が離婚したい理由を明確にし、やり直すのは不可能だということを冷静に伝えるのもポイント。離婚条件を譲歩して、相手に離婚を納得してもらうという方法もあります。
離婚を相手に納得させる方法については、こちらの記事を参考にしてください。
「離婚を夫や妻に納得させる9つの言葉|拒否する理由や心理学的交渉術を知ってスムーズな離婚を」
別居を検討する
相手と冷静に離婚の話し合いができないときや、相手のDVやモラハラがあるときには離婚前に別居を検討しましょう。また離婚を切り出した後に一緒に暮らすのが苦痛になったという場合や、離婚調停・離婚裁判に進む場合にも別居した方がいいでしょう。
別居期間が長くなると、それ自体で法定離婚事由の一つである「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。また別居によって余計な喧嘩が減ったり、双方が冷静に離婚について考えるきっかけになることも期待できます。
DV夫と早く安全に離婚する方法は、こちらの記事を参考にしましょう。
「DV夫と離婚したい…早く安全に離婚するための手順・相談先・気になるポイントを徹底解説」
早期に弁護士に相談
円満離婚を目指すには、早期に弁護士に相談するのが有効です。相手と顔を合わせて離婚の協議を進めるのは精神的・肉体的に負担が大きい場合には、弁護士があなたの代理人として話し合いを進めてくれます。また離婚条件についても、それぞれの状況に応じて適切な条件をアドバイスしてもらえます。
実際に離婚調停や離婚裁判に進んだ場合には、裁判所とのやり取りや書類の作成、代理人としての対応を代行してもらえます。離婚問題に強い弁護士のサポートにより、適正な条件でスムーズに離婚が成立する可能性が高まります。さらに精神的な負担や労力も大幅に軽減されるはずです。
離婚時に依頼したい弁護士の選び方については、こちらの記事を参考にしてください。
「離婚時に依頼したい弁護士の選び方|相談前・相談時のポイントと費用に関する注意点を解説」
まとめ
離婚の仕方には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚があります。そして裁判離婚には、判決離婚・和解離婚・認諾離婚の3種類があります。それぞれにかかる期間や手続きの流れ、費用などが異なるので事前にチェックしておきましょう。
相手に離婚を切り出す前には、離婚条件について考えておくといいでしょう。共有財産を調査して財産分与を有利に進めてください。子どもがいる場合は親権や養育費、面会交流についても検討してください。相手に慰謝料を請求したい方は、原因となった証拠の確保が必須です。離婚前に別居を検討する場合は、別居した時点で婚姻費用の請求を忘れずに。
また離婚後の暮らしについての準備やひとり親家庭が利用できる公的支援制度のチェック、自分と子どもの戸籍・姓についてもしっかりと考えてください。円満離婚を目指すためには離婚の切り出し方や離婚条件に優先順位を付けるのもポイント。またなるべく早い段階で、弁護士に相談するのもおすすめです。